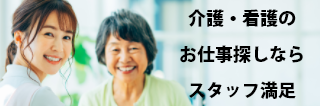いくつからが高齢者なのか【カイゴのゴカイ 13】

高齢者とは
介護ということを考える際に、普通ならいくつくらいから介護が必要なのかとか、そもそもいくつからが高齢者というべきなのかということを知っておくに越したことはない。
今時、65歳で高齢者だと思う人は、少なくともそうなってしまった人にはまずいないだろう。
思ったより、65って若いんだなというのが正直なところだろう。
実際、私も63になるが、年寄りになった気がほとんどしない。
健康寿命ということばがある。
厚生労働省が2019年に発表したところによると、日本人の健康寿命は男性が72.68歳、女性が75.38歳とのことである。
この年の日本人の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳なので、男性は約9年、女性は約12年健康でない老人の期間があることになる。
これを聞くと、寝たきりや要介護の期間が10年くらいあるのかと思うことだろう。
健康寿命とは
実は、この健康寿命というのは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことを指す。たとえば腰痛で日常生活が制限されるとか、高血圧で食べたいものを我慢するとかいうものもこれに含まれる。
ただ、これは主観的な要素も強い。
たとえば高血圧で食べたいものをがまんするというのは、人によっては日常生活が制限されていると思うだろうし、ちゃんと歩けるし、仕事もできているとい場合、多少のがまんはしているが、日常生活が制限されているとは感じない人もいるだろう。
実は、この健康寿命というのは、「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか?」というアンケートに「ある」と回答した人は不健康、「ない」と回答した人は健康ということで集計したものだ。
先ほどの食べたいものをがまんするというのも、その人がそれをどう感じているかで、健康寿命に達してしまったか、まだ健康なのかが違ってくる。
私は63歳だが、高血圧と糖尿病と心不全という病気を抱えている。
だが、塩分はまったく控えていない(たまたま、利尿剤という薬を飲んでいるため、むしろナトリウムは低いので)し、毎晩飲みたいだけワインを飲んでいる(といっても、酒に弱いのでボトル半分で眠くなってしまうから、そのくらいしか飲んでいないが)し、カロリー制限もしていない。
普通に医者のいうことを聞いていれば、塩分もワインもカロリーも制限されるから「日常生活に影響がある」と答える人が多いだろう。
こういう制限を受け入れる人のほうが、私より血圧も血糖値も正常に近い値になるだろう。ところが、アンケートで「影響がある」と答えてしまうと、健康寿命に達してしまう。
私のほうがデータが悪いのに、自分で勝手に制限をしていないので、「影響がある」とは、答えない。
心不全については、利尿剤という薬を飲んでいるおかげで、症状がなくなった。歩いていて、息が切れることもなくなったし、仕事にも差し支えないので、人一倍働いている。だから、やはり日常生活に影響があるとは答えない。
ただ、利尿剤のおかげで、尿がたくさん出るので、1時間に一回以上トイレに行く。またそれを補わないと脱水になるので、水やお茶のペットボトルは手放せない。
ただ、自分としては、会議中に堂々とトイレにいくし、日常生活に制限があるとは考えない。これだって、日常生活に制限が生じたと考える人もいるだろう。
自立できなくなる年齢
いずれにせよ、厚生労働省がいう健康寿命というのは、このような人それぞれの主観的なものだし、決して、人の介護や支援が必要になる(要介護や要支援の認定を受ける)年齢という意味ではない。また、いわゆるよぼよぼの高齢者になる年齢という意味ではない。
男性の72歳や女性の75歳というと、むしろ何か病気を抱えて薬を飲むことはあっても、当たり前に歩けるし、働くこともほとんどの人ができる年齢だ。
では、多くの人がイメージする、自立できなくなる年齢が健康寿命ということになるとどのくらいが平均的なものなのだろうか?
2012年に、高齢労働省が65歳の人が亡くなるまでの間、要介護認定を受けずに自立している期間と、要介護認定を受けて自立できなくなった期間が、それぞれどれだけあったかを調査している。
それによると、65歳男性の平均余命は18.9年。そのうち自立している期間が17.2年、自立できなくなった期間が1.6年だった。女性の場合は、平均余命が24.0年。そのうち自立している期間が20.5年、自立できなくなった期間が3.4年だった。
自立している期間を健康寿命と考えると、男性の場合、65+17.2で82.2歳が本当の健康寿命ということになる。女性の場合は、65+20.5で85.5歳が健康寿命だ。
親の介護などを考える場合、平均的にみると男性なら82歳以降、女性なら85歳以降は介護を覚悟しないといけないことになるが、逆にいうと男性なら82歳まで、女性なら85歳までは自立していられると考えていい。
逆にいうと、そのくらいの年齢までは年寄り扱いしなくていいと言えるかもしれない。
心理的な年齢
これを考えたら、前にも述べたが75歳になれば認知機能テストを押し付けて、できなかったら免許を取り上げるとか、テストに関係なしに、75歳以上になれば免許の返納を迫るというのは、あまりに早いことがわかる。
心理的な年齢という考え方もある。
2020年現在の日本人の中位年齢は、48.6歳である。現在はもう少し上がっているはずだ。
要するに日本人の中で上から数えて真ん中の人の年齢が48.6歳ということになる。48.6歳より上の人は、自分がなんとなく、歳をとったなとかおじさんになったなと感じるだろうし、それより若い人は、まだまだ若造だと感じるだろう。
サザエさんは1951年から朝日新聞の朝刊で連載されたが、その時の設定でサザエさんは24歳、マスオさんは28歳だったとされる。
実は、1950年当時の日本人の平均年齢(おおむね真ん中くらいの年齢)は26歳だった。つまり、ものの見事にサザエさんは平均より2歳若く、マスオさんは2歳上という平均的日本人を描いているのだ。
今はそれが48歳くらいになっているので、サザエさんもマスオさんも40代に見える。
日本人の平均くらいの顔から思い浮かべる年齢が、日本人の平均年齢が上がるとともに上がってくるということだろう。
高齢の感覚と人口比率
実際、日本人は全般的に若返っている。SMAPの5人はおおむねこのくらいの年齢で、一番上の中居正広が51歳、一番若い香取慎吾が46歳だ。
それに対して、波平さんは54歳だがすっかりおじいさんに見える。SMAPの5人が、この年齢になっても外見上は今と大きな変化はないだろう。
当時は、55歳以上の人が人口の1割くらいしかいなかったのだ。
以前、高齢者を専門にする先輩の医師が、65歳という年齢で切って、高齢者という風にしてしまうより、人口の上から1割を高齢者とする方が、肌感覚に合っているのではと主張されていたことがある。
私もそれが妥当に思う。心理的な年齢というのは周囲との比較で決まるとすれば、人口の上から1割の人は、周りを見渡して、自分より上が1割しかいないで、年下が9割ということになれば、自分を年寄りだなという感覚になるだろうし、周囲から見ても年寄りと見えるのではないだろうか?
波平さんは1950年当時は、人口の上から1割くらいのところにいたので、年寄りくさいということになるのではないだろうか?
日本が高齢化社会に入った1970年には65歳以上の人が人口の7%しかいなかった。当時であれば、60代前半で年寄りの仲間入りと感じ、周囲からそう見える人は少なくなかっただろう。名優加藤嘉が『砂の器』という日本の映画史上に残る名作で、主人公の年老いた父親を演じたのは61歳の時だった。演技とはいえ、おじいさんにしか見えなかったのを覚えている。
80歳の壁
さて、毎年、敬老の日になると総務省が、高齢者の人口推計を発表するが、それによると、80歳以上は27万人増の1259万人で、割合が10・1%と初めて人口の10%を超えたとのことだ。
この心理的な年齢という考え方では、80歳になって初めて、上から1割に達するということになる。
そのくらいの年齢になって、本人も周囲も高齢者という感覚になるということだ。
私も『80歳の壁』という本を書いてベストセラーになったが、70代までの間は、そんなに中高年の頃と比べて、体力や知力は変わらないと思っている人が多いようだが、80歳くらいになると、衰えを覚え始めるようだ。そこに「壁」を感じるというということだろう。
実際、コロナ自粛によって、3年以上も日本人は、家に閉じこもるような生活を強いられたが、70代の人なら足腰が弱る(フレイルと呼ばれる状態)ことはあっても、要介護状態にはならないが、80代だと要介護になってしまった人がかなりの数でいるようだ。
実際、コロナ前から要介護高齢者も80代から激増する。
70代で不幸にして要介護状態に入ってしまう人もいるが、やはり80歳からが、介護も含めて年寄りとして扱うことが必要な高齢者という時代に入ったということではないだろうか?
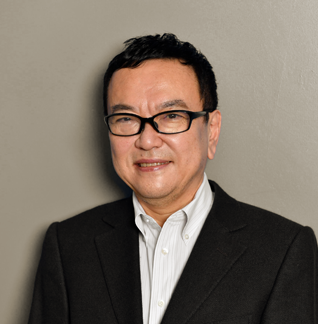
著者
和田 秀樹(わだ ひでき)
国際医療福祉大学特任教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科医師を歴任。
著書に「80歳の壁(幻冬舎新書)」、「70歳が老化の分かれ道(詩想社新書)」、「うまく老いる 楽しげに90歳の壁を乗り越えるコツ(講談社+α新書)(樋口恵子共著)」、「65歳からおとずれる 老人性うつの壁(毎日が発見)」など多数。
この記事の関連記事



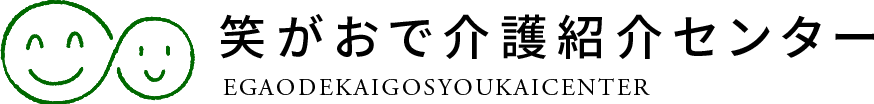




 0120-177-250
0120-177-250