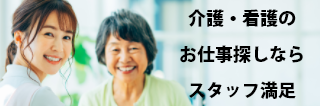認知症の発病を食い止めるには【カイゴのゴカイ 2】

認知症は年齢が高くなると割合が上がる
現実に、長年、老年医療をやっていると、病気にかかるというのと、発症するのは違うこともよくわかる。
コロナにしても、PCR検査が陽性なのに無症状の人がたくさんいた。そして、何事もなかったように、その後も元気でいることがほとんどだ。
B型やC型の肝炎ウィルスなどをもっている人は、今は無症状でも、ちゃんとした処置をしておかないと、のちに肝炎や肝硬変、ひどい場合は肝がんになってしまう。しかし、ならないで済む人もいる。
認知症の場合、歳をとるほど発症の可能性は高くなる。
東京都健康長寿医療センターによると、80歳代の後半であれば男性の35%、女性の44%、95歳を過ぎると男性の51%、女性の84%が認知症であることが明らかにされている。
テストをすれば、そのくらいの認知症がいることになる。
もちろん、それ以降も認知症の割合が増え続ける。
95歳をすぎて男性の約半分が認知症になっていないのだが、若いころと比べて知的機能の低下や記憶力の低下が起こっていない人はいないだろう。
頭を使い続けることが重要
実際、前回も問題にしたように、85歳を過ぎてアルツハイマー型の脳の変性が起こっていない人はいない。
そして、私も長年、毎年100枚くらいのCTやMRIなどの脳の画像を見ているが、この年代で、脳が縮んでいない人はいないし、それどころかその多くはかなり縮んでいる。
しかし、テストで認知症と診断されるレベルまで脳の機能が落ちる人は4割くらいしかいない。
アメリカの別の調査では、日常生活に支障が出るレベルの認知症の人は、85歳以上の16%しかいないということだ。
これは何を意味するかというと老化によってダメになった脳でも、それなりに使えるということだ。
人間の脳は、多く見積もっても1割くらいしか使っていないとされる。
うまく使えば、アルツハイマー病に侵され、脳がかなり委縮していても、少なくとも実用機能は保たれるということだ。そして95歳になっても男性の約半数が、テストをクリアできる。
いっぽう、脳の老化に勝てないで、認知症になってしまう人も85歳以上の4割、90歳以上の6割いるということだ。
この差はなんなのだろう。
おそらくは、頭を使い続けるかどうかだ。
歳をとればとるほど、人間のさまざまな機能は使わなかったときの衰え方が激しくなる。
たとえば、コロナ自粛を2年以上していても、50代くらいまでの人なら歩けなくなることはない。
ところが60代になると前より脚力が落ちたと自覚する人は少なくないだろう。
これが70代になると本当にふらついたり、歩けなくなる人さえいる。そして80代になるとかなりの数の人が外で歩けなくなったことを実感する。
脳も同じで、コロナ自粛で会話が減ることで、歳をとるほどボケたようになったと家族が訴えるケースが多い。
2017年の国際アルツハイマー病会議(AAIC)において、ランセット国際委員会が「難聴」が「高血圧」「肥満」「糖尿病」などとともに認知症の危険因子の一つに挙げられたとのことである。さらに2020年には、「予防可能な12の要因の中で、難聴は認知症の最も大きな危険因子である」という指摘もなされている。
これも耳が聞こえにくくなると、コミュニケーションが減ったり、相手が話していてもよく聞こえないから脳の刺激にならないことが原因だろう。
脳が委縮したり、脳にアルツハイマー型の変性が生じても、脳をきちんと使っていれば、認知症になるのをかなり遅らせられることが可能だというのは、私の長年の臨床経験と合致する。
CTやMRIなどの画像を見て、同じくらい脳が委縮していても、かなり頭がはっきりしている人も、相当ボケたようになっている人もいるが、やはりふだん頭を使っているかどうかの差は大きいようだ。
ただ、レーガン元大統領やサッチャー元首相が認知症になったように頭を使っている人も認知症になる。
実際、若年性の認知症の場合、現役でバリバリ仕事をしている人が認知症になり、どんどん進行していくことも珍しくない。
認知症、とくにアルツハイマー型の認知症の場合、やはり脳の変化が速いタイプと遅いタイプの人がいるようだ。
運悪く、進行が速いタイプのものや若年とは言わずとも、60代や70代前半で認知症になるタイプのものにかかってしまったら、どんなに頭を使っていても、認知症になるときはなってしまうのだ。
ただ、私はそれでも頭を使っていれば、それを遅らせることができると思っている。
レーガン大統領にしてもサッチャー首相にしても、もし大統領や首相にならずに、普通の隠居した高齢者として、頭を使わないでいたら、もっと早く認知症状態に陥っていたのではないかというのが私の推測だ。
89年まで大統領を務めたレーガン大統領は退任4年後の93年にアルツハイマー病と診断され、94年に国民にそれを公表した。当時は、相当認知症が進行していたようで、自分は今でも大統領だと思い込んでいたようだ。
ただ、妻のナンシーは、それを否定せず自宅にホワイトハウスの執務室を再現し、レーガンはそこで新聞を読むなどの「執務」を毎日数時間行うことによって症状の進行を食い止めたという。
頭を使い続けることで、会話の能力や新聞を読む能力がある程度維持されたということだ。
実際、その後の進行はゆっくりだったようで、その10年後の2004年に亡くなっている。
認知症にならないことは不可能だが、このように発病を遅らせたり、その後の進行を遅らせることができることの意味は大きい。
認知症の進行を遅らせる方法
今のご時世は、認知症になってもそう寿命が縮むことはない。
たとえば、その人の寿命が90歳だったとして、80歳で認知症になるなら認知症の罹患期間は10年ということになるが、85歳なら5年で済む。
認知症にならないで死を迎える人というのは、要するに頭を使い続けることで、認知症が発病する前に死を迎えたということなのだ(たとえば、あと5年長生きしていれば、認知症になっていたかもしれないということだ)。昔は認知症の高齢者があまりいなかったのは、日本人がそれだけ長生きしていなかったということが大きな要因だ。
進行を遅らせることにも意味があるのは言うまでもない。
次回以降で説明したいが、認知症というのは初期の間は、物忘れがかなりひどくても、会話はほとんど以前と同じようにできるし(ただし、30分前に言ったのと同じ話をすることは珍しくないが)、人の話もよく理解できる。レーガン大統領のように、本を読んだり、新聞を読んだりもできる。
日常生活のことはたいがい自分でできるので介護の必要もあまりない。
同じ80歳で認知症になり、寿命が90歳だったとして、進行が速ければ介護が必要な期間が5年とか7年になってしまうが、遅ければ、要介護の期間が1,2年で済むこともある。
認知症になったからと言って、その後はずっと介護に苦しめられるというのは誤解だ。進行を遅らせる方法はちゃんとあるのだ。
だから、頭を使い続けることが大事なのだが、実は、頭の使い方にはテクニックがある。
次回以降は、とくに歳をとってから、どのように頭を使うと認知症の発病を遅らせ、その後の進行を遅らせるかについて、私の経験から論じてみたい。
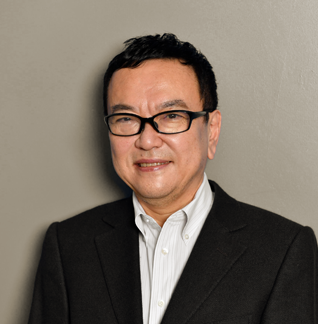
著者
和田 秀樹(わだ ひでき)
国際医療福祉大学特任教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科医師を歴任。
著書に「80歳の壁(幻冬舎新書)」、「70歳が老化の分かれ道(詩想社新書)」、「うまく老いる 楽しげに90歳の壁を乗り越えるコツ(講談社+α新書)(樋口恵子共著)」、「65歳からおとずれる 老人性うつの壁(毎日が発見)」など多数。
この記事の関連記事



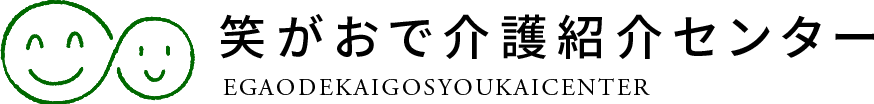




 0120-177-250
0120-177-250