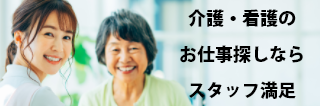認知症を予防する頭の使い方【カイゴのゴカイ 3】

頭を使い続ければ認知症の進行を遅らせられる
これまで認知症について、なることは避けることはできないが、頭を使い続けていれば、それを遅らせることができるという話をしてきた。
もちろん認知症の種類や性質にもよる。若年性のアルツハイマー病や進行のものすごい速いタイプにあたると、どんなに頭を使い続けていても、どんどん進行して、数年のうちに話が通じなくなってしまう。
ただ、経験的に言わせてもらうと、高齢者の認知症の場合は、頭を使っているほど発症は遅れるし、刺激のない、不活発な生活を送っていると大して脳が縮んでいないのにボケてしまうようだ。
認知症の発症を上手に遅らせることができて、たとえば90まで発症しなければ、それほど長くない期間に天寿を迎えることになる。
「おじいちゃん(おばあちゃん)は晩年、少しボケたところがあったけど、幸せそうに生きていたよね」みたいな話になるだろう。
少なくともボケるのを遅らせても、天寿はそう変わらないと考えられるから、ボケるのが遅れるほうが、死ぬまでに認知症である期間は短くなるはずだ。そのほうが多くの人や、その家族にとって幸せなのは確かだろう。
実際、認知症が増えたのは長寿化の影響は大きいだろう。昔はボケる前に死んでいたのだ。
また、認知症になってからでも頭を使っていると、進行は遅くなる。
認知症の進行を遅らせる生活
実は1990年代の半ばに以前紹介した浴風会病院のほかに、茨城県の鹿嶋市の病院でも月に2回ほど認知症の患者さんを診ていたことがある。
すると浴風会の患者さんは進行が速いのに、鹿嶋の患者さんの進行は遅いのだ。
浴風会病院というのは、現在では都内の高級住宅地である杉並区に位置することもあって、認知症の診断を受けると、近所に恥ずかしいせいか、家に閉じ込めておく傾向があった。
それに対して鹿嶋の患者さんは、認知症の診断を受けても好きに歩かせることができる。みんなが顔見知りなので、ちょっと迷子になってフラフラ歩いていても近所の人が連れ帰ってくれるからだ。
さらに、農業や漁業をやっている人の場合、認知症の診断を受けてからも、その仕事を続ける人も多い。本格的に病気が進んできて、仕事ができなくなってからやめるというような人が多い。
こういう生活が認知症の進行を遅らせるのだろう。
介護保険と認知症
実は、そのころは介護保険はまだ始まっていなかった。
そういうこともあって、自分の著書では認知症の発見は遅いほうがいいと書いたほどだ。認知症と早めに診断してしまうと、とくに都会では、外に出さないようになるし、仕事をまだしている人の場合、仕事をやめさせることになるからかえって本人には不幸だし、認知症の進行を進めてしまうからだ。
そういうこともあってか、認知症の臨床を行う人たちの間で、なるべく頭や体を使ったほうが、認知症の進行が遅れるという考えが共有されていたのだろう。2000年から介護保険が始まったときには、日中、なるべくデイサービスでアクティビティをやってもらうことが大きな柱となった。
もちろん、これには当時の厚生省(2001年から厚生労働省)が、要介護高齢者をなるべく施設でなく、在宅で介護すべしといわんばかりと政策スタンスだったこともあるだろう。
昼間はデイサービスで預かることで、仕事をしている女性が続けられるというのが売りなのだが、私はこのやり方では、昼は仕事、夜は介護ということで女性に24時間労働を強いかねないのでとても賛成できない。
ただ、認知症の人が家に閉じ込められることが減り、デイサービスに通うようになることが増えると、確かに介護保険が始まる前と比べて、明らかに認知症の進行は遅くなっている。
脳トレと認知症
実は、1999年にアリセプトという脳の老化を遅らせるとされている薬が発売されて、それで認知症の進行が遅れていると考える医者も多い。しかし、私はどちらかというとデイサービスのほうが有効だったと考えている。
ということで、頭を使うと認知症の発症は遅くなるし、認知症になってからの進行も遅くなるというのは、私の長年の高齢者専門の精神科医の経験から断言したい。
ということは、多くの人も考えているようで、「脳トレ」なるものが流行っているようだ。
『ネイチャー』や『JAMA』(アメリカの医学会雑誌)のような超一流の医学誌に、脳トレの効果にまつわる大規模調査の結果が発表されている。
そのうちの1つ、アラバマ大学のカーリーン・ボール氏による2,832人の高齢者に対する研究では、たとえば言語を記憶する、問題解決能力を上げる、問題処理の能力を上げるというようなトレーニングをさせた場合、練習した課題のテストの点だけは上がるのですが、ほかの認知機能がさっぱり上がらないことがわかっている。
つまり、与えられた課題のトレーニングにはなっても、脳全体のトレーニングにはまったくなっていないことが確認されたということだ。
ほかのいくつかの研究でも同様の結果が出ている。
要するに腕の筋力トレーニングばかり行っていても、腕に筋肉はついても全身の筋肉が増えたりしないのと同様に、歳をとってもある種の能力は鍛えられるが波及効果はほとんど期待できない。
だから、私は脳トレは勧めない。
ラットを使った実験でも、動物同士の接触が多くなるようにしかけられたボックスに入れると脳の変性が少なくなったというものがある。
これが人間にどれほど当てはまるかわからないが、実際に、認知症の予防やなってからの進行を遅らせるのに有効なのは、やはり人との会話である。
老人ホームなどに入ると認知症が一気に進むという話があるが、確かに慣れるまでの間、不活発な生活をすることで認知症が進む人はいるが、慣れてきて話し相手が見つかったり、職員が上手に話しかけをすると認知症の進行は遅くなるというのが著者の実感だ。
あと、前述の鹿嶋の認知症の人のように仕事を続けるというのも、認知症の発症予防や進行予防にはいい。
会話が続くということもあるが、たとえば会話もなく、黙々と農業を続けていてもよさそうだ。
これは、おそらく脳トレとちがって脳のいろいろな部分を使うからだろう。
そういう点では、料理や買い物など家事労働だって、いろいろと脳を使うから悪いことではない。
趣味だって続けるに越したことがない。
認知症になってから、将棋であれ、歌を作るのであれ、趣味を持っている人は進行が遅い傾向がある。
これはおそらく、認知症になる前にやっていても、その発症を遅らせる作用があるだろう。
ただ、認知症というのは、それでも少しずつは進んでいく。
今日できることを明日もできるように
長年、認知症の患者さんを診てきた経験でいうと、認知症介護や認知症の人の生活で一番大切なことの一つが「今日できていることを、明日もできるようにキープする」ということだ。
今日、料理ができるなら、明日も料理を続ける。今日ATMでお金が引き出せるなら明日もそれを続けるという風にだ。
実は、私が続けてほしいと思うものに自動車の運転がある。
今の法律では、認知機能テストで悪い点をとって、その後医師の診断で認知症と診断されると免許が取り上げられてしまう。
そんなの当たり前と思う人が多いだろうが、以前、レーガン元大統領が在任中もアルツハイマー病を発症していた可能性が高いと書いたように、認知症というのは軽いうちは大統領でも務まる。
重くなると人との会話も通じなくなるし、エンジンだってかけられなくなる。
要するに、認知症が一定以上重くなれば免許を取り上げるというのなら話はわかるが、運転が普通にできる程度の軽い認知症の人から免許を取り上げると、進行が速くなるだけだ。
池袋の暴走事故にしても、最近の97歳の歌人の事故にしても、認知機能テストはクリアしていた。認知機能と事故の相関はないというデータも多い。
実際、認知症の人が起こした重大事故というのはほとんど記憶にないし、インターネットで検索しても出てこない。
その当時のことを覚えていないという話は多いが、認知機能テストをクリアしているということは認知症のせいで覚えていないのでなく、意識障害(体は起きているが脳が寝とぼけている状態)によるものと考えるべきだろう。
認知症にまつわる誤解が解け、認知症でも運転ができる間は運転を続けられるような環境に早くなってほしい。
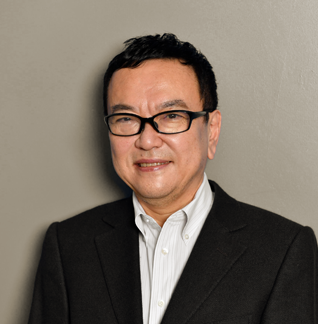
著者
和田 秀樹(わだ ひでき)
国際医療福祉大学特任教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科医師を歴任。
著書に「80歳の壁(幻冬舎新書)」、「70歳が老化の分かれ道(詩想社新書)」、「うまく老いる 楽しげに90歳の壁を乗り越えるコツ(講談社+α新書)(樋口恵子共著)」、「65歳からおとずれる 老人性うつの壁(毎日が発見)」など多数。
この記事の関連記事



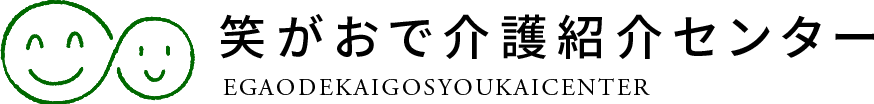




 0120-177-250
0120-177-250