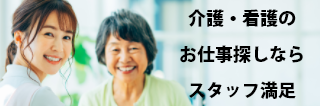иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«еҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒ®еҪ№еүІгғ»зҫ©еӢҷгҒЁжіЁж„ҸзӮ№

й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з”ҹжҙ»ж–ҪиЁӯгҒ§гҒӮгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒЁй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјүгҒ®2зЁ®йЎһгҒ«еҢәеҲҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гҒҜ60гҖң65жӯігҒ®иҮӘз«ӢгҖңиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„ж–№гӮ„иӘҚзҹҘз—ҮгҖҒеҢ»зҷӮгӮұгӮўгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№гҒҫгҒ§гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиІ жӢ…йЎҚгҒ®е°‘гҒӘгҒ„гӮҝгӮӨгғ—гҒӢгӮүеҲҶиӯІгӮҝгӮӨгғ—гӮ„й«ҳзҙҡгҒӘиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҫгҒ§зЁ®йЎһгҒҢиұҠеҜҢгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®жҰӮиҰҒгҒЁзЁ®йЎһгҖҒж–ҪиЁӯгҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„е…Ҙеұ…гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгғ»иІ»з”ЁгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…гҒ«гҒӮгҒҹгӮҠеҝ…иҰҒгҒӘгҖҢиә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҫ©еӢҷгӮ„иІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶгҒ®гҒӢиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒ®жіЁж„ҸзӮ№гӮ„иә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒ®еҜҫеҝңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®жҰӮиҰҒ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒ60гҖң65жӯід»ҘдёҠгҒ®й«ҳйҪўиҖ…гҒҢд»Ӣиӯ·гӮ„з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢж–ҪиЁӯгҒ§гҒҷгҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒЁй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјүгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҢзү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҖҢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҖҢйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҖҢгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјүгҖҚгҒ®4зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲҶйЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗ4гӮҝгӮӨгғ—гҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖ‘
| ж–ҪиЁӯ | еҲҶйЎһ | зЁ®йЎһ |
| зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | е…¬зҡ„ж–ҪиЁӯ |
еәғеҹҹеһӢгғ»ең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢпјҲгӮөгғҶгғ©гӮӨгғҲеһӢпјү ең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢпјҲеҚҳзӢ¬еһӢпјү ең°еҹҹгӮөгғқгғјгғҲеһӢ |
| жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | ж°‘й–“ж–ҪиЁӯ |
д»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚ дҪҸе®…еһӢ еҒҘеә·еһӢ |
| йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | е…¬зҡ„ж–ҪиЁӯ | йӨҠиӯ· |
| гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№ | е…¬зҡ„ж–ҪиЁӯ |
AеһӢ BеһӢ CеһӢпјҲиҮӘз«ӢеһӢпјү CеһӢпјҲд»Ӣиӯ·еһӢпјү йғҪеёӮеһӢ |
В
зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®еұ…дҪҸең°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеәғеҹҹеһӢгҒЁгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒжң¬дҪ“ж–ҪиЁӯгӮ’гӮӮгҒӨе ҙеҗҲгҒҜгӮөгғҶгғ©гӮӨгғҲеһӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжң¬дҪ“ж–ҪиЁӯгӮ’гӮӮгҒҹгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜеҚҳзӢ¬еһӢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеңЁе®…гҒ§д»Ӣиӯ·гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢж–№гҒ®е…ғгҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢж–ҪиЁӯгҒҜең°еҹҹгӮөгғқгғјгғҲеһӢгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢд»ҳеёҜгҒҷгӮӢд»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚгҒЁгҖҒеӨ–йғЁгҒ®д»Ӣиӯ·дәӢжҘӯиҖ…гҒЁеҘ‘зҙ„гҒҷгӮӢдҪҸе®…еһӢгҖҒиҮӘз«ӢиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҒҘеә·еһӢгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜеңЁе®…з”ҹжҙ»гҒҢеӣ°йӣЈгҒӘй«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒ§гҖҒд»Ӣиӯ·гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸйӨҠиӯ·гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҖҒдёҖйғЁгҒ§гҒҜзӣІгғ»иҒҙиҰҡгҒ«йҡңе®ігӮ’гӮӮгҒӨж–№гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒҜAеһӢгғ»BеһӢгҒЁгӮӮгҒ«еҒҘеә·гҒӘй«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҒҢгҒӮгӮӢAеһӢгҖҒжҸҗдҫӣгҒҢгҒӘгҒ„BеһӢгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮCеһӢгҒҜгҖҢгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚз§°гҒ§гӮӮзҹҘгӮүгӮҢгҖҒиҮӘз«ӢеһӢгҒҜиҮӘз«ӢиҖ…гӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҒд»Ӣиӯ·еһӢгҒҜиҰҒд»Ӣиӯ·иҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйғҪеёӮйғЁгҒ§гҒҜдәәе“Ўй…ҚзҪ®гӮ„еұ…дҪҸйқўз©ҚгҒ®еҹәжә–гӮ’з·©е’ҢгҒ—гҒҹйғҪеёӮеһӢгӮӮйҒӢе–¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒЁж°‘й–“ж–ҪиЁӯгҒ®2зЁ®йЎһгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒҜзӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәгӮ„ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒӘгҒ©гҒҢйҒӢе–¶гҒҷгӮӢж–ҪиЁӯгҒ§гҖҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒ®й«ҳгҒ„дәәгӮ„дҪҺжүҖеҫ—иҖ…гҒ®ж”ҜжҸҙгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘзӣ®зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
еңЁе®…еҫ©её°гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢд»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯпјҲиҖҒеҒҘпјүгҖҚгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢд»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯгҖҚгҒҜз—…ж°—гғ»йҡңе®ігғ»еҠ йҪўгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ§еңЁе®…гҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„ж–№гӮ’еҜҫиұЎгҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ«д»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜеӨ–йғЁгҒ®д»Ӣиӯ·дәӢжҘӯиҖ…гҒЁеҘ‘зҙ„гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜд»Ӣиӯ·гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒёгҒ®и»ўеұ…гӮ’жұӮгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
ж–ҪиЁӯгҒ”гҒЁгҒ«еҜҫиұЎиҖ…гӮ„йҖҖеұ…гҒ®жқЎд»¶гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®зЁ®йЎһ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒиҖҒдәәгҒЁгҒ„гҒҶзӨҫдјҡйҖҡеҝөгҒ«еҪ“гҒҰгҒҜгҒҫгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҸе®…пјҲгғӣгғјгғ пјүгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®й«ҳйҪўиҖ…ж–ҪиЁӯгҒҢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…ж–ҪиЁӯгҒ«гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҖҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҖҚгҒЁгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒҢгӮұгӮўгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүеұ…дҪҸгҒҷгӮӢгҖҢй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјүгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗй«ҳйҪўиҖ…ж–ҪиЁӯгҒ®еҲҶйЎһгҖ‘
| еҲҶйЎһ | д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯ | й«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјү |
| еҗҚз§° |
|
|
гҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж–ҪиЁӯгҒҜж¬ЎгҒ®4ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®зү№еҫҙгҖ‘
| ж–ҪиЁӯ | зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№ |
| еҹәжң¬зҡ„жҖ§ж ј | иҰҒд»Ӣиӯ·й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®з”ҹжҙ»ж–ҪиЁӯ | й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҸеұ… | з’°еўғзҡ„гғ»зөҢжёҲзҡ„гҒ«еӣ°зӘ®гҒ—гҒҹй«ҳйҪўиҖ…гҒ®е…Ҙеұ…ж–ҪиЁӯ | дҪҺжүҖеҫ—й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҸеұ… |
| ж–ҪиЁӯгҒ®иЁӯзҪ®дё»дҪ“ |
ең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“ зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәә |
йҷҗе®ҡгҒӘгҒ— |
ең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“ зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәә |
ең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“ зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәә зҹҘдәӢиӘҚеҸҜгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжі•дәә |
| еҜҫиұЎиҖ… | 65жӯід»ҘдёҠгҒ§иә«дҪ“гғ»зІҫзҘһгҒ«и‘—гҒ—гҒ„йҡңе®ігҒҢгҒӮгӮҠеёёжҷӮгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢдәә | й«ҳйҪўиҖ…вҖ» | 65жӯід»ҘдёҠгҒ§з’°еўғгҒҠгӮҲгҒізөҢжёҲзҡ„зҗҶз”ұгҒ«гӮҲгӮҠиҮӘе®…гҒ§йӨҠиӯ·гҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„дәә | 60жӯід»ҘдёҠгҒ§е®¶ж—ҸгҒӢгӮүгҒ®жҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҡиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гҒ«дёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгӮӢдәә |
вҖ»гҖҢй«ҳйҪўиҖ…гҖҚгҒҜгҖҒжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®ж №жӢ жі•гҒ§гҒӮгӮӢиҖҒдәәзҰҸзҘүжі•гҒ§е®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒзӨҫдјҡйҖҡеҝөгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢиҖҒдәәгҖҚгҒ®ж–№гҒҢеҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮ
4ж–ҪиЁӯгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰй«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢж–№гҒҢе„Әе…ҲгҒ•гӮҢгӮӢж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…гҒ®еӨҡгҒ„ең°еҹҹгӮ„дәәж°—гҒҢй«ҳгҒ„ж–ҪиЁӯгҒҜе…Ҙеұ…гҒҫгҒ§гҒ®еҫ…ж©ҹжңҹй–“гҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҖӮе…Ҙеұ…гӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢж–№гҒ®еҒҘеә·зҠ¶ж…ӢгӮ„иҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒ«еҗҲгҒЈгҒҹж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒігҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢдё»гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜж¬ЎгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҖ‘
- д»Ӣиӯ·
- гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғі
- з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙ
- йЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣ
- гҒқгҒ®д»–
д»Ӣиӯ·гҒ«гҒҜгҖҒиө·гҒҚдёҠгҒҢгӮҠгғ»жӯ©иЎҢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹ移乗гғ»з§»еӢ•гҒӘгҒ©гҒ®д»ӢеҠ©гӮ„гҖҒе…ҘжөҙгӮ„жҺ’жі„гҒ®д»ӢеҠ©гҖҒйЈҹдәӢгҒ®й…ҚиҶігӮ„гӮ№гғ—гғјгғігӮ’еҸЈгҒ«йҒӢгҒ¶гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮөгғқгғјгғҲгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
ж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢж–№гҒ«гҒҜгҖҒе°Ӯй–ҖгҒ®дҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҒӘгҒ©гҒҢеҲ©з”ЁиҖ…гҒ”гҒЁгҒ®гғЎгғӢгғҘгғјгӮ’зө„гӮ“гҒ§гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгҒ«гҒҜгҖҒжҺғйҷӨгғ»жҙ—жҝҜгғ»зүҮд»ҳгҒ‘гғ»жҺЎе…үгғ»жҸӣж°—гғ»иҰӢе®ҲгӮҠгғ»еЈ°жҺӣгҒ‘гғ»жқҘиЁӘиҖ…гҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒз”ҹжҙ»гҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮӢгӮөгғқгғјгғҲе…ЁиҲ¬гҒ§гҒҷгҖӮ
йЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮжңқгғ»жҳјгғ»еӨ•гҒ®дёҖж—ҘдёүеӣһгҖҒж—ўеҫҖз—ҮгӮ„еҡҘдёӢж©ҹиғҪгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹйЈҹдәӢгҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ3жҷӮгҒ«гҒҜгҒҠгӮ„гҒӨгҒ®жҷӮй–“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиЎҢдәӢйЈҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӨгғҷгғігғҲгҒҢгҒӮгӮӢж—ҘгҒ«гҒҜзү№еҲҘгҒӘгғЎгғӢгғҘгғјгҒҢз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®д»–гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҖҒиҝҺгғ»иІ·гҒ„зү©д»ЈиЎҢгғ»з·ҠжҖҘжҷӮеҜҫеҝңгғ»еӨ–йғЁгҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒЁгҒ®йҖЈзөЎгӮӮеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒёгҒ®е…Ҙеұ…гҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…иҖ…гғ»иә«еҶ…гғ»гҒқгҒ®д»–гҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰгҖҒжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’гҒҝгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲ
е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгҖҒ60жӯід»ҘдёҠгҒ®й«ҳйҪўиҖ…гҒ§гҒҷгҖӮж—ўеҫҖз—ҮгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҒҘеә·дёҠгҒ®дёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгҒҹгҒҫгҒҫеңЁе®…гҒ§йҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒдёҮгҒҢдёҖгҒ”иҮӘиә«гҒ«гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«еҜҫеҮҰгҒҢйҒ…гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е°Ӯй–ҖеҢ»гӮ„д»Ӣиӯ·гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢеёёеӢӨгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜиҰӢе®ҲгӮҠгӮ„гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҖҒз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’дёҖдәәгҒ§гҒ“гҒӘгҒҷгғ—гғ¬гғғгӮ·гғЈгғјгӮ„иІ жӢ…гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҗҢгҒҳж–ҪиЁӯгҒ«дҪҸгӮҖе…Ҙеұ…иҖ…гҒЁдәӨжөҒгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒ家ж—ҸгӮ„зҹҘдәәгҒҢйқўдјҡгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгӮҠгҒЁгҖҒдёҖдәәгҒҚгӮҠгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„е·ҘеӨ«гҒ§жҜҺж—ҘгӮ’жҘҪгҒ—гҒҸйҒҺгҒ”гҒӣгӮӢзӮ№гӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒҷгҖӮ
иә«еҶ…гҒёгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲ
иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©д»Ӣиӯ·гҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиә«еҶ…гҒ®ж–№гҒҢд»Ӣиӯ·гӮ„гӮұгӮўгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®жҷӮй–“гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰеҜҫеҝңгҒ«гҒӮгҒҹгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж–ҪиЁӯгҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§зӣҙжҺҘд»Ӣиӯ·гҒ®еҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҮ‘йҠӯзҡ„гҒӘжҸҙеҠ©гӮ„йқўдјҡгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹй–“жҺҘзҡ„гҒӘй–ўгӮҸгӮҠж–№гҒёеӨүеҢ–гҒ—гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жҷӮй–“гҒҢдҪҝгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒд»•дәӢгӮ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒёгҒ®иІ жӢ…гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒқгҒ®д»–гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲ
й«ҳйҪўиҖ…гҒ®еӯӨз«ӢгҒ«гӮҲгӮӢеӯӨзӢ¬жӯ»гғ»зҒ«дәӢгғ»е®іиҷ«гҒ®зҷәз”ҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒй«ҳйҪўеҢ–зӨҫдјҡгҒ®иӘІйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҮӘе®…гҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹй«ҳйҪўиҖ…гҒҢдәЎгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒзӣёз¶ҡдәәгҒ®еӯҳеңЁгӮ„жүҖеңЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫе»әзү©гҒ гҒ‘гҒҢж®ӢгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢз©әгҒҚ家е•ҸйЎҢгҖҚгӮӮеҗҢж§ҳгҒ§гҒҷгҖӮ
家гҒ®жҢҒгҒЎдё»гҒ§гҒӮгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гҒ”иҮӘиә«гҒҢгҖҒиҮӘе®…гӮ’йҒ©еҲҮгҒ«еҮҰеҲҶгҒ—гҒҰж–ҪиЁӯгҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзӣёз¶ҡгӮ„з©әгҒҚ家гҒ®е•ҸйЎҢгҒҢи§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгҖҒеӯӨзӢ¬жӯ»гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮӮдәҲйҳІгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғе…ғпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзөұиЁҲеҚ”дјҡгҖҢжі•еҢ»еү–жӨңдҫӢгҒӢгӮүгҒҝгҒҹй«ҳйҪўиҖ…жӯ»дәЎгҒ®е®ҹж…ӢгҒЁиғҢжҷҜиҰҒеӣ гҖҚ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгӮ„иІ»з”Ё
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“гӮ„зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәгҒҢйҒӢе–¶гҒҷгӮӢе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒЁгҖҒж°‘й–“гҒ®дјҒжҘӯгғ»еӣЈдҪ“гҒҢйҒӢе–¶гҒҷгӮӢж°‘й–“ж–ҪиЁӯгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮиІ»з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒӢгӮүгҒ®жҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒж°‘й–“ж–ҪиЁӯгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢй«ҳйЎҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒёе…Ҙеұ…гҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жөҒгӮҢгҒЁжүӢз¶ҡгҒҚгҒҜж¬ЎгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢжөҒгӮҢгҒЁжүӢз¶ҡгҒҚгҖ‘
- ж–ҪиЁӯгҒ®гғӘгӮөгғјгғҒгғ»иӘ¬жҳҺдјҡгҒёгҒ®еҸӮеҠ
- еёҢжңӣжқЎд»¶гҒ®ж•ҙзҗҶгҒЁжұәе®ҡ
- ж–ҪиЁӯгҒ®зөһгӮҠиҫјгҒҝгғ»иіҮж–ҷи«ӢжұӮ
- ж–ҪиЁӯгҒ®иҰӢеӯҰгғ»иӘ¬жҳҺдјҡгҒёгҒ®еҸӮеҠ
- дҪ“йЁ“е…Ҙеұ…гғ»д»®з”іиҫјгҒҝ
- еҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒ®жә–еӮҷ
- ж–ҪиЁӯеҒҙгҒЁгҒ®йқўи«Ү
- еҜ©жҹ»
- еҘ‘зҙ„
- е…Ҙеұ…
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«ж–ҪиЁӯгҒ®жғ…е ұгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҖҒз”ігҒ—иҫјгӮҖж–ҪиЁӯгӮ’зөһгӮҠиҫјгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮгғ‘гғігғ•гғ¬гғғгғҲгӮ„иіҮж–ҷгӮ’еҸ–гӮҠеҜ„гҒӣгҖҒиӘ¬жҳҺдјҡгӮ„иҰӢеӯҰдјҡгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж–ҪиЁӯгҒёиҰӢеӯҰгӮ’з”ігҒ—иҫјгҒҝгҖҒзӣҙжҺҘиЁӘе•ҸгҒ—гҒҰиӘ¬жҳҺгӮ’гҒҚгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дҪ“йЁ“е…Ҙеұ…гҒ§гҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«ж–ҪиЁӯгҒ§еҜқжіҠгҒҫгӮҠгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒҢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҒҘеә·зҠ¶ж…ӢгӮ’гҒҝгҒҰд»®з”іиҫјгҒҝгҒ®еүҚгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е…Ҙеұ…з”ігҒ—иҫјгҒҝгҒ§гҒҜгҖҒдәӢеүҚеҜ©жҹ»гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жӣёйЎһгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗе…Ҙеұ…гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжӣёйЎһгҖ‘
- е…Ҙеұ…з”іиҫјжӣё
- дҪҸж°‘зҘЁ
- жҲёзұҚ謄жң¬
- еҚ°й‘‘иЁјжҳҺ
- еҒҘеә·иЁәж–ӯжӣё
- иЁәзҷӮжғ…е ұжҸҗдҫӣжӣё
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиў«дҝқйҷәиҖ…иЁј
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁј
- иЁәзҷӮжғ…е ұжҸҗдҫӣжӣёгғ»зңӢиӯ·гӮөгғһгғӘгғј
- жүҖеҫ—иЁјжҳҺжӣё
вҖ»дёҠиЁҳгҒҜдёҖдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮ
В
е…Ҙеұ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒ«гҒҜгҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒЁгҒ—гҒҰж•·йҮ‘гӮ„дёҖжҷӮе…Ҙеұ…йҮ‘гҒҢгҖҒжҜҺжңҲгҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҒҠйҮ‘гҒЁгҒ—гҒҰжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒҢи«ӢжұӮгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®й«ҳйҪўиҖ…ж–ҪиЁӯгҒ®е…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒҜж¬ЎгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҖ‘
| ж–ҪиЁӯ | еҲқжңҹиІ»з”Ё | жңҲйЎҚиІ»з”Ё |
| зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | 0еҶҶ | 5гҖң15дёҮеҶҶ |
| д»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯ | 0еҶҶ | 8гҖң20дёҮеҶҶ |
| д»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷў | 0еҶҶ | 9гҖң15дёҮеҶҶ |
| еҒҘеә·еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | 0пҪһж•°е„„еҶҶ | 10гҖң40дёҮеҶҶ |
| йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | 0еҶҶ | 0пҪһ14дёҮеҶҶ |
| гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№ | 0пҪһ30дёҮеҶҶ | 6гҖң20дёҮеҶҶ |
| гӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ | 0пҪһж•°зҷҫдёҮеҶҶ | 12гҖң18дёҮеҶҶ |
| гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®… | 0пҪһж•°еҚғдёҮеҶҶ | 10гҖң40дёҮеҶҶ |
дёҠиЁҳгҒҜзӣ®е®үгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒҜеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒж°‘й–“ж–ҪиЁӯгҒҜиҰҸжЁЎгӮ„иЁӯеӮҷгғ»гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®зЁӢеәҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиІ»з”ЁгҒ«е№…гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҒЁгҒҜ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҒЁгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ«дҪ•гҒӢгҒҢиө·гҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иЎҢгҒҶдәәгҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒҶй«ҳйҪўиҖ…ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜгҖҒиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒ®еҪ№еүІгҒЁгҒ—гҒҰиҚ·зү©гӮ„иә«жҹ„гҒ®еј•гҒҚеҸ–гӮҠгӮ’жӢ…гҒҶдәәгӮ’жҢҮгҒ—гҖҒж–ҪиЁӯгҒ®йҒӢе–¶иҖ…гҒҢж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжі•дәәгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒж”Ҝжү•гҒ„гҒҢж»һгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«еӮөеӢҷгӮ’жӢ…гҒҶж„Ҹе‘ігӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҒ®зҫ©еӢҷгғ»иІ¬д»»
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҒҜгҖҒз·ҠжҖҘжҷӮгҒ®йҖЈзөЎе…ҲгҒЁгҒӘгӮҠе…Ҙеұ…иҖ…иҮӘиә«гҒ«д»ЈгӮҸгӮӢж„ҸжҖқжұәе®ҡгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«иӘҚзҹҘз—ҮгӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜгҖҒз—ҮзҠ¶гҒ®йҖІиЎҢгҒ«гҒЁгӮӮгҒӘгҒЈгҒҰиӘҚзҹҘж©ҹиғҪгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒҢд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«еҲӨж–ӯгӮ„жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®дәӢж•…гғ»гӮұгӮ¬гғ»з—…зҠ¶гҒ®жӮӘеҢ–гғ»ж•‘жҖҘжҗ¬йҖҒгғ»жӯ»дәЎжҷӮгҒ«гҒҜиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒ«йҖЈзөЎгҒҢе…ҘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиіғиІёдҪҸе®…гҒ®еҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢдҝқиЁјдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгӮ’иІ гҒҶгӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒж»һзҙҚжҷӮгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„зҫ©еӢҷгҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүгӮҲгҒ„пјҹ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүдёҚеңЁгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒдҝқиЁјдјҡзӨҫгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒиә«е…ғеј•еҸ—дәәдёҚиҰҒгҒ®ж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒігҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
дҝқиЁјдјҡзӨҫгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢ
дҝқиЁјдјҡзӨҫгҒЁгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®иә«е…ғдҝқиЁјгғ»еҸЈеә§з®ЎзҗҶгғ»жӯ»дәЎжҷӮгҒ®еҜҫеҝңгӮ’иә«еҶ…гҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰиЎҢгҒҶдјҡзӨҫгҒ§гҒҷгҖӮ
дәӢеүҚгҒ«гӮұгӮўгғһгғҚгӮёгғЈгғјгӮ„гӮҪгғјгӮ·гғЈгғ«гғҜгғјгӮ«гғјгҒ«дҫқй јгҒ—гҖҒе…Ҙеұ…е…ҲгҒ®ж–ҪиЁӯжӢ…еҪ“иҖ…гҒЁгӮұгӮўгғ—гғ©гғігӮ’зӯ–е®ҡгҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҖҒдҝқиЁјдјҡзӨҫгҒЁгӮӮеҗҢж„ҸжӣёгӮ’гҒӢгӮҸгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүдёҚиҰҒгҒ®ж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒ¶
дәӢеүҚгҒ«дҝқиЁјйҮ‘пјҲй җгӮҠйҮ‘пјүгӮ’зҙҚе…ҘгҒ—гҖҒиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒӘгҒ—гҒ§е…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгӮӢж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—дҝқиЁјйҮ‘гҒҜй«ҳйЎҚгҒӢгҒӨгҒҫгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹйҮ‘йЎҚгӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒжҲҗе№ҙеҫҢиҰӢдәәеҲ¶еәҰгҒ®жҙ»з”ЁгӮӮжӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жҲҗе№ҙеҫҢиҰӢдәәеҲ¶еәҰгҒЁгҒҜгҖҒйҮ‘иһҚиіҮз”ЈгҒ®з®ЎзҗҶгӮ„жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’第дёүиҖ…гҒ«д»ЈиЎҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҙеұ…иҖ…иҮӘиә«гҒҫгҒҹгҒҜгҒқгҒ®е®¶ж—ҸгҖҒеёӮеҢәз”әжқ‘гҒҢз”ігҒ—з«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒ家еәӯиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒёд»»гҒ•гӮҢгҒҹдәәгҒҢеҫҢиҰӢдәәгҒЁгҒ—гҒҰиә«е…ғеј•еҸ—дәәгӮ„з·ҠжҖҘжҷӮгҒ®йҖЈзөЎеҜҫеҝңгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒ®жіЁж„ҸзӮ№
иә«е…ғеј•еҸ—дәәпјҲдҝқиЁјдәәпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒдёҖе®ҡд»ҘдёҠгҒ®жүҖеҫ—гӮ„иіҮз”ЈзҠ¶жіҒгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢдәӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж–ҪиЁӯгӮ„з—…йҷўеҒҙгҒ®е®ҡгӮҒгҒҹгғ«гғјгғ«гҒ§гҖҒ3иҰӘзӯүд»ҘеҶ…гҒ®иҰӘж—ҸгӮ„65жӯід»ҘдёӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе№ҙйҪўгҒ®еҹәжә–гҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жқЎд»¶гӮ’гӮҜгғӘгӮўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜгҖҒжң¬дәәзўәиӘҚиЁјжҳҺжӣёпјҲйЎ”еҶҷзңҹд»ҳгҒҚпјүгӮ„дҪҸж°‘зҘЁгҖҒеҚ°й‘‘иЁјжҳҺжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҖҒжӯЈејҸгҒ«жң¬дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁјжҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒж–ҪиЁӯгҒЁйқўи«ҮгӮ„еҜ©жҹ»гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж„ҸжҖқзўәиӘҚгӮ„иІ жӢ…гғ»зҫ©еӢҷеҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®иӘ¬жҳҺгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲиӘ¬жҳҺгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜзўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷпјүгҖӮ
иә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒ®еҪ№еүІгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰдҫқй јгӮ„жӨңиЁҺгӮ’иЎҢгҒҶ
д»ҠеӣһгҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®зЁ®йЎһгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиӘҚзҹҘж©ҹиғҪгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҹж–№гҒҜиҮӘиә«гҒ§жӯЈгҒ—гҒҸеҲӨж–ӯгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гӮӮеӨҡгҒҸгҖҒиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒ®еӯҳеңЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
ж–ҪиЁӯгҒёгҒ®е…Ҙеұ…гӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгӮ„иІ»з”ЁгҒЁгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰиә«е…ғеј•еҸ—дәәгғ»дҝқиЁјдәәгҒҢеҝ…иҰҒгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘе ҙеҗҲгҒҜж—©гӮҒгҒ«е®¶ж—ҸгӮ„зҹҘдәәгҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒдҝқиЁјдјҡзӨҫгҒ®жҙ»з”ЁгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҖҢ笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ жҺўгҒ—гҒӢгӮүгҖҒе…Ҙеұ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҒҫгҒ§е№…еәғгҒҸеҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮй–ўиҘҝгҒ§е…Ҙеұ…гӮ’жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгӮүгҖҒгҒңгҒІз§ҒгҒ©гӮӮгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮдәҲз®—гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ”зҙ№д»ӢгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№



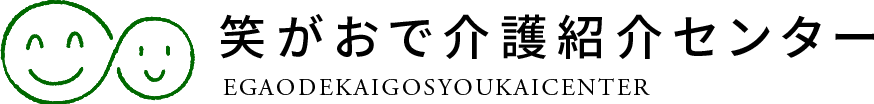




 0120-177-250
0120-177-250