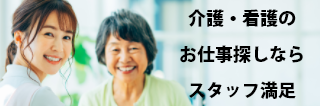гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҒ“гҒ®4еӨ§з—ҮзҠ¶пјҒз—ҮзҠ¶еҲҘгҒ«жІ»зҷӮж–№жі•гӮ’и©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬

гҖҢгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’иҖігҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢж–№гӮӮеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮзү№еҫҙзҡ„гҒӘжҢҜжҲҰгҒӘгҒ©гӮ’дјҙгҒҶзҘһзөҢеӨүжҖ§з–ҫжӮЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒ«еӨҡгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮжң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®дё»гҒӘз—ҮзҠ¶гҖҒз–ҫжӮЈгҒ®йҮҚз—ҮеәҰгҖҒгҒқгҒ—гҒҰзҸҫеңЁгҒ®жІ»зҷӮжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзҘһзөҢз–ҫжӮЈгҒ«й–ўеҝғгҒ®гҒӮгӮӢж–№гӮ„гҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІгҒ”дёҖиӘӯгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®з—…еӣ гҒЁдё»гҒӘз—ҮзҠ¶
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҖҒдёӯи„ій»’иіӘгҒ®гғүгғјгғ‘гғҹгғізҘһзөҢзҙ°иғһгҒ®еӨүжҖ§гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғүгғјгғ‘гғҹгғізҘһзөҢдјқйҒ”зү©иіӘгҒҢж¬ д№ҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§з”ҹгҒҳгӮӢйҖІиЎҢжҖ§гҒ®зҘһзөҢеӨүжҖ§з–ҫжӮЈгҒ§гҒҷгҖӮзү№еҫҙзҡ„гҒӘ4еӨ§з—ҮзҠ¶гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе®үйқҷжҷӮжҢҜжҲҰгҖҒеӢ•дҪңз·©ж…ўгҖҒзӯӢеј·еүӣгҖҒе§ҝеӢўдҝқжҢҒйҡңе®ігҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з—ҮзҠ¶гҒҜгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®жӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҸҫгӮҢж–№гӮ„йҖІиЎҢгӮ№гғ”гғјгғүгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҖҒз”ҹжҙ»гҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮӮж§ҳгҖ…гҒ§гҒҷгҖӮиЁәж–ӯгҒҜгҖҒз—…жӯҙиҒҙеҸ–гҖҒзҘһзөҢеӯҰзҡ„жӨңжҹ»гҒ«еҠ гҒҲгҖҒи„із”»еғҸжӨңжҹ»гҒӘгҒ©гӮ’з·ҸеҗҲзҡ„гҒ«иЎҢгҒ„гҖҒд»–гҒ®зҘһзөҢз–ҫжӮЈгҒЁгҒ®й‘‘еҲҘиЁәж–ӯгҒҢйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®4еӨ§з—ҮзҠ¶
- е®үйқҷжҷӮжҢҜжҲҰ
- еӢ•дҪңз·©ж…ўпјҲз„ЎеӢ•гғ»еҜЎеӢ•пјү
- зӯӢеј·еүӣпјҲзӯӢеӣәзё®пјү
- е§ҝеӢўдҝқжҢҒйҡңе®іпјҲи»ўеҖ’гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„пјү
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®з—ҮзҠ¶гҒЁгҒҜпјҹ
йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒЁйқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒЁйқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶
| е®үйқҷжҷӮжҢҜжҲҰ: зү№гҒ«е®үйқҷжҷӮгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ |
| еӢ•дҪңз·©ж…ў: еӢ•дҪңй–Ӣе§ӢгҒҢйҒ…延гҒ—гҖҒеӢ•дҪңйҒӮиЎҢгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ |
| зӯӢеј·еүӣ: зӯӢиӮүгҒ®з·ҠејөгҒҢеў—еӨ§гҒ—гҖҒй–ўзҜҖеҸҜеӢ•еҹҹгҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ |
| е§ҝеӢўеҸҚе°„йҡңе®і: е§ҝеӢўеҲ¶еҫЎгҒҢеӣ°йӣЈгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒи»ўеҖ’гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҢеў—еӨ§гҒҷгӮӢгҖӮ |
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҠ гҒҲгҖҒиӨҮеӢ•дҪңдёҚиғҪгҖҒгғӘгӮәгғҹгӮ«гғ«гҒӘеӢ•дҪңгҒ®йҡңе®ігҒӘгҒ©гҒҢгҒҝгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶
йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«еҠ гҒҲгҖҒиҮӘеҫӢзҘһзөҢз—ҮзҠ¶пјҲдҫҝз§ҳгҖҒй »е°ҝгҖҒиө·з«ӢжҖ§дҪҺиЎҖең§гҒӘгҒ©пјүгҖҒзқЎзң йҡңе®ігҖҒе—…иҰҡйҡңе®ігҖҒзІҫзҘһз—ҮзҠ¶пјҲгҒҶгҒӨгҖҒе№»иҰҡгғ»еҰ„жғігҒӘгҒ©пјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гӮӮзү№еҫҙзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒйқһйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒҜйҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ«е…Ҳз«ӢгҒЈгҒҰеҮәзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиЁәж–ӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘжүӢгҒҢгҒӢгӮҠгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®йҮҚгҒ•гӮ’жё¬гӮӢж–№жі•
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®йҮҚгҒ•гӮ’жё¬гӮӢгҒ«гҒҜгҖҒдё»гҒ«гҖҢгғӣгғјгӮЁгғігғ»гғӨгғјгғ«йҮҚз—ҮеәҰгҖҚгҒЁгҖҢз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪйҡңе®іеәҰгҖҚгҒ®2гҒӨгҒ®жҢҮжЁҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғӣгғјгӮЁгғігғ»гғӨгғјгғ«йҮҚз—ҮеәҰ
гҒ“гҒ®ж–№жі•гҒҜгҖҒз—…ж°—гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢдҪ“гҒ®гҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒ«зҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гҒҸгӮүгҒ„з—ҮзҠ¶гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒӢгҒӘгҒ©гӮ’ж•°еҖӨгҒ§иЎЁгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ гҒ“гӮҢгӮүгҒ®и©•дҫЎж–№жі•гҒҜгҖҒз—…ж°—гҒ®йҖІиЎҢе…·еҗҲгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒжІ»зҷӮжі•гӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҢ»зҷӮиІ»гҒ®еҠ©жҲҗгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жқЎд»¶гӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гӮӮгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®и©•дҫЎзөҗжһңгҒҢеҸӮиҖғгҒ«гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
| 0еәҰ | з—…ж°—гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ |
| 1еәҰ | дҪ“гҒ®зүҮеҒҙгҒ гҒ‘гҒ«з—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ |
| 2еәҰ | дҪ“гҒ®дёЎеҒҙгҒ«з—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘж”ҜйҡңгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ |
| 3еәҰ | жӯ©иЎҢгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒи»ўгҒігӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |
| 4еәҰ | ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®еӢ•дҪңгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’дәәгҒ«жүӢдјқгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |
| 5еәҰ | и»ҠжӨ…еӯҗгӮ„гғҷгғғгғүгҒ®дёҠгҒ§еҜқгҒҹгҒҚгӮҠгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҷгҒ№гҒҰгӮ’дәәгҒ«жүӢдјқгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |
з”ҹжҙ»ж©ҹиғҪйҡңе®іеәҰ
гҒ“гҒ®ж–№жі•гҒҜгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ§гҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„иҮӘеҲҶгҒ§гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҖҒгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„дәәгҒ®еҠ©гҒ‘гҒҢеҝ…иҰҒгҒӢгҒӘгҒ©гӮ’3ж®өйҡҺгҒ§и©•дҫЎгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
| 1еәҰ | гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©дёҖдәәгҒ§ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ |
| 2еәҰ | ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®дёҖйғЁгҒ§дәәгҒ®еҠ©гҒ‘гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ |
| 3еәҰ | ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§дәәгҒ®еҠ©гҒ‘гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ |
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҢгҒӘгҒңиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒӢ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҖҒи„ігҒ®зү№е®ҡгҒ®е ҙжүҖгҒ§гҖҒгҒӮгӮӢзЁ®йЎһгҒ®зҘһзөҢзҙ°иғһгҒҢжёӣгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҺҹеӣ гҒ§иө·гҒ“гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҘһзөҢзҙ°иғһгҒҜгҖҒдҪ“гҒ®еӢ•гҒҚгӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еӨ§еҲҮгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңзҘһзөҢзҙ°иғһгҒҢжёӣгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®пјҹ
гҒӘгҒңгҒ“гҒ®зҘһзөҢзҙ°иғһгҒҢжёӣгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ®и©ігҒ—гҒ„зҗҶз”ұгҒҜгҒҫгҒ гӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒӮгӮӢгҒҹгӮ“гҒұгҒҸиіӘгҒҢи„ігҒ®дёӯгҒ«гҒҹгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҺҹеӣ гҒ®дёҖгҒӨгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮ“гҒұгҒҸиіӘгҒҢзҘһзөҢзҙ°иғһгӮ’еӮ·гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒж•°гҒҢжёӣгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҖҒе№ҙйҪўгӮ’йҮҚгҒӯгӮӢгҒ”гҒЁгҒ«гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ«гҒӘгӮӢдәәгҒҢеў—гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒе№ҙйҪўгӮӮгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®зҷәз—ҮгҒ«й–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҒәдјқгӮӮй–ўдҝӮгҒҷгӮӢгҒ®пјҹ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ«гҒҜгҖҒ家ж—ҸгҒ®дёӯгҒ§еҗҢгҒҳз—…ж°—гҒ®дәәгҒҢгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒЁгҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| 家ж—ҸжҖ§гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—… | 家ж—ҸгҒ®дёӯгҒ«еҗҢгҒҳз—…ж°—гҒ®дәәгҒҢгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҒәдјқеӯҗгҒ®з•°еёёгҒҢеҺҹеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |
| еӯӨзҷәжҖ§гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—… | 家ж—ҸгҒ®дёӯгҒ«еҗҢгҒҳз—…ж°—гҒ®дәәгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҒәдјқеӯҗгҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гҖҒз”ҹжҙ»зҝ’ж…ЈгӮ„з’°еўғгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиҰҒеӣ гҒҢиӨҮйӣ‘гҒ«зөЎгҒҝеҗҲгҒЈгҒҰз—…ж°—гҒ®зҷәз—ҮгҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ |
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®жІ»зҷӮи–¬гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®жІ»зҷӮгҒ«гҒҜгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘзЁ®йЎһгҒ®и–¬гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®и–¬гҒҜгҖҒи„ігҒ®дёӯгҒ®гғүгғ‘гғҹгғігҒЁгҒ„гҒҶзү©иіӘгҒ®еғҚгҒҚгӮ’иЈңгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒиӘҝзҜҖгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз—ҮзҠ¶гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ©гҒ®и–¬гӮ’дҪҝгҒҶгҒӢгҒҜгҖҒжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ®е№ҙйҪўгӮ„з—ҮзҠ¶гҖҒд»–гҒ®з—…ж°—гҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиҰҒеӣ гӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰеҢ»её«гҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒиӢҘгҒ„дәәгӮ„иӘҚзҹҘз—ҮгҒҢгҒӘгҒ„дәәгҒ«гҒҜгғүгғ‘гғҹгғігӮўгӮҙгғӢгӮ№гғҲгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ„иӘҚзҹҘз—ҮгҒҢгҒӮгӮӢдәәгҒ«гҒҜL-гғүгғ‘гҒҢжңҖеҲқгҒ«еҮҰж–№гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
дё»гҒӘжІ»зҷӮи–¬
| гғүгғ‘гғҹгғігӮўгӮҙгғӢгӮ№гғҲ | и„ігҒ®дёӯгҒ®гғүгғ‘гғҹгғігҒ®еғҚгҒҚгӮ’зӣҙжҺҘгҒҫгҒӯгҒҰгҖҒз—ҮзҠ¶гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢи–¬гҒ§гҒҷгҖӮ |
| L-гғүгғ‘ | и„ігҒ®дёӯгҒ§гғүгғ‘гғҹгғігӮ’дҪңгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жқҗж–ҷгҒЁгҒӘгӮӢи–¬гҒ§гҒҷгҖӮ |
| COMTйҳ»е®іи–¬гҖҒMAO-Bйҳ»е®іи–¬ | гғүгғ‘гғҹгғігҒ®еғҚгҒҚгӮ’й•·гҒҸжҢҒз¶ҡгҒ•гҒӣгҒҹгӮҠгҖҒеҠ№жһңгӮ’й«ҳгӮҒгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢи–¬гҒ§гҒҷгҖӮ |
| жҠ—гӮігғӘгғіи–¬ | дҪ“гҒ®йңҮгҒҲгҒӘгҒ©гӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢи–¬гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеүҜдҪңз”ЁгҒҢеҮәгӮ„гҒҷгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |
| гҒқгҒ®д»– | еЎ©й…ёгӮўгғһгғігӮҝгӮёгғігҖҒгғүгғӯгӮӯгӮ·гғӯгғ‘гҖҒгӮҫгғӢгӮөгғҹгғүгҖҒгӮўгғҮгғҺгӮ·гғіеҸ—е®№дҪ“жӢ®жҠ—и–¬гҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘзЁ®йЎһгҒ®и–¬гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ |
д»–гҒ®и–¬гҒЁгҒ®йЈІгҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®и–¬гӮ’жңҚз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒд»–гҒ®з—…ж°—гҒ®и–¬гҒЁгҒ®йЈІгҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒжҠ—зІҫзҘһи–¬гҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’жӮӘеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®жІ»зҷӮж–№жі•
и–¬гҒ§з—ҮзҠ¶гӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгӮ„и–¬гҒ®еүҜдҪңз”ЁгҒҢе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒжүӢиЎ“зҷӮжі•гҒӘгҒ©гӮӮиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒи–¬зү©зҷӮжі•д»ҘеӨ–гҒ®жІ»зҷӮж–№жі•гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
и„іж·ұйғЁеҲәжҝҖзҷӮжі•
и„ігҒ«еҹӢгӮҒиҫјгӮ“гҒ йӣ»жҘөгҒЁиғёгҒ«еҹӢгӮҒиҫјгӮ“гҒ еҲәжҝҖиЈ…зҪ®гӮ’гғҜгӮӨгғӨгғјгҒ§гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§гҖҒи„ігҒ«йӣ»ж°—еҲәжҝҖгӮ’йҖҒгӮҠзҘһзөҢзҙ°иғһгҒ®иҲҲеҘ®гӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢжІ»зҷӮжі•гҒ§гҒҷгҖӮгӮӘгғ•зҠ¶ж…ӢгҒ§гӮӮиә«дҪ“гӮ’еӢ•гҒӢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢпјҲгӮӘгғ•зҠ¶ж…Ӣпјқи–¬гҒ®еғҚгҒҚгҒҢејұгҒҫгҒЈгҒҹзҠ¶ж…ӢпјүгҖҒи–¬гӮ’жёӣгӮүгҒӣгӮӢпјҲL-гғүгғ‘пјүгҒӘгҒ©гҒ®еҠ№жһңгӮ’жңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮж №жІ»жІ»зҷӮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒжүӢиЎ“еҫҢгӮӮи–¬гҒ®жңҚз”ЁгҒҜеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ и„іж·ұйғЁеҲәжҝҖзҷӮжі•гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®ж–№гҒҢжІ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ70жӯід»ҘдёӢгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҒL-гғүгғ‘гҒҢжңүеҠ№гҒӘгҒ©гҒ®еҹәжә–гҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ¬гғңгғүгғ‘гғ»гӮ«гғ«гғ“гғүгғ‘з©әи…ёжҠ•дёҺгӮІгғ«
и–¬зү©зҷӮжі•гҒ§йҒӢеӢ•еҗҲдҪөз—ҮгҒ®гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮұгғјгӮ№гҒӘгҒ©гҒ§з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғҮгғҗгӮӨгӮ№жІ»зҷӮгҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒиғғзҳ»з©әи…ёи·ҜгӮ’йҖ иЁӯгҒ—гҒҰгӮІгғ«зҠ¶гҒ®гғ¬гғңгғүгғ‘иЈҪеүӨгӮ’йҖҒгӮҠиҫјгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жІ»зҷӮжі•гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҖҒи–¬гҒ®е®үе®ҡгҒ—гҒҹеҗёеҸҺгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒи–¬гҒҢеҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢжҷӮй–“еёҜгҒЁеҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„жҷӮй–“еёҜпјҲгӮӘгғігғ»гӮӘгғ•зҸҫиұЎпјүгҒ®еӨүеӢ•гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒи–¬гҒҢеҠ№гҒҚгҒҷгҒҺгҒҰиө·гҒ“гӮӢдёҚйҡҸж„ҸйҒӢеӢ•пјҲгӮёгӮ№гӮӯгғҚгӮёгӮўпјүгӮӮжҠ‘гҒҲгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
MRIгӮ¬гӮӨгғүдёӢеҸҺжқҹи¶…йҹіжіўзҷӮжі•
MRIз”»еғҸгӮ’гҒҝгҒӘгҒҢгӮүгҖҒи„ігҒ«и¶…йҹіжіўгӮ’еҪ“гҒҰгҒҰзӢҷгҒЈгҒҹйғЁдҪҚгӮ’зҶұеҮқеӣәгҒ•гҒӣгӮӢжІ»зҷӮгҒ§гҒҷгҖӮи–¬зү©зҷӮжі•гҒ§еҚҒеҲҶгҒ«гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„йҒӢеӢ•з—ҮзҠ¶гҒ®з·©е’ҢгӮ’жңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒжҢҜжҲҰгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдё»гҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҖҒжІ»зҷӮгҒ§еҝғиә«гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ иҚ·гҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒ“гҒЁгҒЁжқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒӣгҒ°дҝқйҷәгӮ’йҒ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒжІ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢж–ҪиЁӯгҒҜеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®гҒқгҒ®д»–гҒ®жІ»зҷӮжі•
и–¬гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜз—ҮзҠ¶гҒҢеҚҒеҲҶгҒ«гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгӮ„гҖҒи–¬гҒ®еүҜдҪңз”ЁгҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒжүӢиЎ“гҒӘгҒ©гҒ®жІ»зҷӮжі•гӮӮйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
и„іж·ұйғЁеҲәжҝҖзҷӮжі•пјҲDBSпјү
и„ігҒ®зү№е®ҡгҒ®йғЁдҪҚгҒ«йӣ»жҘөгӮ’еҹӢгӮҒиҫјгҒҝгҖҒйӣ»ж°—еҲәжҝҖгӮ’дёҺгҒҲгӮӢжІ»зҷӮжі•гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲәжҝҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒзҘһзөҢгҒ®еғҚгҒҚгӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҖҒгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’ж”№е–„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲ
- и–¬гҒ®йҮҸгӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢ
- и–¬гҒ®еҠ№жһңгҒҢдёҚе®үе®ҡгҒ«гҒӘгӮӢгҖҢгӮӘгғігғ»гӮӘгғ•зҸҫиұЎгҖҚгӮ’ж”№е–„гҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲ
- е…ЁгҒҰгҒ®дәәгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„
- йӣ»жұ дәӨжҸӣгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢ
гғ¬гғңгғүгғ‘гғ»гӮ«гғ«гғ“гғүгғ‘з©әи…ёжҠ•дёҺгӮІгғ«зҷӮжі•
и–¬гӮ’зӣҙжҺҘе°Ҹи…ёгҒ«йҖҒгӮҠиҫјгӮҖжІ»зҷӮжі•гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒи–¬гҒҢдҪ“еҶ…гҒ«еҗёеҸҺгҒ•гӮҢгӮӢгӮ№гғ”гғјгғүгӮ’дёҖе®ҡгҒ«дҝқгҒЎгҖҒи–¬гҒ®еҠ№жһңгӮ’е®үе®ҡгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲ
- и–¬гҒ®еҠ№жһңгҒҢе®үе®ҡгҒ—гӮӘгғігғ»гӮӘгғ•зҸҫиұЎгҒҢж”№е–„гҒ•гӮҢгӮӢ
- дёҚйҡҸж„ҸйҒӢеӢ•гҒ®ж”№е–„гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲ
- жүӢиЎ“гҒҢеҝ…иҰҒ
- е…ЁгҒҰгҒ®дәәгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„
MRIгӮ¬гӮӨгғүдёӢеҸҺжқҹи¶…йҹіжіўзҷӮжі•
MRIгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒи¶…йҹіжіўгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰи„ігҒ®зү№е®ҡгҒ®йғЁдҪҚгӮ’жІ»зҷӮгҒҷгӮӢж–°гҒ—гҒ„ж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲ
- жүӢиЎ“гҒ®иІ жӢ…гҒҢжҜ”ијғзҡ„е°‘гҒӘгҒ„гҖӮ
- дҝқйҷәйҒ©з”ЁгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲ
- жІ»зҷӮгҒ§гҒҚгӮӢж–ҪиЁӯгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ
- еҠ№жһңгҒҢеҮәгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғіпјҡдҪ“гӮ’еӢ•гҒӢгҒ—гҖҒз”ҹжҙ»гҒ®иіӘгӮ’й«ҳгӮҒгӮҲгҒҶ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ®жІ»зҷӮгҒ«гҒҜгҖҒи–¬зү©зҷӮжі•гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮӮйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒйҒӢеӢ•ж©ҹиғҪгӮ’з¶ӯжҢҒгғ»ж”№е–„гҒ—гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’гӮҲгӮҠеҝ«йҒ©гҒ«йҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҖҒдҪ“гҒ®еӢ•гҒҚгӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒҷгӮӢзҘһзөҢгҒҢеҫҗгҖ…гҒ«жҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҸз—…ж°—гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдҪ“гҒҢзЎ¬гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеӢ•гҒҚгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еҙ©гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’ж”№е–„гҒ—гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®иіӘгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒ—гҒ®дёӯгҒ«жІ»зҷӮгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮ
гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒҜгҖҒйҖІиЎҢжҖ§гҒ®з—…ж°—гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘжІ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз—ҮзҠ¶гӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ—гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮз—…ж°—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӯЈгҒ—гҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҖҒеҢ»её«гӮ„е°Ӯй–Җ家гҒЁеҚ”еҠӣгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒиҮӘеҲҶгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңҖе–„гҒ®жІ»зҷӮжі•гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ гӮӮгҒ—гҖҒгғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдҪ•гҒӢеҝғй…ҚгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒҠж°—и»ҪгҒ«еҢ»её«гҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№



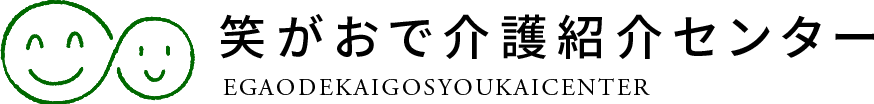




 0120-177-250
0120-177-250