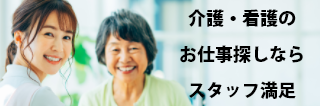ヨボヨボにされない医療【カイゴのゴカイ 28】

コロナ対策で露呈した医療現場の課題
感染症対策と要介護状態増加のジレンマ
10月に『医者にヨボヨボにされない47の心得』(講談社+α新書)という本を出したら、思った以上に反響がよく、ベストセラーになりそうな勢いだそうだ。 この連載も介護対策だけでなく、最終的には要介護になるにしても、それをなるべく遅らせる方法を伝えたいというのがテーマになっている。 ところが医者というのは、患者がヨボヨボになっても、長生きすることが第一だと考える人が多い。 そのことを象徴するのがコロナ対策だろう。 とにかく、感染を防ぐ、人がなるべく死なないようにするというのに主眼が置かれて、結果的にヨボヨボになっても知ったことではないというのが、政府や専門家会議の基本的なスタンスだった。 だから、外出や会食を徹底的に禁じ、三密を避け、さまざまな自粛を呼びかけ続けた。 結果的に日本は世界でいちばん長い自粛期間となった。 3年間の自粛生活で、要介護状態や、その予備軍のフレイル状態になった人はかなりの数に上るはずだ。 それに対して、昔から高齢者が多いことを自覚しているスウェーデンでは、集団免疫政策をとって、なるべく自粛生活をさせないようにした。 そうしないと高齢者がヨボヨボになることを熟知しているからだろう。
死なないことが最優先?
ただ、このようなとにかく死なないことが大切で(人間は必ず死ぬのだから、これは延命治療と言える)、患者がヨボヨボになっても知ったことではないというのは、感染症の専門家に限らず、医者全体に言えることのように思えてならない。
血圧と認知機能の関係性
高血圧でも元気な高齢者たち
たとえば血圧だ。 私について言うと、血圧については薬を飲まないと最高血圧が220mmHgにもなってしまうので薬は飲んでいるが、140まで下げると頭がフラフラしてしまうので、170くらいでコントロールしている。 長生きができるより、残りの人生(現在64歳である)頭がシャキッとしているほうがいいという考え方のもとである。 実は88歳にして20億円の株を運用しているデイトレーダーの藤本茂さんと対談する機会があったのだが、240以上の血圧が記録された紙を見せてくれた。 藤本さんいわく、「血圧を下げると株の勘がにぶる」とのことだった。 やはり血圧を高くしておいて脳に十分な酸素がいったほうが長生きできない(それでも藤本さんはすでに日本人男性の平均寿命より7歳も長生きしていて、まだまだ死にそうにないくらいお元気だったが)かもしれないが、頭はシャキッとする人の方がずっと多いのは私の長年の臨床経験からも言えることだ。 先日も私の本を読んで血圧の薬をやめたら朝勃ちが復活したと喜んでいた人にお会いした。
血圧と自立度の意外な関係
最近は100歳まで生きた人の研究が進んでいる。 有名なのは、慶応義塾大学医学部が行った100~108歳の百寿者163人を対象にした研究だ。 するとそのうちの半数以上が高血圧の既往があることがわかったのだが、それ以上に私が注目しているのは、身体的な自立度を調べたところ、最も自立度が高かったのは上の血圧が156~220のグループということだ。 認知症の程度も、血圧が高いほうが軽かったのだ。 血圧が高い人のほうが元気で自立できるということだろう。 さらにいうと、血圧が高い人のほうがむしろ100歳まで生きる可能性が高いことも示唆されているのだ。
血糖値と低血糖リスク
血糖値コントロールの難しさ
血糖値については朝の血糖値が300mg/dlを越えた時のみ薬を飲むようにしていて、Hba1cという過去1-2ヶ月の血糖値の平均を反映するとされる数値(5.6%未満が正常とされるが糖尿病学会では、4.6から6.2%を正常としている)については9%までにしようということで、薬や運動量などを決めている。 ただし、食生活については好きなようにしている。 これについては、アメリカの大規模調査で糖尿病の人の血糖値を薬などで下げた場合、7~7.9%がいちばん死亡率が低いことがわかっているのだが、それでも5%以上の人が低血糖の発作を起こしている(正常値まで下げるとこれが16%以上になる)というデータをみて、車の運転中の低血糖発作(これが大事故につながる)を避けるためにもう少し高めでコントロールすることにしている。 血圧や血糖値は、医者のほうは長生きのために正常まで下げろというが、これだってあてにならないし、少なくともヨボヨボになりやすいのは確かなことなのだ。
コレステロールと寿命、そして元気
コレステロール値と心筋梗塞
長生きと元気のトレードオフというものの典型がコレステロールだ。 コレステロール値が高いと心筋梗塞になりやすいということでアメリカで目の敵にされ、日本でも目の敵にされるようになったものだ。 ただ、コレステロールは男性ホルモンや免疫細胞の材料なので、この値が高いほうが男性ホルモンも歳をとっても減りにくいし、感染症にも強くなる。 命と元気のどちらを取るという場合、命を取るならコレステロールを下げることになるし、元気をとるなら高いのを放っておくということになる。
コレステロール値とがん死亡率
ただ、これはあくまでもアメリカでの話だ。 実は、コレステロール値が高いと免疫力が高くなるので、がんになりかけの細胞を免疫が殺してくれる可能性が高まる。 実際、ハワイの住民調査でもフラミンガム研究というコレステロール値と虚血性心疾患の死亡率の関係を調べた有名な住民調査研究でも、コレステロール値が高いほうががん死亡率が低いことが明らかになっている。 つまり心筋梗塞で死ぬ国はコレステロールを下げたほうがいいが、がんで死ぬ国は高めに保っておいた方がいい。 アメリカは心疾患が死因のトップだが、日本はがんで死ぬ人が急性心筋梗塞で死ぬ人の12倍もいるので、コレステロール値は下げてはいけないのだ。 ついでにいうと、コレステロールは男性ホルモンや女性ホルモンの材料なので、コレステロール値を下げると男性ホルモンや女性ホルモンが減ってしまう。 つまり元気がなくなったり、肌艶が悪くなったり、骨粗しょう症になりやすくなってしまう、つまりヨボヨボになってしまうのだ。 つまり、コレステロールは下げるとヨボヨボになるばかりでなく寿命まで縮めてしまうということである。
栄養状態と健康寿命
軽度肥満と平均余命
ヨボヨボにならないために私がもう一つ注意しているのは、栄養状態の大切さだ。 長生きという点でもBMIが25から30という日本では軽度肥満をされている人たちがいちばん40歳時点での平均余命が長いことが明らかにされているが、私が30年以上高齢者医療に従事して経験するのは、やはりふっくらしている人のほうが元気だということだ。 ついでにいうと、最近、肥満パラドックスというのが話題にされていて、太っている人のほうが心不全になってもそれによる症状の悪化が少ないという。 また下半身に負担をかけるから痩せたほうがいいとされている閉塞性動脈硬化症でも太っている人のほうがやせている人よりはるかに10年後の生存率が高いということも明らかになっている。
食生活と健康
そのため、私も、糖尿病とか高脂血症を抱えているが、食生活については好きなものを好きなだけ食べている。 そのおかげか、将来長生きできるかどうかはわからないが、仕事量は維持できているし、お世辞かもしれないが歳の割に外見も若いと言われる。 栄養状態のよさはよぼよぼにならない秘訣と信じるようになったのだが、そんな折、統合医療(東洋医療や代替医療といわれるものと従来の医療と統合した医療)の第一人者の帯津良一先生との対談の機会を得た。 帯津先生は、毎晩、お酒を欠かさず、好きなものを食べ、しめにはラーメンを食べるという生活をずっと続けておられるのだが、88歳の現在でもお元気で、現役で医者を続けておられる。 そしてふっくらとした穏やかな顔にはしわがほとんどない。 手にもしわがない。 栄養状態の大切さを改めて痛感した時間だった。 そして帯津先生は、好きなものを食べて、食べる幸せを満喫しておられる。
幸せ感と栄養状態
私もまったく同じで、ワインを飲み、おいしいものを食べ歩くことを心がけている。 身体に悪いはず(とくに糖尿病に)なのに、仕事が終わってからの食事なので食べる時刻も遅いし、お酒も入っているので食べて帰ってからすぐ寝る生活だ。 でも、幸せなのだ。 ということで、おそらくこの幸せ感と栄養状態のよさが、自分がヨボヨボになるのを遅らせ、また免疫力を上げているのだろう。 ちなみに、私はこれだけの持病を抱えながら、コロナ陽性に3回もなったが、全部、無症状だった。
長生きより元気を
長生きより、元気をとるという生活習慣は高齢になるほど役に立つと私は信じている。 実際、さまざまな調査で、長生きできないけど元気になれるというような検査データの方がむしろ生存率が高いことも明らかになっている。 高齢になったらヨボヨボにならないころを心がけたほうがよさそうだ。 もちろんヨボヨボにならないために軽い運動や頭を使うことを続けるほうが、元気にも寿命にも良い影響があるのも付け加えておきたい。
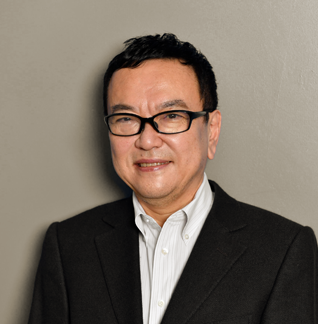
著者
和田 秀樹(わだ ひでき)
国際医療福祉大学特任教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科医師を歴任。
著書に「80歳の壁(幻冬舎新書)」、「70歳が老化の分かれ道(詩想社新書)」、「うまく老いる 楽しげに90歳の壁を乗り越えるコツ(講談社+α新書)(樋口恵子共著)」、「65歳からおとずれる 老人性うつの壁(毎日が発見)」など多数。
この記事の関連記事



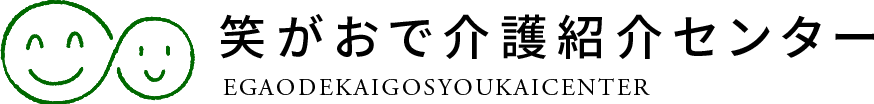




 0120-177-250
0120-177-250