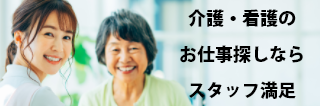д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒҜпјҹгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®зЁ®йЎһгғ»ж–ҷйҮ‘гғ»еҲ©з”ЁгҒ®жөҒгӮҢгӮ’и§ЈиӘ¬

2000е№ҙгҒӢгӮүж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ3е№ҙгҒ”гҒЁгҒ«ж”№е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№гӮ’зӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒ§ж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘдҝқйҷәж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ40жӯід»ҘдёҠгҒ®е…ЁеӣҪж°‘гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж”Ҝжү•гҒ„гҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҰӮиҰҒгӮ„зЁ®йЎһгҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гӮ„иҮӘе·ұиІ жӢ…и»ҪжёӣеҲ¶еәҰгҖҒеҲ©з”ЁжүӢй ҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”иҮӘиә«гӮ„гҒ”дёЎиҰӘгҒ®д»Ӣиӯ·гҒ§гҒҠжӮ©гҒҝгҒ®ж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІжңҖеҫҢгҒҫгҒ§гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒҜпјҹ
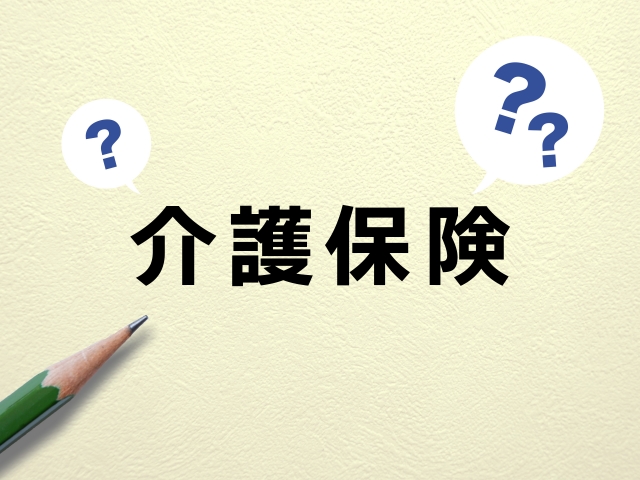
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒҜгҖҒ65жӯід»ҘдёҠгҒ§иҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙгҒ®иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹж–№гҒҢеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒҢе®ҡгӮҒгҒҹ16зЁ®гҒ®зү№е®ҡз–ҫз—…гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜ40жӯігҒӢгӮүгҒ§гӮӮеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»ж”ҜжҸҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№гҒ®зҠ¶жіҒгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒжңҖйҒ©гҒӘд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгӮұгӮўгғ—гғ©гғігҖҚгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҒ—гҒҰжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜдҪ•жӯігҒӢгӮүпјҹеҲ©з”ЁгҒ®жөҒгӮҢгӮ„е…Ҙеұ…гҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ’и§ЈиӘ¬
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®зЁ®йЎһ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘзЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҘдёӢгҒ®6зЁ®йЎһгҒ«еӨ§еҲҘгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
- д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢзӣёи«ҮгҖҒгӮұгӮўгғ—гғ©гғігҒ®дҪңжҲҗ
- иҮӘе®…гҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢ家дәӢжҸҙеҠ©зӯүгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№
- ж–ҪиЁӯгҒӘгҒ©гҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҰж—Ҙеё°гӮҠгҒ§иЎҢгҒҶгӮөгғјгғ“гӮ№
- ж–ҪиЁӯгҒӘгҒ©гҒ§з”ҹжҙ»пјҲе®ҝжіҠпјүгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒй•·жңҹй–“еҸҲгҒҜзҹӯжңҹй–“еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№
- иЁӘе•Ҹгғ»йҖҡгҒ„гғ»е®ҝжіҠгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№
- зҰҸзҘүз”Ёе…·гҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№
еҸӮз…§пјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒпјҡе…¬иЎЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒ®и§ЈиӘ¬гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гҒ«й–ўгҒҷгӮӢзӣёи«ҮгҒЁгӮұгӮўгғ—гғ©гғігҒ®дҪңжҲҗ
еұ…е®…д»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘз«ӢгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒд»Ӣиӯ·еҶ…е®№гӮ’жұәе®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢгӮұгӮўгғ—гғ©гғігҖҚгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгӮұгӮўгғ—гғ©гғігҖҚдҪңжҲҗеҫҢгҒҜгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®е®ҹж–ҪгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дәӢжҘӯиҖ…гӮ„й–ўдҝӮж©ҹй–ўгҒЁгҒ®йҖЈзөЎгӮ„иӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгҒ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгҒҢй–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
иҮӘе®…гҒ«иЁӘе•Ҹ
иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·пјҲгғӣгғјгғ гғҳгғ«гғ—пјү
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘе®…гҒ«иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·е“ЎпјҲгғӣгғјгғ гғҳгғ«гғ‘гғјпјүгҒҢиЁӘе•ҸгҒ—гҖҒд»Ӣиӯ·гӮ„з”ҹжҙ»гҒ®жҸҙеҠ©гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЁӘе•Ҹе…Ҙжөҙ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘе®…гҒ«зңӢиӯ·иҒ·е“ЎгӮ„д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎгҒҢиЁӘе•ҸгҒ—гҖҒиә«дҪ“гҒ®жё…жҪ”гҒ®дҝқжҢҒгҖҒеҝғиә«ж©ҹиғҪгҒ®з¶ӯжҢҒеӣһеҫ©гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰе…ҘжөҙгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЁӘе•ҸзңӢиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘе®…гҒ«зңӢиӯ·её«гҒӘгҒ©гҒҢиЁӘе•ҸгҒ—гҖҒеҝғиә«ж©ҹиғҪгҒ®з¶ӯжҢҒеӣһеҫ©гҒӘгҒ©гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹзҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұгӮ„иЁәзҷӮгҒ®иЈңеҠ©гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЁӘе•ҸгғӘгғҸгғ“гғӘ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘе®…гҒ«зҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҖҒдҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҖҒиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒӘгҒ©гҒҢиЁӘе•ҸгҒ—гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®иҮӘз«ӢгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨңй–“еҜҫеҝңеһӢиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘе®…гҒ«иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·е“ЎпјҲгғӣгғјгғ гғҳгғ«гғ‘гғјпјүгҒҢиЁӘе•ҸгҒ—гҖҒжҺ’жі„гҒ®д»ӢеҠ©гӮ„е®үеҗҰзўәиӘҚгҖҒж•‘жҖҘи»ҠгҒ®жүӢй…ҚгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеӨңй–“еёҜпјҲ18гҖң8жҷӮпјүгӮ’еҗ«гӮҖ24жҷӮй–“гҒ®гӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гҒҢж•ҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе®үеҝғгҒ—гҒҰгӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҡжңҹе·Ўеӣһгғ»йҡҸжҷӮеҜҫеҝңеһӢиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·зңӢиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘе®…гҒ«иЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·е“ЎпјҲгғӣгғјгғ гғҳгғ«гғ‘гғјпјүгӮ„зңӢиӯ·её«гҒҢе®ҡжңҹзҡ„гҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜйҡҸжҷӮиЁӘе•ҸгҒ—гҖҒ24жҷӮй–“дҪ“еҲ¶гҒ§еҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғқгғјгғҲгҒ®жҸҗдҫӣгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–ҪиЁӯгҒ«йҖҡгҒҶ
йҖҡжүҖд»Ӣиӯ·пјҲгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№пјү
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ»гғігӮҝгғјгҒӘгҒ©гҒ«йҖҡгҒ„гҖҒеӯӨз«Ӣж„ҹгҒ®и§Јж¶ҲгӮ„еҝғиә«ж©ҹиғҪгҒ®з¶ӯжҢҒгҖҒ家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гҒ®иІ жӢ…и»ҪжёӣгҒӘгҒ©гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹд»Ӣиӯ·гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҖҡжүҖгғӘгғҸгғ“гғӘ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢиҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯгҖҒз—…йҷўгҖҒиЁәзҷӮжүҖгҒӘгҒ©гҒ®гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғіж–ҪиЁӯгҒ«йҖҡгҒ„гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®иҮӘз«ӢгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢйҖҡжүҖд»Ӣиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢйҖҡжүҖд»Ӣиӯ·гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ«йҖҡгҒ„гҖҒйЈҹдәӢгӮ„е…ҘжөҙгҒӘгҒ©гҒ®з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮ„з”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҗ‘дёҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҒӘгҒ©гӮ’ж—Ҙеё°гӮҠгҒ§е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зҷӮйӨҠйҖҡжүҖд»Ӣиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢзҷӮйӨҠйҖҡжүҖд»Ӣиӯ·гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ«йҖҡгҒ„гҖҒз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮ„еҸЈи…”ж©ҹиғҪеҗ‘дёҠгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гӮ’ж—Ҙеё°гӮҠгҒ§е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеёёгҒ«зңӢиӯ·её«гҒ«гӮҲгӮӢиҰіеҜҹгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢйӣЈз—…гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҖҒи„іиЎҖз®Ўз–ҫжӮЈеҫҢйҒәз—ҮзӯүгӮ’жӮЈгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҒҢгӮ“жң«жңҹжӮЈиҖ…гҒ®ж–№гҒ®гҒҝгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
иӘҚзҹҘз—ҮеҜҫеҝңеһӢйҖҡжүҖд»Ӣиӯ·
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ»гғігӮҝгғјгӮ„гӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ гҒӘгҒ©гҒ«йҖҡгҒ„гҖҒиҮӘз«ӢгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйЈҹдәӢгӮ„е…ҘжөҙгҒӘгҒ©гҒ®з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮ„гҖҒз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҗ‘дёҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҒӘгҒ©гӮ’ж—Ҙеё°гӮҠгҒ§е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иЁӘе•Ҹгғ»йҖҡгҒ„гғ»е®ҝжіҠгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢ
е°ҸиҰҸжЁЎеӨҡж©ҹиғҪеһӢеұ…е®…д»Ӣиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж–ҪиЁӯгҒёгҒ®гҖҢйҖҡгҒ„гҖҚгҒЁзҹӯжңҹй–“гҒ®гҖҢе®ҝжіҠгҖҚгҖҒиҮӘе®…гҒёгҒ®гҖҢиЁӘе•ҸгҖҚгҒ®3гҒӨгҒ®д»Ӣиӯ·ж–№жі•гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰд»Ӣиӯ·гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зңӢиӯ·е°ҸиҰҸжЁЎеӨҡж©ҹиғҪеһӢеұ…е®…д»Ӣиӯ·пјҲиӨҮеҗҲеһӢгӮөгғјгғ“гӮ№пјү
гҖҢе°ҸиҰҸжЁЎеӨҡж©ҹиғҪеһӢеұ…е®…д»Ӣиӯ·гҖҚгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж–ҪиЁӯгҒёгҒ®гҖҢйҖҡгҒ„гҖҚгҒЁзҹӯжңҹй–“гҒ®гҖҢе®ҝжіҠгҖҚгҖҒиҮӘе®…гҒёгҒ®гҖҢиЁӘе•ҸгҖҚгҒ®3гҒӨгҒ®д»Ӣиӯ·ж–№жі•гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰд»Ӣиӯ·гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮұгӮўгғ—гғ©гғідҪңжҲҗжҷӮгҒ«гҖҢд»Ӣиӯ·гҖҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹж–№гҒ®гҒҝеҲ©з”ЁеҸҜиғҪгҒ§гҖҒд»Ӣиӯ·гӮҲгӮҠгӮӮи»ҪгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢж”ҜжҸҙгҖҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢж–№гҒ®еҲ©з”ЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
зҹӯжңҹй–“гҒ®е®ҝжіҠ
зҹӯжңҹе…ҘжүҖз”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјҲгӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғҶгӮӨпјү
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢзү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒӘгҒ©гҒ®д»Ӣиӯ·иҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯгҒ«жңҖеӨ§гҒ§30ж—Ҙй–“ж»һеңЁгҒ—гҖҒд»Ӣиӯ·гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зҹӯжңҹе…ҘжүҖзҷӮйӨҠд»Ӣиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгӮ„д»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯгҖҒд»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўгҒ«жңҖеӨ§гҒ§30ж—Ҙй–“ж»һеңЁгҒ—гҖҒд»Ӣиӯ·гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–ҪиЁӯзӯүгҒ§з”ҹжҙ»
д»Ӣиӯ·иҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯпјҲзү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјү
еёёгҒ«д»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгҖҒеңЁе®…еҫ©её°гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒд»Ӣиӯ·иҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯгҒ§з”ҹжҙ»гҒ—гҒӘгҒҢгӮүд»Ӣиӯ·гӮ„з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯпјҲиҖҒеҒҘпјү
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒд»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯгҒ§з”ҹжҙ»гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ„еҝ…иҰҒгҒӘеҢ»зҷӮгҖҒд»Ӣиӯ·гҒӘгҒ©гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·зҷӮйӨҠеһӢеҢ»зҷӮж–ҪиЁӯ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢй•·жңҹгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰзҷӮйӨҠгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒд»Ӣиӯ·зҷӮйӨҠеһӢеҢ»зҷӮж–ҪиЁӯгҒ§з”ҹжҙ»гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгӮ„еҝ…иҰҒгҒӘеҢ»зҷӮгҖҒд»Ӣиӯ·гҒӘгҒ©гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјҲжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҒи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ зӯүпјү
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гӮ„и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒӘгҒ©гҒ§з”ҹжҙ»гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒйЈҹдәӢгӮ„е…ҘжөҙгҒӘгҒ©гҒ®ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёҠгҒ®ж”ҜжҸҙгӮ„гҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷў
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢй•·жңҹгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰзҷӮйӨҠгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒд»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўгҒ§з”ҹжҙ»гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒзҷӮйӨҠдёҠгҒ®з®ЎзҗҶгӮ„зңӢиӯ·гҖҒд»Ӣиӯ·гӮ„гҒқгҒ®д»–еҝ…иҰҒгҒӘеҢ»зҷӮгҒӘгҒ©гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҖҒиҮӘз«ӢгӮ’ж”ҜжҸҙгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢгӮөгғјгғ“гӮ№
иӘҚзҹҘз—ҮеҜҫеҝңеһӢе…ұеҗҢз”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјҲгӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ пјү
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгҖҒд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«е…ұеҗҢз”ҹжҙ»гӮ’иЎҢгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒиҮӘз«ӢгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰйЈҹдәӢгӮ„е…ҘжөҙгҒӘгҒ©гҒ®з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгҖҒз”ҹжҙ»ж©ҹиғҪеҗ‘дёҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҒӘгҒ©гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢд»Ӣиӯ·иҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯе…ҘжүҖиҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢд»Ӣиӯ·иҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯгҒ«е…ҘжүҖгҒ—гҖҒз”ҹжҙ»гҒ®ж”ҜжҸҙгӮ„ж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҖҒзҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҮӘз«ӢгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гӮ„и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«е…ҘжүҖгҒ—гҖҒз”ҹжҙ»гҒ®ж”ҜжҸҙгӮ„ж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҖҒзҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зҰҸзҘүз”Ёе…·гӮ’дҪҝгҒҶ
зҰҸзҘүз”Ёе…·иІёдёҺ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®е®¶ж—Ҹд»Ӣиӯ·гҒ®иІ жӢ…и»ҪжёӣгҒӘгҒ©гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹдәӢжҘӯиҖ…гҒҢзҰҸзҘүз”Ёе…·гӮ’йҒёгҒ¶гҒҹгӮҒгҒ®жҸҙеҠ©гғ»еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гғ»иӘҝж•ҙгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒзҰҸзҘүз”Ёе…·гӮ’иІёдёҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№е®ҡзҰҸзҘүз”Ёе…·иІ©еЈІ
гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒ®е®¶ж—Ҹд»Ӣиӯ·гҒ®иІ жӢ…и»ҪжёӣгҒӘгҒ©гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҰҸзҘүз”Ёе…·иІ©еЈІгҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹдәӢжҘӯиҖ…гҒҢе…ҘжөҙгӮ„жҺ’жі„гҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖҒиІёдёҺдёҚеҸҜгҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзҰҸзҘүз”Ёе…·гӮ’иІ©еЈІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢж–ҷйҮ‘

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢж–ҷйҮ‘гҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»з”ЁгҒ®1еүІгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒдёҖе®ҡд»ҘдёҠгҒ®жүҖеҫ—гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜ2еүІгҖң3еүІгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиҮӘе®…гҒ§з”ҹжҙ»гҒҷгӮӢдәәгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҒ«гҒҜгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰеҲҘгҒ«д»ҘдёӢгҒ®йҷҗеәҰйЎҚгҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
|
д»Ӣиӯ·еәҰ |
1гғ¶жңҲгҒ®йҷҗеәҰйЎҚ |
|
иҰҒж”ҜжҸҙпј‘ |
50,320еҶҶ |
|
иҰҒж”ҜжҸҙпј’ |
105,310еҶҶ |
|
иҰҒд»Ӣиӯ·пј‘ |
167,650еҶҶ |
|
иҰҒд»Ӣиӯ·пј’ |
197,050еҶҶ |
|
иҰҒд»Ӣиӯ·пј“ |
270,480еҶҶ |
|
иҰҒд»Ӣиӯ·пј” |
309,380еҶҶ |
|
иҰҒд»Ӣиӯ·пј• |
362,170еҶҶ |
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№ж–ҷйҮ‘гҒҢйҷҗеәҰйЎҚгҒ®зҜ„еӣІеҶ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°1еүІпјҲдёҖе®ҡд»ҘдёҠгҒ®жүҖеҫ—гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜ2еүІгҖң3еүІпјүиІ жӢ…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҜ„еӣІеӨ–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜе…ЁйЎҚиҮӘе·ұиІ жӢ…гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҹгӮҒгҖҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜгҒ„гҒӨгҒӢгӮүгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§жү•гҒҶпјҹж”Ҝжү•гҒ„ж–№жі•гғ»е…ҚйҷӨжқЎд»¶гӮ’еҫ№еә•и§ЈиӘ¬
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁиІ жӢ…гӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰ

еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ1еүІиІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮӢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№ж–ҷйҮ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒй•·жңҹзҡ„гҒӘд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒӘгҒ©гҒҜеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иІ жӢ…гҒҢйҒҺйҮҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁиІ жӢ…гӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢжҺӘзҪ®гӮ„еҲ¶еәҰгӮ’3гҒӨгҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- зү№е®ҡе…ҘжүҖиҖ…д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»ж”ҜзөҰжҺӘзҪ®
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒ«е…ҘжүҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒжүҖеҫ—гӮ„иіҮз”ЈгҒ«еҝңгҒҳгҒҰеұ…дҪҸиІ»гҒЁйЈҹиІ»гҒҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒӢгӮүж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№е®ҡе…ҘжүҖиҖ…д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»ж”ҜзөҰгҒ«гҒҜгҖҒгҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ§иІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠж°—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
- й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»ж”ҜзөҰжҺӘзҪ®
1гғ¶жңҲгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ жӢ…йЎҚгҒҢй«ҳйЎҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒжүҖеҫ—гҒ«еҝңгҒҳгҒҰиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹдёҠйҷҗйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹеҲҶгҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҠйҷҗйЎҚгҒҜ15,000еҶҶгҖң140,100еҶҶгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®иіҮж–ҷгҒЁз…§гӮүгҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒҢгҒ©гҒ®еҢәеҲҶгҒ«еұһгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮ’дәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҸӮз…§пјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒпјҡгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢеҲ©з”Ёж–ҷ
- й«ҳйЎҚеҢ»зҷӮгғ»й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·еҗҲз®—еҲ¶еәҰ
еҢ»зҷӮиІ»гҒЁд»Ӣиӯ·иІ»гҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…йЎҚгҒ®еҗҲиЁҲгҒҢгҖҒжүҖеҫ—гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹдёҠйҷҗйЎҚгӮ’и¶…йҒҺгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒи¶…йҒҺгҒ—гҒҹеҲҶгҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁгҒ®жөҒгӮҢ

е®ҹйҡӣгҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒ6гӮ№гғҶгғғгғ—гҒ®жүӢй ҶгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҘдёӢгҒ§гҖҒй ҶгҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
1. иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгҒ®з”іи«Ӣ
гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®зӘ“еҸЈгҒ§иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгҒ®з”іи«ӢгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з”іи«ӢгҒ«гҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиў«дҝқйҷәиҖ…иЁјгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжә–еӮҷгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮ’з”іи«ӢгҒ§гҒҚгӮӢе№ҙйҪўгӮ„з”іи«Ӣе ҙжүҖгҒҜпјҹиҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгҒ®жөҒгӮҢгӮӮи§ЈиӘ¬
2. иӘҚе®ҡиӘҝжҹ»гғ»дё»жІ»еҢ»ж„ҸиҰӢжӣё
иӘҝжҹ»е“ЎгҒҢз”іи«ӢиҖ…гҒ®еҝғиә«гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’иӘҝжҹ»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
3. еҜ©жҹ»еҲӨе®ҡ
гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒЁд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡеҜ©жҹ»дјҡгҒ«гӮҲгӮӢиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒ®еҲӨе®ҡгҒҢиЎҢгҒӘгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
4. иӘҚе®ҡ
еҜ©жҹ»еҲӨе®ҡгҒ«гӮӮгҒЁгҒҘгҒҚгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’иЎҢгҒӘгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡзөҗжһңпјҲиҰҒж”ҜжҸҙ1пҪҘ2гҒӢгӮүиҰҒд»Ӣиӯ·1гҖң5гҒҫгҒ§гҒ®пј—ж®өйҡҺгҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜйқһи©ІеҪ“пјүгҒҜз”іи«ӢиҖ…гҒ«йҖҡзҹҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
5. д»Ӣиӯ·пјҲд»Ӣиӯ·дәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иЁҲз”»жӣёгҒ®дҪңжҲҗ
д»Ӣиӯ·пјҲд»Ӣиӯ·дәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иЁҲз”»жӣёгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢгӮұгӮўгғ—гғ©гғігҖҚгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ«жңҖйҒ©гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гӮ’жұәе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
6. д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁгҒ®й–Ӣе§Ӣ
гҖҢгӮұгӮўгғ—гғ©гғігҖҚгҒ«гӮӮгҒЁгҒҘгҒ„гҒҹгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҲ©з”ЁеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҘдёҠгҒҢе®ҹйҡӣгҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жүӢй ҶгҒ§гҒҷгҖӮ
з…©йӣ‘гҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒз°ЎеҚҳгҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҒҜгҒҠдҪҸгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®зӘ“еҸЈгҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гғ»д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгӮ’гҒҠжҺўгҒ—гҒӘгӮүгҖҢ笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒё

жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҰӮиҰҒгӮ„зЁ®йЎһгҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гӮ„иҮӘе·ұиІ жӢ…и»ҪжёӣеҲ¶еәҰгҖҒеҲ©з”ЁжүӢй ҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢеүҚгҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ”дёЎиҰӘгҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҒ”иҮӘиә«гҒҢе®үеҝғгҒ—гҒҰиҖҒеҫҢгҒ®з”ҹжҙ»гӮ’иҝҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢ笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒ§гҒҜе°ӮеұһгҒ®зӣёи«Үе“ЎгҒҢгҒ”еёҢжңӣгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ гӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”еёҢжңӣгҒ®ж–ҪиЁӯгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒз„Ўж–ҷгҒ§дҪ•еәҰгҒ§гӮӮзҡҶж§ҳгҒ®гҒҠжӮ©гҒҝгҒ«еҜ„гӮҠж·»гҒ„гҖҒгҒҠжүӢдјқгҒ„гӮ’гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒңгҒІгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж©ҹгҒ«гҖҢ笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒ§зҙҚеҫ—гҒ®гҒ„гҒҸж–ҪиЁӯгӮ’гҒҠжҺўгҒ—гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№



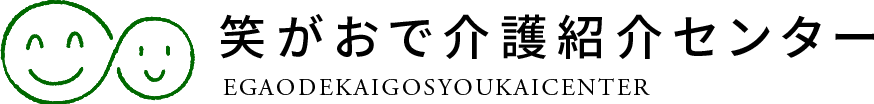




 0120-177-250
0120-177-250