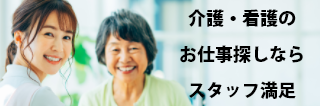д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒЁгҒҜпјҹдәӨд»ҳиҰҒ件гӮ„з”іи«Ӣж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮи§ЈиӘ¬
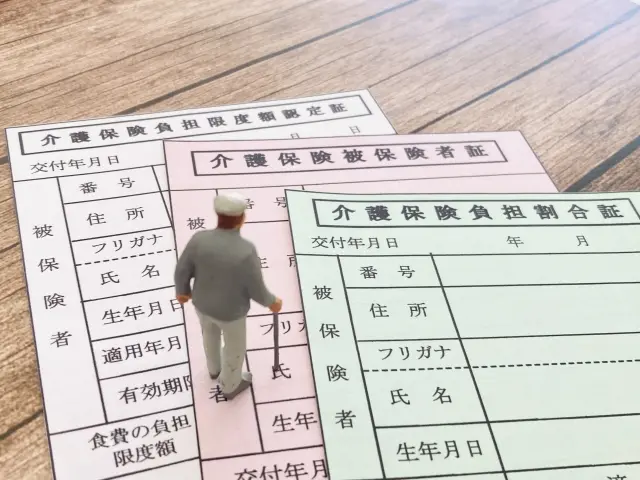
д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒ家иЁҲгӮ’ең§иҝ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒеұ…дҪҸиІ»гҒЁйЈҹиІ»гҒ®и»ҪжёӣгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢеҲ¶еәҰгҒҢгҖҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒёз”іи«ӢгҒҷгӮҢгҒ°гҖҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҖҚгҒҢдәӨд»ҳгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҢдәӨд»ҳиҰҒ件гҒҢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҖҢиҮӘеҲҶгҒ®е®¶ж—ҸгҒ«гҒҜйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®пјҹгҖҚгҒЁз–‘е•ҸгӮ’жҠұгҒҸж–№гӮӮеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§д»ҠеӣһгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®дәӨд»ҳиҰҒ件гӮ„еҲ©з”ЁиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҖҒеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„з”іи«Ӣж–№жі•гҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”家ж—ҸгҒҢд»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгҒ«е…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҖҒе°‘гҒ—гҒ§гӮӮиІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҹгҒ„гҒЁгҒҠиҖғгҒҲгҒ®ж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІжң¬иЁҳдәӢгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒЁгҒҜ

пјҲз”»еғҸеҮәе…ёпјҡзҫӨйҰ¬зңҢжҳӯе’Ңжқ‘гҖҢдҪҺжүҖеҫ—иҖ…гҒ®еұ…дҪҸиІ»гҒЁйЈҹиІ»гҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҖҚпјү
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒЁгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ®иҰҒ件гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢдәәгҒёзҷәиЎҢгҒ•гӮҢгӮӢиЁјжҳҺжӣёгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®дәӨд»ҳиҰҒ件гӮ’зҹҘгӮӢеүҚгҒ«гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҗҶи§ЈгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒЁгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®еұ…дҪҸиІ»гғ»йЈҹиІ»гӮ’и»ҪгҒҸгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
еҹәжң¬зҡ„гҒ«гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒёе…Ҙеұ…гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒеұ…дҪҸиІ»гҒЁйЈҹиІ»гҒҜе…ЁйЎҚиҮӘе·ұиІ жӢ…гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҪҸеұ…гӮ„йЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҒҜд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиҰҒж”ҜжҸҙгӮ„иҰҒд»Ӣиӯ·гҒ§иӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒеұ…дҪҸиІ»гӮ„йЈҹиІ»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒҜеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгӮ’дәӨд»ҳгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒёз”іи«ӢгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢи»ҪжёӣйЎҚгӮ„з”іи«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒҜиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡд»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгғ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«е…ҘгӮӢгҒ«гҒҜпјҹе…Ҙеұ…жқЎд»¶гӮ„е…Ҙеұ…гҒ®жөҒгӮҢгӮ’и§ЈиӘ¬
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®дәӨд»ҳиҰҒ件гҒЁгҒҜ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®дәӨд»ҳгҒ«гҒҜгҖҒеҗ„ж®өйҡҺгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжүҖеҫ—иҰҒ件гҒЁй җиІҜйҮ‘иҰҒ件гҒ®2зЁ®йЎһгӮ’жәҖгҒҹгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢи©ігҒ—гҒҸиҰӢгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жүҖеҫ—иҰҒ件
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®дәӨд»ҳгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жүҖеҫ—иҰҒ件гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
- жң¬дәәгӮ’еҗ«гӮҖдё–еёҜе…Ёе“ЎгҒҢдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁ
- еҲҘдё–еёҜгҒ®й…ҚеҒ¶иҖ…гӮӮдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁ
иІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҒҜеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ®4ж®өйҡҺгҒ®иҰҒ件гҒ«еҪ“гҒҰгҒҜгҒҫгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
|
еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺ |
жүҖеҫ—иҰҒ件пјҲе№ҙйҮ‘еҸҺе…ҘпјӢгҒқгҒ®д»–жүҖеҫ—йҮ‘йЎҚгҒ®еҗҲиЁҲпјү |
|
第1ж®өйҡҺ |
иҖҒйҪўзҰҸзҘүе№ҙйҮ‘гҖҒз”ҹжҙ»дҝқиӯ·еҸ—зөҰгҒ®дәә |
|
第2ж®өйҡҺ |
80дёҮеҶҶд»ҘдёӢ |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ1пјү |
80дёҮеҶҶи¶…120дёҮеҶҶд»ҘдёӢ |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ2пјү |
120дёҮеҶҶи¶… |
гҒӘгҒҠеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺгҒ«гҒҜ第4ж®өйҡҺгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҪҸж°‘зЁҺгҒ®иӘІзЁҺеҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®дәӨд»ҳеҜҫиұЎгҒ«гҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҹгҒ гҒ—зү№дҫӢжёӣйЎҚжҺӘзҪ®гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й җиІҜйҮ‘иҰҒ件
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ®й җиІҜйҮ‘иҰҒ件гҒҜд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
|
еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺ |
й җиІҜйҮ‘иҰҒ件 |
|
第1ж®өйҡҺ |
еҚҳиә«пјҡ1,000дёҮеҶҶд»ҘдёӢ |
|
第2ж®өйҡҺ |
еҚҳиә«пјҡ650дёҮеҶҶд»ҘдёӢ |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ1пјү |
еҚҳиә«пјҡ550дёҮеҶҶд»ҘдёӢ |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ2пјү |
еҚҳиә«пјҡ500дёҮеҶҶд»ҘдёӢ |
й җиІҜйҮ‘гҒ«гҒҜд»ҘдёӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- й җиІҜйҮ‘пјҲжҷ®йҖҡгғ»е®ҡжңҹпјү
- жңүдҫЎиЁјеҲё
- йҮ‘гғ»йҠҖгҒӘгҒ©пјҲз©ҚгҒҝз«ӢгҒҰиіје…ҘгӮ’еҗ«гӮҖпјү
- жҠ•иіҮдҝЎиЁ—
- зҸҫйҮ‘
гҒӘгҒҠиІ еӮөпјҲеҖҹе…ҘйҮ‘гӮ„дҪҸе®…гғӯгғјгғігҒӘгҒ©пјүгҒҜй җиІҜйҮ‘гҒ®йЎҚгҒӢгӮүе·®гҒ—еј•гҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҒ®еҲ©з”ЁиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚ

еҲ©з”ЁиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҒҜгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺгӮ„еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–ҪиЁӯгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒж®өйҡҺгҒ”гҒЁгҒ®иІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
вҖ»пјҲ пјүеҶ…гҒҜзү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҫгҒҹгҒҜзү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®гӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғҶгӮӨгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®йҮ‘йЎҚ
гҖҗеұ…дҪҸиІ»гҒ®иІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚпјҲеҶҶпјҸ1ж—ҘпјүгҖ‘
|
В |
гғҰгғӢгғғгғҲеһӢеҖӢе®Ө |
гғҰгғӢгғғгғҲеһӢеҖӢе®Өзҡ„еӨҡеәҠе®Ө |
еҫ“жқҘеһӢеҖӢе®Ө |
еӨҡеәҠе®Ө |
|
第1ж®өйҡҺ |
820 |
490 |
490пјҲ320пјү |
0 |
|
第2ж®өйҡҺ |
820 |
490 |
490пјҲ420пјү |
370 |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ1пјү |
1,310 |
1,310 |
1,310пјҲ820пјү |
370 |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ2пјү |
1,310 |
1,310 |
1,310пјҲ820пјү |
370 |
гҖҗйЈҹиІ»гҒ®иІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚпјҲеҶҶпјҸ1ж—ҘпјүгҖ‘
|
В |
гӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғҶгӮӨд»ҘеӨ–гҒ®зү№е®ҡд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№ |
гӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғҶгӮӨ |
|
第1ж®өйҡҺ |
300 |
300 |
|
第2ж®өйҡҺ |
390 |
600 |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ1пјү |
650 |
1,000 |
|
第3ж®өйҡҺпјҲ2пјү |
1,360 |
1,300 |
пјҲеҮәе…ёпјҡеӨ§йҳӘеёӮгҖҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡз”іи«ӢжӣёгҖҚпјү
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢж–ҪиЁӯгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢж–ҪиЁӯгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®7зЁ®йЎһгҒ§гҒҷгҖӮж–ҪиЁӯгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҰӮиҰҒгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠд»Ӣиӯ·зҷӮйӨҠеһӢеҢ»зҷӮж–ҪиЁӯгҒҜ2024е№ҙ3жңҲгҒ§гҒ®е»ғжӯўгҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж–°гҒҹгҒ«еүөиЁӯгҒ•гӮҢгӮӢд»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўгҒЁгҒ—гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
|
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢж–ҪиЁӯгғ»гӮөгғјгғ“гӮ№ |
е…Ҙеұ…гғ»еҲ©з”ЁжқЎд»¶ |
жҰӮиҰҒ |
|
зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ |
|
|
|
д»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯ |
|
|
|
д»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷў |
|
|
|
ең°еҹҹеҜҶзқҖеһӢд»Ӣиӯ·иҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯ |
|
|
|
гӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғҶгӮӨпјҲзҹӯжңҹе…ҘжүҖз”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјү |
|
|
|
гӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғҶгӮӨпјҲзҹӯжңҹе…ҘжүҖзҷӮйӨҠд»Ӣиӯ·пјү |
|
|
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®з”іи«Ӣгғ»жӣҙж–°ж–№жі•

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®з”іи«ӢгӮ„жӣҙж–°ж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
з”іи«ӢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжӣёйЎһ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®з”іи«ӢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжӣёйЎһгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡз”іи«Ӣжӣё
- еҗҢж„Ҹжӣё
- й җиІҜйҮ‘гӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢж·»д»ҳжӣёйЎһ
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиў«дҝқйҷәиҖ…иЁјгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгҒ®еҶҷгҒ—
з”іи«ӢжӣёгҒҜиҮӘжІ»дҪ“гҒ®зӘ“еҸЈгҒ§еҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢгҒ»гҒӢгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒӢгӮүгӮӮгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
йҖҡеёігҒ®еҶҷгҒ—гӮ’ж·»д»ҳгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиў«дҝқйҷәиҖ…жң¬дәәгҒЁй…ҚеҒ¶иҖ…гҒ®дҝқжңүгҒҷгӮӢгҖҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®йҖҡеёігҖҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰз”іи«Ӣж—ҘгҒ®зӣҙиҝ‘2гғ¶жңҲд»ҘеҶ…гҒ®иЁҳеёігҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠзҸҫйҮ‘гҒҜиҮӘе·ұз”іе‘ҠгҒ§ж§ӢгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
иҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜеҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёзӯүгҒ§зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
з”іи«ӢгҖңдәӨд»ҳгҒҫгҒ§гҒ®жүӢй Ҷ
з”іи«ӢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжӣёйЎһгӮ’гҒқгӮҚгҒҲгҒҹгӮүгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәжӢ…еҪ“зӘ“еҸЈгҒ«зӣҙжҺҘжҢҒеҸӮгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒйғөйҖҒгҒ§з”іи«ӢгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зӘ“еҸЈгҒ«жҢҒеҸӮгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒи©ІеҪ“иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®е ҙгҒ§д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒҢдәӨд»ҳгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—ж·»д»ҳжӣёйЎһгҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒӘгҒ©гҖҒдёҚеӮҷгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҒҷгҒҗгҒ«зҷәиЎҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§жіЁж„ҸгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
йғөйҖҒгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒ1йҖұй–“зЁӢеәҰгҒ§зөҗжһңгҒҢйҖҡзҹҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жӣҙж–°гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚж–№жі•
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®жңүеҠ№жңҹй–“гҒҜгҖҒз”іи«ӢгҒ—гҒҹжңҲгҒ®еҲқж—ҘгҒӢгӮүзӣҙиҝ‘гҒ®7жңҲ31ж—ҘгҒҫгҒ§гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°3жңҲ21ж—ҘгҒ«з”іи«ӢгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜ3жңҲ1ж—ҘгҖң7жңҲ31ж—ҘгҒ®й–“гҒ§еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
жіЁж„ҸгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒиҮӘеӢ•жӣҙж–°гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒжҜҺе№ҙз”іи«ӢгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҖӮжӣҙж–°ж—ҘгҒҢиҝ‘гҒҘгҒҸгҒЁиҮӘжІ»дҪ“гҒӢгӮүгҒҠзҹҘгӮүгҒӣгҒҢеұҠгҒҸгҒ®гҒ§гҖҒжӣҙж–°гӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜжңҹж—ҘгҒҫгҒ§гҒ«еҲқеӣһз”іи«ӢжҷӮгҒЁеҗҢгҒҳжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§з”ігҒ—иҫјгӮ“гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҒӘгҒҠеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺгҒҢеӨүжӣҙгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгӮӮеӨүгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰҡгҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзү№дҫӢжёӣйЎҚжҺӘзҪ®гҒЁгҒҜ

еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺгҒҢ第4ж®өйҡҺпјҲ第1ж®өйҡҺгҖң第3ж®өйҡҺпјҲ2пјүгҒ«и©ІеҪ“гҒ—гҒӘгҒ„дәәпјүгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—й«ҳйҪўгҒ®еӨ«е©Ұдё–еёҜгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒҢд»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгҒёе…Ҙеұ…гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеңЁе®…гҒ§з”ҹжҙ»гҒҷгӮӢдәәгҒҢз”ҹиЁҲеӣ°йӣЈгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҢзү№дҫӢжёӣйЎҚжҺӘзҪ®гҖҚгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®е ҙеҗҲгҖҒйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢдҪҸеұ…иІ»гҒЁйЈҹиІ»гҒ®иІ жӢ…дёҠйҷҗйЎҚгҒҜгҖҒ第3ж®өйҡҺпјҲ2пјүгҒЁеҗҢгҒҳйҮ‘йЎҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠзү№дҫӢжёӣйЎҚжҺӘзҪ®гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ«гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®иҰҒ件гӮ’гҒҷгҒ№гҒҰжәҖгҒҹгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- дё–еёҜдәәж•°гҒҢ2дәәд»ҘдёҠпјҲеҲҘеұ…гҒ®й…ҚеҒ¶иҖ…гҒ®дәәж•°гӮӮеҗ«гӮҖпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁ
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒ«е…Ҙеұ…гғ»е…ҘйҷўгҒ—гҖҒзҸҫеңЁиЈңи¶ізөҰд»ҳгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁ
- пјҲдё–еёҜгҒ®е№ҙй–“еҸҺе…ҘпјүвҲ’пјҲж–ҪиЁӯгҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒ®иҰӢиҫјйЎҚпјүгҒҢ80дёҮеҶҶд»ҘдёӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁ
- й җиІҜйҮ‘зӯүгҒ®йҮ‘йЎҚгҒ®еҗҲиЁҲгҒҢ450дёҮеҶҶд»ҘдёӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁ
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮ’ж»һзҙҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁ
- и»ҠгӮ„дёҚеӢ•з”ЈгҒӘгҒ©гҒ®ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиіҮз”Јд»ҘеӨ–гҒ«гҖҒиіҮз”ЈгӮ’дҝқжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁ
зү№дҫӢжёӣйЎҚжҺӘзҪ®гӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜд»ҘдёӢгҒ®еҝ…иҰҒжӣёйЎһгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢзӘ“еҸЈгҒёз”ігҒ—иҫјгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡз”іи«Ӣжӣё
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиў«дҝқйҷәиҖ…иЁјпјҲеҶҷгҒ—гҒ§гӮӮеҸҜпјү
- дё–еёҜе…Ёе“ЎгҒ®й җиІҜйҮ‘йҖҡеёіпјҲеҶҷгҒ—гҒ§гӮӮеҸҜпјү
- дё–еёҜе…Ёе“ЎгҒ®еҸҺе…ҘгӮ’иЁјгҒҷгӮӢжӣёйЎһпјҲжүҖеҫ—иЁјжҳҺжӣёгӮ„е№ҙйҮ‘ж”Ҝжү•йҖҡзҹҘжӣёгҒӘгҒ©пјү
- иІ жӢ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢеұ…дҪҸиІ»гҖҚгҖҢйЈҹиІ»гҖҚгҒ®йЎҚгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгӮӮгҒ®пјҲж–ҪиЁӯгҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„жӣёйЎһгӮ„йҮҚиҰҒдәӢй …иӘ¬жҳҺжӣёгҒӘгҒ©пјү
еҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒҜиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёзӯүгҒ§дәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®з”іи«ӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢQ&A

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®з”іи«ӢгҒ§ж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒQ&AгҒ§гҒҫгҒЁгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡгҒ®й җиІҜйҮ‘йЎҚгҒҜиӘҝжҹ»гҒ•гӮҢгӮӢпјҹ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡгҒ®й җиІҜйҮ‘йЎҚгҒҜгҖҒиӘҝжҹ»гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ§гҒҜгҖҒй җиІҜйҮ‘гҒ®иӘҝжҹ»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з”іи«ӢжӣёгҒ«й җиІҜйҮ‘гӮ„иІ еӮөйЎҚгӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒд»ҘдёӢгҒ®иЎЁгҒ®гҖҢзўәиӘҚж–№жі•гҖҚгҒ«иЁҳијүгҒ®ж·»д»ҳжӣёйЎһзӯүгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёҠгҒ§гҖҒдҝқйҷәиҖ…гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒйҮ‘иһҚж©ҹй–ўзӯүгҒ«з…§дјҡгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲеҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҒҢеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖҚпјү
гҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒдҝқйҷәиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢеёӮз”әжқ‘гӮ„еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ®йҒӢе–¶дё»дҪ“гҒҢгҖҒйҮ‘иһҚжңҹй–“гҒ«иӘҝжҹ»гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠдёҚжӯЈгҒ«з”іи«ӢгҒ—гҒҰеҸ—зөҰгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҹзөҰд»ҳйЎҚгҒ«еҠ гҒҲгҒҰжңҖеӨ§2еҖҚпјҲзөҰд»ҳйЎҚгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰ3еҖҚпјүгҒ®еҠ з®—йҮ‘гӮ’зҙҚд»ҳгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҷҡеҒҪгҒ®з”іи«ӢгҒҜгӮ„гӮҒгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еӨ«е©ҰгҒ§дё–еёҜеҲҶйӣўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ®жүҖеҫ—иҰҒ件гҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢпјҹ
еӨ«е©ҰгҒҢдҪҸж°‘зҘЁгӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰеҲҘдё–еёҜгҒ«гҒӘгӮӢгҖҢдё–еёҜеҲҶйӣўгҖҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒй…ҚеҒ¶иҖ…гҒ®жүҖеҫ—гҒҜеҗҲз®—гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲе©ҡ姻еұҠгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҢдәӢе®ҹе©ҡгҖҚгҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҖҒеҗҢгҒҳгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—й…ҚеҒ¶иҖ…гҒҢиЎҢж–№дёҚжҳҺгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгӮ„гҖҒй…ҚеҒ¶иҖ…гҒӢгӮүDVгӮ„жҡҙеҠӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜдҫӢеӨ–гҒ§гҖҒеҜҫиұЎеӨ–гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дё–еёҜеҲҶйӣўгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒжүҖеҫ—иҰҒ件гҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
иҰҒ件гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгӮ’з”іи«ӢгҒ—гӮҲгҒҶ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгҒ®е…Ҙеұ…гӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеұ…дҪҸиІ»гҒЁйЈҹиІ»гҒҜе…ЁйЎҚиІ жӢ…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҲ©з”ЁгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дё–еёҜе…Ёе“ЎгҒҢдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй җиІҜйҮ‘гҒҢиҰҒ件д»ҘдёӢгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚиӘҚе®ҡиЁјгҒ®з”іи«ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҜгҒ„гҒӢгҒҢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒӘгҒҠ笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҒ§гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯжҺўгҒ—гҒ®гӮөгғқгғјгғҲгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘд»Ӣиӯ·гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒ”зӣёи«ҮгӮӮжүҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҪ•гҒӢдёҚжҳҺгҒӘзӮ№гӮ„гҒҠеӣ°гӮҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№



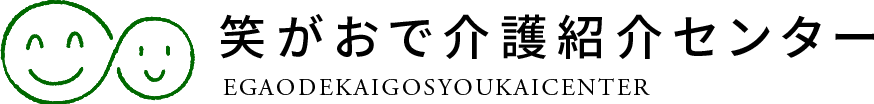




 0120-177-250
0120-177-250