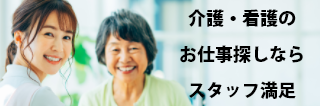гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒЁе…Ҙеұ…еүҚгҒ«гҒҠгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„еҜҫзӯ–

гҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢеүҚгҒ«е•ҸйЎҢзӮ№гӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гҖҚгҖҢе®үеҝғгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгҖӮз”ҹжҙ»гҒ®е ҙгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’еҝғй…ҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҗҢж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜеӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒӘгҒ©гҒ®е•ҸйЎҢгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ§иө·гҒ“гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„е•ҸйЎҢгҒЁгҒқгҒ®еҜҫзӯ–гҖҒеҲ©з”ЁеүҚгҒ«гҒҠгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒӘгҒ©гӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ®жғ…е ұгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӮ№гҒ«жіЁж„ҸгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒӢгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҙеұ…гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…дҪҸе®…гҒҜгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒ«зӣёеҝңгҒ—гҒ„з’°еўғгҒ®гӮӮгҒЁе°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢиҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®иіғиІёдҪҸе®…гҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒдёҖе®ҡгҒ®йқўз©ҚгҒЁдёҖе®ҡгҒ®иЁӯеӮҷгӮ’еӮҷгҒҲгҒҹгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ®дҪҸе®…гҒ§е°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгӮүгҒігҒ«з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еҜҫиұЎгҒҜгҖҒ60жӯід»ҘдёҠгҒ®ж–№гҒҫгҒҹгҒҜиҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹ40жӯід»ҘдёҠгҒ®ж–№гҒ§гҒҷпјҲе…·дҪ“зҡ„гҒӘе…Ҙеұ…еҹәжә–гҒҜж–ҪиЁӯгҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮеҗҢдҪҸе®…гҒҜгҖҒгҒқгҒ®зү№еҫҙгҒ«гӮҲгӮҠдёҖиҲ¬еһӢгҒЁд»Ӣиӯ·еһӢгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зү№еҫҙгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖиҲ¬еһӢ
иҮӘз«ӢеәҰгҒ®й«ҳгҒ„й«ҳйҪўиҖ…гӮ’дё»гҒӘеҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒ§гҒҷгҖӮиҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҸд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӨ–йғЁгҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒЁеҘ‘зҙ„гҒ—гҒҰгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮеҢ»зҷӮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮеҗҢж§ҳгҒ§гҒҷгҖӮжүӢеҺҡгҒ„д»Ӣиӯ·гӮ„еҢ»зҷӮгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дё»гҒӘеј·гҒҝгҒҜе°Ӯй–Җ家гҒ®иҰӢе®ҲгӮҠгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғ•гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒ“гҒЁгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеҘҪгҒҚгҒӘжҷӮй–“гҒ«йЈҹдәӢгӮ’йЈҹгҒ№гҒҹгӮҠгҖҒеҘҪгҒҚгҒӘжҷӮй–“гҒ«гҒҠйўЁе‘ӮгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒж°—еҲҶи»ўжҸӣгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒҚгҒ«еӨ–еҮәгҒ§гҒҚгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ家дәӢжҸҙеҠ©гҒ®гӮӘгғ—гӮ·гғ§гғігӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гӮӮиҰӢйҖғгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®иІ жӢ…гӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·еһӢ
иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„й«ҳйҪўиҖ…гҒ«гӮӮеҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒ§гҒҷгҖӮиҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ®зү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒҜгҖҒзү№е®ҡж–ҪиЁӯгҒ«е…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиҰҒд»Ӣиӯ·иҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢйЈҹдәӢгғ»жҺ’жі„гғ»е…ҘжөҙгҒӘгҒ©гҒ®дё–и©ұгҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҖҒзҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұгҒ§гҒҷпјҲд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№пјүгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶзү№е®ҡж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гғ»и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гғ»йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®иҰҒ件пјҲиҖҒдәәзҰҸзҘүжі•пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҖҚгҖҢд»Ӣиӯ·гҒ®жҸҗдҫӣгҖҚгҖҢ家дәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҖҚгҖҢеҒҘеә·з®ЎзҗҶгҖҚгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒзү№е®ҡж–ҪиЁӯгҒ«и©ІеҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒд»Ӣиӯ·еһӢгҒҜзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжүҖе®ҡгҒ®дәәе“Ўеҹәжә–гӮ„иЁӯеӮҷеҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„й«ҳйҪўиҖ…гҒ«гӮӮеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮӯгғғгғҒгғігӮ„жөҙе®ӨгҒӘгҒ©гӮ’е…ұз”ЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒдёҖиҲ¬еһӢгӮҲгӮҠгӮӮеұ…е®ӨгҒҢзӢӯгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒЁжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®зү№еҫҙгҒЁйҒ•гҒ„
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®еҲ©зӮ№
гғЎгғӘгғғгғҲгӮ’ж„ҹгҒҳгӮ„гҒҷгҒ„зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰд»ҘдёӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„
й«ҳйҪўиҖ…гҒҜиіғиІёзү©д»¶гӮ’еҖҹгӮҠгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиІёдё»гҒҢеҒҘеә·йқўгӮ„йҮ‘йҠӯйқўгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜгҖҢй«ҳйҪўиҖ…гҒ®еұ…дҪҸгҒ®е®үе®ҡзўәдҝқгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢгҖҚгҒ§гҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ’е…Ҙеұ…гҒ•гҒӣгҒҰзҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдәӢжҘӯгҒЁе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮе…Ҙеұ…гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮй•·жңҹе…ҘйҷўгҒӘгҒ©гӮ’зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдәӢжҘӯиҖ…еҒҙгҒ®йғҪеҗҲгҒ§дёҖж–№зҡ„гҒ«еҘ‘зҙ„гӮ’и§ЈйҷӨгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зӮ№гӮӮйӯ…еҠӣгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶпјҲйҖҖеҺ»жқЎд»¶гҒ®зўәиӘҚгҒҜеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷпјүгҖӮ
з”ҹжҙ»гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„з’°еўғгҒҢж•ҙгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ
й«ҳйҪўиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰз”ҹжҙ»гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„з’°еўғгҒҢж•ҙгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гӮӮйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮж®өе·®гӮ’и§Јж¶ҲгҒҷгӮӢгҖҒжүӢгҒҷгӮҠгӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒдҪҸе®…гҒҜгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиҰҸжЁЎгғ»иЁӯеӮҷгҒҜд»ҘдёӢгҒ®еҹәжә–гҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
| еәҠйқўз©Қ | еҺҹеүҮ25гҺЎд»ҘдёҠпјҲеұ…й–“гғ»йЈҹе Ӯгғ»еҸ°жүҖгҒӘгҒ©гҒҢе…ұеҗҢеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҚҒеҲҶгҒӘйқўз©ҚгӮ’жңүгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜ18гҺЎд»ҘдёҠпјү |
| е°Ӯз”ЁйғЁеҲҶгҒ®иЁӯеӮҷ | еҸ°жүҖгғ»жөҙе®Өгғ»жҙ—йқўиЁӯеӮҷгғ»ж°ҙжҙ—дҫҝжүҖгғ»еҸҺзҙҚиЁӯеӮҷпјҲе…ұз”ЁйғЁеҲҶгҒ«еҸ°жүҖгғ»жөҙе®Өгғ»еҸҺзҙҚиЁӯеӮҷгӮ’еӮҷгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҗ„е°ӮжңүйғЁеҲҶгҒ«гҒ“гӮҢгӮүгӮ’еӮҷгҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҒЁжҜ”гҒ№дҪҸз’°еўғгҒҢеҗҢзӯүд»ҘдёҠгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜеҗ„жҲёгҒ«еӮҷгҒҲгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮеҸҜпјү |
В д»ҘдёҠгҒ®з’°еўғдёӢгҒ§гҖҒгӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢиҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮй«ҳйҪўиҖ…гҒ®дёҚе®үгӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„дҪҸе®…гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№
е…Ҙеұ…гӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«зҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„е•ҸйЎҢзӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒҢй«ҳйЎҚ
еҗҢгҒҳз«Ӣең°жқЎд»¶гғ»йқўз©Қгғ»гӮ°гғ¬гғјгғүгҒ®иіғиІёдҪҸе®…гҒЁжҜ”гҒ№гӮӢгҒЁиІ»з”ЁгҒҜй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе»әзү©гҒҢгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҶгҒҲгҖҒиҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢдјҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜе•ҸйЎҢзӮ№гҒЁгҒ„гҒ„гҒ«гҒҸгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж–ҪиЁӯж•°гҒ®жҖҘеў—гҒ«дјҙгҒ„гҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№е“ҒиіӘгҒ«гҒ°гӮүгҒӨгҒҚгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒе…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒ®зӣёе ҙгҒҜгҖҒжҜ”ијғеҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гӮҲгӮҠе®үгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘе…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒҜгӮұгғјгӮ№гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ®дёӯгҒ§иІ»з”ЁгҒҢйҡӣз«ӢгҒЈгҒҰй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒҜпјҹзӣёе ҙгҒЁе®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢгғқгӮӨгғігғҲ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢдёҚеҚҒеҲҶ
еӣҪеңҹдәӨйҖҡзңҒгҒҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢжғ…е ұжҸҗдҫӣгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®зҸҫзҠ¶зӯүгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒд»Өе’Ң2е№ҙ8жңҲжҷӮзӮ№гҒ§д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ«еҹәгҒҘгҒҸзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·зӯүгҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯпјҲд»Ӣиӯ·еһӢпјүгҒҜе…ЁдҪ“гҒ®8.1пј…гҒ§гҒҷгҖӮ
еҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢжғ…е ұжҸҗдҫӣ гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®зҸҫзҠ¶зӯүгҖҚ
В
еӨҡгҒҸгҒ®ж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒеҚҒеҲҶгҒӘдҪ“еҲ¶гғ»иЁӯеӮҷгӮ’ж•ҙгҒҲгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгҒҫгҒҹеҚҒеҲҶгҒӘд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮӮжҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еӣҪеңҹдәӨйҖҡзңҒгҒҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢгӮөй«ҳдҪҸгҒ®дҫӣзөҰзҠ¶жіҒзӯүгҒ«дҝӮгӮӢгғҮгғјгӮҝгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®16.2пј…гҒҢгҖҢиҒ·е“ЎгҒ®ж•°гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҖҚгҖҒ9.3пј…гҒҢгҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢиҒ·е“ЎгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒҢдҪҺгҒ„гҖҚгҖҒ8.5пј…гҒҢгҖҢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№пјҲ家дәӢгҖҒе®үеҗҰзўәиӘҚгҖҒз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгҒӘгҒ©пјүгҒ®еҶ…е®№гҒҢдёҚжәҖгҖҚгҒЁеӣһзӯ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҮәе…ёпјҡеӣҪеңҹдәӨйҖҡзңҒгҖҢгӮөй«ҳдҪҸгҒ®дҫӣзөҰзҠ¶жіҒзӯүгҒ«дҝӮгӮӢгғҮгғјгӮҝгҖҚ
В
з©әе®ӨгӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гҒҹгҒ„дәӢжҘӯиҖ…гҒ®еёҢжңӣгҒ§гҖҒиҮӘж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜеҜҫеҝңгҒ—гҒҚгӮҢгҒӘгҒ„иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒ®й«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…еүҚгҒ«дҪ“еҲ¶гғ»иЁӯеӮҷгғ»еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гӮ’гӮҲгҒҸзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
еӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒ®жЁӘиЎҢ
зі»еҲ—гҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еј·еҲ¶зҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжң¬дәәгҒҢжңӣгӮ“гҒ§гҒ„гҒӘгҒ„д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮдёҖйғЁгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜеӣІгҒ„иҫјгҒҝгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёӯгҒ«гҒҜгҖҒ家иіғгҒӘгҒ©гӮ’дҪҺйЎҚгҒ«жҠ‘гҒҲгҒҰгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒҢиҮӘгӮүгҒ®еёҢжңӣгҒ§дәӢжҘӯиҖ…гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰгҖҒеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮеӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®зҗҶеҝөгӮ’иёҸгҒҝгҒ«гҒҳгӮӢиЎҢзӮәгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзҸҫеңЁгҒҜеҜҫзӯ–гҒҢи¬ӣгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒҜжёӣгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮжіЁж„ҸгҒҜеҝ…иҰҒгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸе•ҸйЎҢгҒёгҒ®жү“й–Ӣзӯ–
д»ҘдёҠгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒӘгҒ©гҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
зӣЈиҰ–гҒ®еј·еҢ–
еӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеӣҪгҒҜзӣЈиҰ–дҪ“еҲ¶гӮ’еј·еҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”Ёе®ҹзёҫгҒӢгӮүдёҚйҒ©еҲҮгҒӘиЎҢзӮәгӮ’жҠҪеҮәгҒ—гҒҰгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒ®з«ӢгҒЎе…ҘгӮҠиӘҝжҹ»гҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒӘгҒ’гӮӢд»•зө„гҒҝгӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒжҜҺжңҲгҒ®еҲ©з”ЁйҷҗеәҰйЎҚгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰдёҖе®ҡгҒ®еүІеҗҲд»ҘдёҠгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгҒ©гҒ®жқЎд»¶гҒ§д»Ӣиӯ·иЁҲз”»гӮ’жҠҪеҮәгҒ—гҒҰгҖҒеӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒёгҒ®й–ўгӮҸгӮҠгҒҢз–‘гӮҸгӮҢгӮӢд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгӮ’зү№е®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Өе’Ң3е№ҙеәҰгҒ®д»Ӣиӯ·е ұй…¬ж”№е®ҡгҒ§гҖҒдәӢжҘӯжүҖжҢҮе®ҡгҒ®йҡӣгҒ®жқЎд»¶д»ҳгҒ‘гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹзӮ№гӮӮиҰӢйҖғгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠжҢҮе®ҡжЁ©иҖ…гҒҢгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®дёҖе®ҡеүІеҗҲд»ҘдёҠгӮ’дҪөиЁӯж–ҪиЁӯд»ҘеӨ–гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…гҒ«гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®жқЎд»¶гӮ’иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжӮӘиіӘгҒӘеӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒҜиЎҢгҒ„гҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иЎҢеӢ•иҰҸзҜ„йҒөе®Ҳе®ЈиЁҖзўәиӘҚжӣёгҒ®зҷәиЎҢ
дёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәй«ҳйҪўиҖ…дҪҸе®…еҚ”дјҡгҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гҒ®е°ҠеҺігӮ„иҮӘе·ұжұәе®ҡжЁ©гӮ’е®ҲгӮҠгҖҒеӨ–йғЁгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’йҒ©еҲҮгҒ«жҙ»з”ЁгҒ—ж–ҪиЁӯгӮ’йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒҹгӮҒгҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒҢе®ҲгӮӢгҒ№гҒҚиЎҢеӢ•иҰҸзҜ„гӮ’зӯ–е®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒ2019е№ҙеәҰгҒӢгӮүиЎҢеӢ•иҰҸзҜ„йҒөе®Ҳе®ЈиЁҖгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹж–ҪиЁӯгӮ’гҖҢйҒ©еҲҮгҒ«йҒӢе–¶гӮ’иЎҢгҒҶгӮөй«ҳдҪҸйҒӢе–¶дәӢжҘӯиҖ…гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢеҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮӮиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиЎҢеӢ•иҰҸзҜ„гҒ®еҶ…е®№гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
пјҲпј‘пјү гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®е°ҠеҺігҒЁгҖҒгҖҢеӨ–д»ҳгҒ‘гӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгӮөгғјгғ“гӮ№зӯүгҒ®жҸҗдҫӣгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеҲ©з”ЁиҖ…гҒҢдәӢжҘӯиҖ…гҒ®йҒёжҠһгғ»еӨүжӣҙгҒ§гҒҚгӮӢжЁ©еҲ©гӮ’е®ҲгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲпј’пјү гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®еҝ…й ҲгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҖҢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгҒЁгҖҢеӨ–д»ҳгҒ‘гӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгҒҜеҢәеҲҘгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲпј“пјү гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«йҡӣгҒ—гҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…йҒӢе–¶дәӢжҘӯиҖ…гҒҢйҒӢе–¶гҒҷгӮӢд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯжүҖгҒҢдҪөиЁӯгғ»йҡЈжҺҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒҢе…Ҙеұ…еүҚгҒӢгӮүеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’з¶ҷз¶ҡеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢжЁ©еҲ©гӮ’е®ҲгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еј•з”ЁпјҡдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәй«ҳйҪўиҖ…дҪҸе®…еҚ”дјҡгҖҖиЎҢеӢ•иҰҸзҜ„йҒөе®Ҳе®ЈиЁҖжӣёВ
иЎҢеӢ•иҰҸзҜ„йҒөе®Ҳе®ЈиЁҖгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒйҒ©еҲҮйҒӢе–¶гҒ®иЁјгҒ«гҒӘгӮӢгғӯгӮҙгғһгғјгӮҜгӮ’гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ„гғ‘гғігғ•гғ¬гғғгғҲгҒ«дҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮжҘӯз•ҢеӣЈдҪ“гӮӮйҒӢе–¶йҒ©жӯЈеҢ–гҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹеҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…е…Ҙеұ…еүҚеҫҢгҒ«з•ҷж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲ
з¶ҡгҒ„гҒҰгҖҒе…Ҙеұ…еүҚгҒ«гҒҠгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гӮ’иЎҢгҒҶ
зҸҫеңЁгҒ®зҠ¶жіҒгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒж–ҪиЁӯгҒ®е…Ҙеұ…жқЎд»¶гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮеҹәжң¬зҡ„гҒӘе…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗе…Ҙеұ…жқЎд»¶пјҲжң¬дәәпјүгҖ‘
- иҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢ60жӯід»ҘдёҠпјҲгҒҫгҒҹгҒҜиҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢ40жӯід»ҘдёҠпјү
вҖ»иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„й«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҗҢеұ…дәәгҖ‘
- й…ҚеҒ¶иҖ…
- 60жӯід»ҘдёҠгҒ®иҰӘж—Ҹ
- иҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢиҰӘж—Ҹ
- зү№еҲҘгҒӘдәӢжғ…гҒ§еҗҢеұ…гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁзҹҘдәӢгҒҢиӘҚгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®
д»ҘдёҠгҒ®е…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гӮӮеҹәжң¬гҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘжқЎд»¶гҒҜж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒӘгҒ©гҒҜйҒ•гҒ„гҒҢзҸҫгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйҖҖеҺ»жқЎд»¶гҒ«гӮӮж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгӮӢйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзҸҫеңЁгҒ®зҠ¶жіҒгҖҒдәҲжғігҒ•гӮҢгӮӢзҠ¶жіҒгҒЁе…Ҙеұ…жқЎд»¶гғ»йҖҖеҺ»жқЎд»¶гӮ’з…§гӮүгҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
еҲҘгҒ®йҒёжҠһиӮўгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸ
е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢж–ҪиЁӯгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒе®Ңе…ЁгҒ«е®үеҝғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒдҪ“иӘҝгҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйҖҖеҺ»гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮеҲҘгҒ®йҒёжҠһиӮўгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮұгғјгӮ№гҒ«еӮҷгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дёҖиҲ¬еһӢгҒҜгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒ®дёҠжҳҮгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠйҖҖеҺ»гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢе…Ҙеұ…жҷӮгҒ«йҖҖеҺ»жқЎд»¶гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰеҲҘгҒ®йҒёжҠһиӮўгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒе®үеҝғгҒ—гҒҰз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«еӮҷгҒҲгҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ пјҲиӘҚзҹҘз—ҮеҜҫеҝңеһӢе…ұеҗҢз”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјүгӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгӮҲгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢ
еӨҡгҒҸгҒ®ж–ҪиЁӯгҒҜд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒдҪ“еҲ¶гӮ„иЁӯеӮҷгӮӮж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…еҫҢгҒ«д»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӨ–йғЁгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·гӮ„гғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮиә«дҪ“ж©ҹиғҪгҒӘгҒ©гҒҢиЎ°гҒҲгӮӢгҒЁгҖҒж–ҪиЁӯгҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜеҝ«йҒ©гҒ«йҒҺгҒ”гҒ—гҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮұгӮўгғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒӘгҒ©гҒЁзӣёи«ҮгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒжҹ”и»ҹгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
家ж—ҸгҒ§йҖЈжҗәгҒҷгӮӢ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁиҮӘе·ұиІ жӢ…гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®иІ»з”ЁгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒӘиІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢж–№гӮӮгҒ„гӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ家ж—ҸгҒ®еҚ”еҠӣгӮ’еҫ—гӮүгӮҢгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®иІ»з”ЁгӮ’и»ҪжёӣгҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒйҖұгҒ«1еӣһгҖҒзқҖжӣҝгҒҲгӮ„жҺ’гҒӣгҒӨгҒӘгҒ©гҖҒиә«гҒ®еӣһгӮҠгҒ®дё–и©ұгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҒеҸҢж–№гҒ®иІ жӢ…гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгӮұгӮўгғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒЁзӣёи«ҮгҒ—гҒӨгҒӨжӨңиЁҺгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒ無駄гҒ®гҒӘгҒ„гӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’зө„гӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®е…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒ®зӣ®е®ү
е…¬зӣҠзӨҫеӣЈжі•дәәе…ЁеӣҪжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ еҚ”дјҡгҒҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒдёҖиҲ¬еһӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе№іеқҮеҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҒҜжңҲйЎҚ142,215еҶҶгҒ§гҒҷгҖӮ
В
еҶ…иЁігҒҜд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
| й …зӣ® | йҮ‘йЎҚ |
| еұ…дҪҸиІ»з”ЁпјҲеүҚжү•гҒ„йҮ‘иҖғж…®еҫҢ家иіғпјү | 61,344еҶҶ |
| жңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘ | 86,403еҶҶ |
еүҚжү•гҒ„йҮ‘гӮ’иҖғж…®гҒ—гҒӘгҒ„家иіғгҒҜ58,901еҶҶгҒ§гҒҷгҖӮжңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҒҜд»ҘдёӢгҒ®й …зӣ®гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗжңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҖ‘
- е…ұзӣҠиІ»гғ»з®ЎзҗҶиІ»пјҡ19,023еҶҶ
- з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгғ»д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҖҒеҹәжң¬гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»пјҡ19,011еҶҶ
- йЈҹиІ»пјҡ45,877еҶҶ
- е…үзҶұж°ҙиІ»пјҡ1,566еҶҶ
вҖ»дёӯдҪҚ90пј…гӮ’еҜҫиұЎгҒ«з®—еҮәгҒ—гҒҹе№іеқҮеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒе°ҸиЁҲгҒЁеҗҲиЁҲгҒҜдёҖиҮҙгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е…Ҙеұ…жҷӮиІ»з”ЁпјҲеүҚжү•йҮ‘жңҲйЎҚжҸӣз®—пјүгҒҜ0еҶҶгҖҒж•·йҮ‘гғ»дҝқиЁјйҮ‘пјҲеҸӮиҖғпјүгҒҜ96,756еҶҶгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘе…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒҜж–ҪиЁӯгҒ§еӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңҲйЎҚжҸӣз®—гҒ—гҒҹз·ҸйЎҚиІ»з”ЁгҒҢ10дёҮеҶҶжңӘжәҖгҒ®ж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒ30дёҮеҶҶд»ҘдёҠгҒ®ж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңҖгӮӮеүІеҗҲгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒҜ14.3пј…гҒ®12пҪһ14дёҮеҶҶжңӘжәҖгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҖӢеҲҘгҒ®зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ§гҒӢгҒӢгӮӢеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒЁжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®еҶ…иЁі
гҖҗд»Ӣиӯ·еәҰеҲҘгҖ‘д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…йЎҚ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ«еҹәгҒҘгҒҸд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒжүҖеҫ—гҒ«еҝңгҒҳгҒҰ1пҪһ3еүІпјҲеҺҹеүҮ1еүІпјүгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰеҲҘгҒ®еҲ©з”ЁйҷҗеәҰйЎҚгҒЁиҮӘе·ұиІ жӢ…йЎҚпјҲеҲ©з”ЁйҷҗеәҰйЎҚгҒҫгҒ§еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲпјүгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ[4]
| иҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰ | еҲ©з”ЁйҷҗеәҰйЎҚ | 1еүІиІ жӢ… | 2еүІиІ жӢ… | 3еүІиІ жӢ… |
| иҰҒж”ҜжҸҙ1 | 50,320еҶҶ | 5,032еҶҶ | 10,064еҶҶ | 15,096еҶҶ |
| иҰҒж”ҜжҸҙ2 | 105,310еҶҶ | 10,531еҶҶ | 21,062еҶҶ | 31,593еҶҶ |
| иҰҒд»Ӣиӯ·1 | 167,650еҶҶ | 16,765еҶҶ | 33,530еҶҶ | 50,295еҶҶ |
| иҰҒд»Ӣиӯ·2 | 197,050еҶҶ | 19,705еҶҶ | 39,410еҶҶ | 59,115еҶҶ |
| иҰҒд»Ӣиӯ·3 | 270,480еҶҶ | 27,048еҶҶ | 54,096еҶҶ | 81,144еҶҶ |
| иҰҒд»Ӣиӯ·4 | 309,380еҶҶ | 30,938еҶҶ | 61,876еҶҶ | 92,814еҶҶ |
| иҰҒд»Ӣиӯ·5 | 362,170еҶҶ | 36,217еҶҶ | 72,434еҶҶ | 108,651еҶҶ |
еҲ©з”ЁйҷҗеәҰйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹеҲҶгҒҜе…ЁйЎҚиҮӘе·ұиІ жӢ…гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжңҲгҒӮгҒҹгӮҠгҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒҢдёҠйҷҗйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲгҒҜи¶…гҒҲгҒҹеҲҶгҒ®жү•гҒ„жҲ»гҒ—гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷпјҲй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»пјүгҖӮи©ігҒ—гҒҸгҒҜгҖҒгӮұгӮўгғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒӘгҒ©гҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒёгҒ®е…Ҙеұ…еҫҢгҒ«еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«
е…Ҙеұ…еҫҢгҒ«еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰж¬ЎгҒ®зӮ№гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№
еҝ…гҒҡжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜзҠ¶жіҒзўәиӘҚгҒЁз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгҒ®2гҒӨгҒ§гҒҷгҖӮиІ·гҒ„зү©гҒӘгҒ©гҒ®з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„е…Ҙжөҙд»ӢеҠ©гҒӘгҒ©гҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жңүз„ЎгҒҜж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҖйғЁгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢгӮӘгғ—гӮ·гғ§гғігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҖҒе…Ҙеұ…еүҚгҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒ®зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ№гӮҝгғғгғ•
гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ®й…ҚзҪ®зҠ¶жіҒгҖҒжңүиіҮж јиҖ…гҒ®еңЁзұҚзҠ¶жіҒгҖҒеӨңй–“гҒ®еӢӨеӢҷдҪ“еҲ¶гҒҜж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе°‘ж•°гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨңй–“гҒҜиҒ·е“ЎгӮ’й…ҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲз·ҠжҖҘйҖҡе ұгҒ§еҜҫеҝңпјүгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®иіӘгҒӘгҒ©гӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ®й…ҚзҪ®зҠ¶жіҒгҒӘгҒ©гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮгғ»д»Ӣиӯ·гҒёгҒ®еҜҫеҝң
еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢеҢ»зҷӮгғ»д»Ӣиӯ·гҒ®гғӢгғјгӮәгӮӮж–ҪиЁӯгҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҖҒеҜҫеҝңзҠ¶жіҒгӮ’зўәгҒӢгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮйҖҖеҺ»жқЎд»¶гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®йҖҖеҺ»зҗҶз”ұгӮ’иӘҝгҒ№гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁе…·дҪ“зҡ„гҒӘзҠ¶жіҒгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜе•ҸйЎҢзӮ№гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒӢгӮүеҲ©з”Ё
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒЁгҒқгҒ®еҜҫзӯ–гҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдё»гҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢе…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖҚгҖҢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢдёҚеҚҒеҲҶгҖҚгҖҢдёҖйғЁгҒ§еӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еӣІгҒ„иҫјгҒҝгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒзӣЈиҰ–гӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®еҜҫзӯ–гҒҢгҒЁгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»–гҒ®2гҒӨгҒҜгҖҒж–ҪиЁӯгӮ’ж…ҺйҮҚгҒ«йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгӮ„еӨ–йғЁгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҜҫеҮҰгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮж–ҪиЁӯгҒ®йҒёжҠһиӮўгӮ’зҹҘгӮҠгҒҹгҒ„ж–№гҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ жӨңзҙўгӮөгӮӨгғҲгҒӘгҒ©гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҜгҒ„гҒӢгҒҢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҒ§гҒҜгҖҒгӮЁгғӘгӮўгӮ„дәҲз®—гҖҒеҢ»зҷӮгҒЁзңӢиӯ·гҒ®дҪ“еҲ¶гҒӘгҒ©гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжқЎд»¶гҒ§зөһгӮҠиҫјгӮ“гҒ§ж–ҪиЁӯгӮ’гҒҠжҺўгҒ—гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгҒқгҒҶгҒҜиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзөҗеұҖгҒ©гӮҢгҒ«зөһгӮҠиҫјгӮҒгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚ
гҖҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“ж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹвҖҰвҖҰгҖҚ
гҒқгӮ“гҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒзӣёи«Үе“ЎгҒёгҒ®з„Ўж–ҷзӣёи«ҮгӮӮгҒ”жҙ»з”ЁгҒҸгҒ гҒ•гҒ„пјҒ
е№ҙй–“зҙ„6,120件гҒ®зҙ№д»Ӣе®ҹзёҫгҒ®гҒӮгӮӢгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢгҖҒгҒ”еёҢжңӣгҒ«гғ”гғғгӮҝгғӘгҒ®ж–ҪиЁӯгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰз„Ўж–ҷгҒ§гҒ”зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯйҒёгҒігҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒңгҒІгҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
[5]еҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢ2019е№ҙеәҰд»Ӣиӯ·е ұй…¬ж”№е®ҡгҖҚВ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№



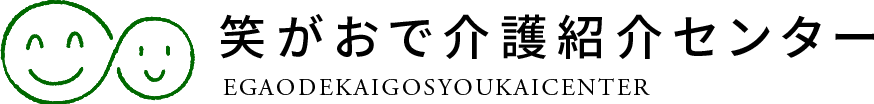




 0120-177-250
0120-177-250