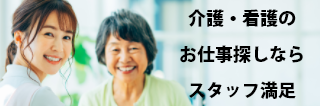гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒЁгҒҜпјҹе…Ҙеұ…жқЎд»¶гғ»гӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒЁйҒёгҒіж–№

гҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«иҲҲе‘ігҒҢгҒӮгӮӢгҒ‘гҒ©и©ізҙ°гҒҢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁжӮ©гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгҖӮгӮҲгҒҸдјјгҒҹж–ҪиЁӯгҒҢжІўеұұгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж··д№ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮз°ЎеҚҳгҒ«иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ®дҪҸе®…гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®жҰӮиҰҒгӮ’и§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«е…Ҙеұ…жқЎд»¶гӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҖҒиІ»з”ЁгҖҒе…Ҙеұ…гҒҷгӮӢдҪҸе®…гҒ®йҒёгҒіж–№гҒӘгҒ©гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ®жғ…е ұгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒе…ЁдҪ“еғҸгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰе…Ҙеұ…гҒ®жӨңиЁҺгӮ’йҖІгӮҒгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒЁгҒҜ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…пјҲпјқгӮөй«ҳдҪҸпјүгҒҜгҖҢй«ҳйҪўиҖ…гҒ®еұ…дҪҸгҒ®е®үе®ҡзўәдҝқгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢгҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гғ»з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®й«ҳйҪўиҖ…гҒҢж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ§еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ®гҖҢдҪҸе®…гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҢе…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй«ҳйҪўиҖ…гҒ®еҝғиә«гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒзҠ¶ж…ӢгҒ«еҝңгҒҳгҒҹдҫҝе®ңгӮ’дҫӣдёҺгҒҷгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгҖҒз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҢе…Ҙеұ…иҖ…гҒҢж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’е•ҸйЎҢгҒӘгҒҸйҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зӣёи«ҮгҒ«еҝңгҒҳгҒҰеҝ…иҰҒгҒӘгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮ’иЎҢгҒҶгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдёҠиЁҳгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’иҰӢгҒҰгӮҸгҒӢгӮӢйҖҡгӮҠгҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҝ…гҒҡжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дё»гҒӘзү№еҫҙгҒҜгҖҒд»–гҒ®д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰе…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҢз·©гӮ„гҒӢгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҙеұ…иҖ…гҒҜиҮӘе®…гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з”ҹжҙ»гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжҜ”ијғзҡ„гҖҒе®үдҫЎгҒӘиіғж–ҷгҒ§е…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгӮӢзӮ№гӮӮгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜгҖҒж–ҪиЁӯгҒ®зү№еҫҙгҒ«гӮҲгӮҠдёҖиҲ¬еһӢгҒЁд»Ӣиӯ·еһӢгҒ«гӮҸгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒЁжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®зү№еҫҙгҒЁйҒ•гҒ„
дёҖиҲ¬еһӢ
зҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гӮ’дё»гҒӘеҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲиҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹ60жӯіжңӘжәҖгӮӮеҜҫиұЎпјүгҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®гҖҢзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҖҚгҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дҪҸе®…гҒЁиЁҖгҒ„жҸӣгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒе…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдҪҸе®…гҒӢгӮүд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӨ–йғЁгҒ®дәӢжҘӯиҖ…гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеӨ–йғЁгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·гӮ„йҖҡжүҖд»Ӣиӯ·гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…ЁгҒҰгҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒӘгҒ©гҒ«гҖҒйҖҖеҺ»гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҝғй…ҚгҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…еүҚгҒ«йҖҖеҺ»жқЎд»¶гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·еһӢ
иҰҒж”ҜжҸҙгҒҫгҒҹгҒҜиҰҒд»Ӣиӯ·гҒ®иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹж–№гӮ’дё»гҒӘеҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјҲгҒҫгҒҹгҒҜд»Ӣиӯ·дәҲйҳІзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјүгҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…ҘжүҖиҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒҜгҖҒзү№е®ҡж–ҪиЁӯгҒ«е…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиҰҒд»Ӣиӯ·иҖ…гҒ«жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®дё–и©ұгҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҖҒзҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶзү№е®ҡж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҒи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҒйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ§гҖҢе…Ҙжөҙгғ»жҺ’жі„гғ»йЈҹдәӢгҒ®д»Ӣиӯ·гҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҖҒжҙ—жҝҜгғ»жҺғйҷӨгҒӘгҒ©гҒ®е®¶дәӢгҖҒеҒҘеә·з®ЎзҗҶгҖҚгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдҪҸе®…гҒҜгҖҒжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·еһӢгҒ§гҒҜгҖҒдҪҸе®…гҒ®гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдҪҸе®…гҒ®гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹиЁҲз”»гҒ«еҹәгҒҘгҒҚеӨ–йғЁгҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒе№…еәғгҒ„д»Ӣиӯ·гҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҝңгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдҪҸе®…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·5иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹж–№гҒ§гӮӮе…Ҙеұ…еҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒз”ҹжҙ»гҒ®иҮӘз”ұеәҰгҒҜдёҖиҲ¬еһӢгӮҲгӮҠдҪҺгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйҖЈеёҜдҝқиЁјдәәгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢдҪҸе®…гҒҢеӨҡгҒ„зӮ№гӮ„дҪҸе®…ж•°гҒҢе°‘гҒӘгҒ„зӮ№гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡиҰҒд»Ӣиӯ·5гҒЁгҒҜпјҹгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒҠйҮ‘гӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гғ»еңЁе®…д»Ӣиӯ·гҒҜз„ЎзҗҶгҒӘгҒ®гҒӢгӮ’и§ЈиӘ¬
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®е…Ҙеұ…жқЎд»¶
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®еҜҫиұЎгҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗе…Ҙеұ…жқЎд»¶гҖ‘
- иҮӘгӮүеұ…дҪҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дҪҸе®…гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй«ҳйҪўиҖ…
- иҮӘгӮүеұ…дҪҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дҪҸе®…гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй«ҳйҪўиҖ…пјӢеҗҢеұ…иҖ…
гҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶй«ҳйҪўиҖ…гҒҜгҖҒ60жӯід»ҘдёҠгҒ®иҖ…гҒҫгҒҹгҒҜиҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹ60жӯіжңӘжәҖгҒ®иҖ…гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ60жӯіжңӘжәҖгҒ®ж–№гҒҜгҖҒзү№е®ҡз–ҫз—…гҒ§д»Ӣиӯ·гӮ„ж”ҜжҸҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«йҷҗгӮҠ40жӯігҒӢгӮүиҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгӮ’з”іи«ӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҗҢеұ…дәәгҒ®жқЎд»¶гӮӮе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢеҗҢеұ…дәәгҒ®жқЎд»¶гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗеҗҢеұ…дәәгҖ‘
- й…ҚеҒ¶иҖ…
- 60жӯід»ҘдёҠгҒ®иҰӘж—Ҹ
- иҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢ60жӯіжңӘжәҖгҒ®иҰӘж—Ҹ
- зү№еҲҘгҒӘзҗҶз”ұгҒ§еҗҢеұ…гҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁзҹҘдәӢгҒӘгҒ©гҒҢиӘҚгӮҒгӮӢиҖ…
д»ҘдёҠгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒж–ҪиЁӯгҒ”гҒЁгҒ«е…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒиҮӘз«ӢгӮ’жқЎд»¶гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдҪҸе®…гҖҒеҒҘеә·зҠ¶ж…ӢгҒ«е•ҸйЎҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’жқЎд»¶гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдҪҸе®…гҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҶ…е®№гҒҜеҖӢеҲҘгҒ®зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдҪҸе®…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜйҖҖеҺ»жқЎд»¶гӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒд»Ӣиӯ·гӮ„еҢ»зҷӮгҒ®гғӢгғјгӮәгҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒд»–гҒ®е…Ҙеұ…иҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҝ·жғ‘иЎҢзӮәгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒйҖҖеҺ»жқЎд»¶гӮӮзўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®дәәе“Ўеҹәжә–
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ§гҒҜгҖҒгӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒҢе»әзү©гҒ«еёёй§җпјҲж—ҘдёӯпјүгҒ—гҒҰзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гғ»з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒд»ҘдёӢгҒ®дәәе“ЎгҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ[1]
гҖҗж—ҘдёӯгҒ«еёёй§җгҒҷгӮӢдәәе“ЎгҖ‘
- зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәгғ»еҢ»зҷӮжі•дәәгғ»жҢҮе®ҡеұ…е®…гӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯжүҖгҒӘгҒ©гҒ®гӮ№гӮҝгғғгғ•
- д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
- зӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«
- д»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“Ў
- д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®иӘІзЁӢдҝ®дәҶиҖ…
- еҢ»её«
- зңӢиӯ·её«
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒд»ҘдёҠгҒ®дәәе“ЎгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮж—ҘдёӯгҒҜе»әзү©гҒ«еёёй§җгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеёёй§җгҒ—гҒӘгҒ„жҷӮй–“еёҜгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰз·ҠжҖҘйҖҡе ұгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§еҜҫеҝңгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒд»Өе’Ң4е№ҙ9жңҲгҒӢгӮүгҖҒдёҖе®ҡгҒ®жқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ®еёёй§җгҒҢдёҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘжқЎд»¶гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ[2]
гҖҗжқЎд»¶гҖ‘
- е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®еҮҰйҒҮгҒ«ж”ҜйҡңгҒҢгҒӘгҒ„
- еёёй§җгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®еҗҢж„ҸгӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒеҫ—гҒҰгҒ„гӮӢ
гҒ“гҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҖҒд»ҘдёӢгҒ®еҶ…е®№гҒ§зҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜжҸҗдҫӣгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҗгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҖ‘
- еҗ„дҪҸеұ…гҒёгҒ®иЁӘе•ҸгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжҜҺж—Ҙ1еӣһд»ҘдёҠгҖҒзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢ
- еҗ„еұ…дҪҸйғЁеҲҶгҒ«з·ҠжҖҘйҖҡе ұиЈ…зҪ®гӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢ
- е…Ҙеұ…иҖ…гҒҢиғҪеӢ•зҡ„гҒ«зӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢж–№жі•гҒ§гҖҒеӨңй–“гӮ’йҷӨгҒҚгҖҒз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢ
гӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒҢеёёй§җгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дҪҸе®…гӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒд»Ӣиӯ·еһӢгҒҜзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…ҘжүҖиҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒ«еҹәгҒҘгҒҚдәәе“Ўй…ҚзҪ®гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨңй–“еёҜгӮӮ1дәәд»ҘдёҠгҒ®иҒ·е“ЎгӮ’й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒе……е®ҹгҒ—гҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣдҪ“еҲ¶гӮ’ж•ҙгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®иЁӯеӮҷ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜгҖҒиҰҸжЁЎгӮ„иЁӯеӮҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮжәҖгҒҹгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„еҹәжә–гҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе°ӮжңүйғЁгҒЁе…ұз”ЁйғЁгҒ«гӮҸгҒ‘гҒҰдё»гҒӘиЁӯеӮҷеҹәжә–гӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е°ӮжңүйғЁ
е°ӮжңүйғЁгҒҜе…Ҙеұ…иҖ…гҒҢз”ҹжҙ»гҒҷгӮӢеұ…е®ӨгӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҗ„еұ…е®ӨгҒҜгҖҒгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеұ…е®ӨгҒ®йқўз©ҚгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰ25гҺЎд»ҘдёҠгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғӘгғ“гғігӮ°гҖҒгӮӯгғғгғҒгғігҖҒгғҖгӮӨгғӢгғігӮ°гҒӘгҒ©гҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒҢе…ұеҗҢгҒ§еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢйғЁеҲҶгҒ«еҚҒеҲҶгҒӘгӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜ18гҺЎд»ҘдёҠгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҗ„е°ӮжңүйғЁгҒ«гӮӯгғғгғҒгғігғ»ж°ҙжҙ—гғҲгӮӨгғ¬гғ»жөҙе®Өгғ»жҙ—йқўиЁӯеӮҷгғ»еҸҺзҙҚиЁӯеӮҷгӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮй«ҳйҪўиҖ…гҒҢе…ұеҗҢгҒ§еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢйғЁеҲҶгҒ«иӘ°гҒ§гӮӮеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮӯгғғгғҒгғігғ»жөҙе®Өгғ»еҸҺзҙҚиЁӯеӮҷгӮ’еӮҷгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҗ„е°ӮжңүйғЁеҲҶгҒ«еӮҷгҒҲгӮӢгҒЁгҒҚгҒЁеҗҢзӯүд»ҘдёҠгҒ®дҪҸз’°еўғгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҗ„е°ӮжңүйғЁеҲҶгҒ«гӮӯгғғгғҒгғігғ»жөҙе®Өгғ»еҸҺзҙҚиЁӯеӮҷгӮ’еӮҷгҒҲгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
е…ұз”ЁйғЁ
е…ұз”ЁйғЁгҒҜй«ҳйҪўиҖ…гҒҢе…ұеҗҢгҒ§еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢйғЁеҲҶгӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮе…ұз”ЁйғЁгӮӮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒе…ұз”Ёе»ҠдёӢгҒ«ж®өе·®гҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ„еӨ–йғЁгҒ«и§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе…ұз”Ёе»ҠдёӢгҒ«и»ўиҗҪйҳІжӯўз”ЁгҒ®жүӢгҒҷгӮҠгҒҢеҸ–гӮҠгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖҒе…ұз”ЁгҒ®йҡҺж®өгҒ®зүҮеҒҙгҒ«дёҖе®ҡгҒ®жқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒҷжүӢгҒҷгӮҠгҒҢеҸ–гӮҠгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒе…ұз”ЁйғЁгҒ«гӮ№гғқгғјгғ„гӮёгғ гҒӘгҒ©гҒ®гғ¬гӮҜгғ¬гғјгӮ·гғ§гғіиЁӯеӮҷгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…ұз”ЁйғЁгҒ®иЁӯеӮҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘҝгҒ№гӮӢгҒЁгҖҒгғ©гӮӨгғ•гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдҪҸе®…гӮ’йҒёгҒігӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№
з¶ҡгҒ„гҒҰгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е®үеҗҰзўәиӘҚгғ»иҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№
е®үеҗҰзўәиӘҚгғ»иҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дҪҸе®…гҒ§жҸҗдҫӣгӮ’зҫ©еӢҷгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒдҪ•гҒӢгҒ—гӮүгҒ®ж–№жі•гҒ§е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®е®үеҗҰгӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮз·ҠжҖҘжҷӮгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒёгҒ®йҖЈзөЎгӮӮиЎҢгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„ж–№жі•гҒҜдәӢжҘӯиҖ…гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеұ…е®ӨгӮ’иЁӘе•ҸгҒ—гҒҹгӮҠгғӘгӮәгғ гӮ»гғігӮөгғјгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒе–«йЈҹгӮ„еӨ–еҮәгҖҒгӮҙгғҹеҮәгҒ—гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дҪҸе®…гҒ§жҸҗдҫӣгӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒӢгӮүзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮ’еёҢжңӣгҒ—гҒӘгҒ„ж—ЁгҒ®з”ігҒ—еҮәгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгӮӮгҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒҜйӣ»и©ұгҒӘгҒ©йҒ©еҲҮгҒӘж–№жі•гҒ§еҪ“и©ІгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе…Ҙеұ…гҒҷгӮӢгҒЁеҝ…гҒҡжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№
з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гӮӮгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®дҪҸе®…гҒ§жҸҗдҫӣгӮ’зҫ©еӢҷгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гғ»д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зңӢиӯ·её«гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢгӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒҢгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёҠгҒ®зӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮгӮ„д»Ӣиӯ·гҒ«й–ўгҒҷгӮӢзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҰеҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮҠгҖҒзӨҫдјҡеҸӮеҠ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№жі•гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒ家ж—ҸгҒёгҒ®йҖЈзөЎгӮ’д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйӣ»зҗғдәӨжҸӣгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгҒ—гҒҹгӮҠгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеҢ»зҷӮгғ»д»Ӣиӯ·гҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢзӣёи«ҮгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒз”ҹжҙ»е…ЁиҲ¬гҒ®зӣёи«ҮгӮ’иЎҢгҒҲгӮӢзӮ№гҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮ1дәәжҡ®гӮүгҒ—гҒ«дёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒӘгҒ©гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҝғеј·гҒ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘзӣёи«ҮгҒ®ж–№жі•гҒҜдҪҸе®…гҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…иҖ…гҒЁгҒ®йқўи«ҮгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒи©ігҒ—гҒ„еҶ…е®№гҒҜзўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
з·ҠжҖҘжҷӮеҜҫеҝңгӮөгғјгғ“гӮ№
еӨҡгҒҸгҒ®дҪҸе®…гҒҢжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз·ҠжҖҘжҷӮеҜҫеҝңгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮз·ҠжҖҘжҷӮеҜҫеҝңгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒдҪ•гҒӢгҒ—гӮүгҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢй§ҶгҒ‘гҒӨгҒ‘гҒҰеҝ…иҰҒгҒӘеҜҫеҝңгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢиө·гҒҚгҒҹе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®еұ…е®ӨгӮ’иЁӘгӮҢгҒҰзҠ¶жіҒгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҖҒеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰж•‘жҖҘи»ҠгӮ’жүӢй…ҚгҖҒ家ж—ҸгҒёйҖЈзөЎгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®й–“гҒ«гҖҒгғҗгӮӨгӮҝгғ«гӮөгӮӨгғігӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж•‘жҖҘйҡҠе“ЎгҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ®зҷәиҰӢж–№жі•гҒҜдҪҸе®…гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒз·ҠжҖҘйҖҡе ұиЈ…зҪ®гӮ„гғӘгӮәгғ гӮ»гғігӮөгғјгҒ®жҙ»з”ЁгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгғӘгӮәгғ гӮ»гғігӮөгғјгҒҜгҖҒз”ҹжҙ»гҒ®гғӘгӮәгғ гҒ«и‘—гҒ—гҒ„еӨүеҢ–гҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«иҮӘеӢ•гҒ§йҖҡе ұгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгӮ»гғігӮөгғјгҒ§гҒҷгҖӮ
йЈҹдәӢжҸҗдҫӣгӮөгғјгғ“гӮ№
йЈҹдәӢжҸҗдҫӣгӮөгғјгғ“гӮ№гӮӮгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дҪҸе®…гҒҢе®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәй«ҳйҪўиҖ…дҪҸе®…еҚ”дјҡгҒҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®зҸҫзҠ¶гҒЁеҲҶжһҗгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒйЈҹдәӢжҸҗдҫӣгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдҪҸе®…гҒ®еүІеҗҲгҒҜ96.2пј…гҒ§гҒҷгҖӮ[3]зҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гғ»з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҸҗдҫӣгӮ’зҫ©еӢҷгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒ»гҒјгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢе®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒҜдҪҸе®…гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҪҸе®…еҶ…гҒ§йЈҹдәӢгӮ’дҪңгҒЈгҒҰжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеӨ–йғЁдәӢжҘӯиҖ…гҒ«дё»гҒӘиӘҝзҗҶгӮ’д»»гҒӣгҒҰдҪҸе®…еҶ…гҒ§гҒҜд»•дёҠгҒ’гҒ гҒ‘гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеӨ–йғЁдәӢжҘӯиҖ…гҒӢгӮүејҒеҪ“гӮ’иӘҝйҒ”гҒ—гҒҰжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҖҒгӮ«гғӯгғӘгғјгӮ„ж „йӨҠгғҗгғ©гғігӮ№гҒ®иЁҲз®—гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮеҒҘеә·зҡ„гҒӘйЈҹз”ҹжҙ»гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдҪҸе®…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®иҰҒжңӣгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒеҲ»гҒҝйЈҹгғ»гғҹгӮӯгӮөгғјйЈҹгҒӘгҒ©гҒ«еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒз”ҹжҙ»гҒ®еҲ©дҫҝжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҶ…е®№гҒҜдҪҸе®…гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҺғйҷӨгғ»жҙ—жҝҜгғ»иІ·гҒ„зү©гҒ®д»ЈиЎҢгҖҒйҖҡйҷўгғ»иІ·гҒ„зү©гҒ®д»ҳгҒҚж·»гҒ„гҖҒе®…й…ҚиҚ·зү©гҒ®й җгҒӢгӮҠгҒӘгҒ©гҒҢи©ІеҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ家дәӢгҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹж–№гӮ„иІ·гҒ„зү©гҒ§йҮҚгҒ„иҚ·зү©гӮ’йҒӢгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹж–№гҒӘгҒ©гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдҫҝеҲ©гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒгӮӘгғ—гӮ·гғ§гғігҒЁгҒ—гҒҰжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҶ…е®№гҒЁж–ҷйҮ‘гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№
дёҖиҲ¬еһӢгҒ®дҪҸе®…гҒ§гҒҜгҖҒдҪөиЁӯгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢд»Ӣиӯ·дәӢжҘӯжүҖгӮ„еӨ–йғЁгҒ®д»Ӣиӯ·дәӢжҘӯжүҖгҒЁеҘ‘зҙ„гҒ—гҒҰд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ«еҹәгҒҘгҒҸд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒдәӢжҘӯиҖ…иҮӘиә«гҒҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәйҒ©з”ЁеӨ–гҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒиІ»з”ЁгҒҜе…ЁйЎҚиҮӘе·ұиІ жӢ…гҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·еһӢгҒ®дҪҸе®…пјҲзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…ҘжүҖиҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢдәӢжҘӯжүҖпјүгҒ§гҒҜгҖҒдәӢжҘӯиҖ…иҮӘиә«гҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдәӢжҘӯиҖ…гҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮ’йҒ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢзӮ№гҒЁгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠеҖӢеҲҘгҒ®еҘ‘зҙ„гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒӘгҒ„зӮ№гҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®иІ»з”Ё
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®иІ»з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҲқжңҹиІ»з”Ё
еҗҢдҪҸе®…гҒ®еҘ‘зҙ„ж–№ејҸгҒҜеҲ©з”ЁжЁ©ж–№ејҸгҒЁиіғиІёеҖҹж–№ејҸгҒ«гӮҸгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҲ©з”ЁжЁ©ж–№ејҸгҒҜеұ…дҪҸйғЁеҲҶгҒЁгӮөгғјгғ“гӮ№йғЁеҲҶгҒ®еҘ‘зҙ„гҒҢдёҖдҪ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№ејҸгҖҒиіғиІёеҖҹж–№ејҸгҒҜеұ…дҪҸйғЁеҲҶгҒЁгӮөгғјгғ“гӮ№йғЁеҲҶгҒ®еҘ‘зҙ„гҒҢеҲҘгҖ…гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№ејҸгҒ§гҒҷгҖӮеҲ©з”ЁжЁ©ж–№ејҸгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…жҷӮгҒ«1гӮ«жңҲгҒӮгҒҹгӮҠгҒ®иіғж–ҷгҒ«жғіе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢе…Ҙеұ…жңҹй–“гӮ’д№—гҒҳгҒҹе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгҒ“гҒ®ж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜе°‘ж•°жҙҫгҒ§гҒҷгҖӮиіғиІёеҖҹж–№ејҸгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжңҲгҖ…гҒ®иІ»з”ЁгӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҸж–№ејҸгҒЁиҖғгҒҲгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮе…¬зӣҠзӨҫеӣЈжі•дәәе…ЁеӣҪжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ еҚ”дјҡгҒҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’0еҶҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®еүІеҗҲгҒҜ70.8пј…гҒ§гҒҷгҖӮ[4]гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®еҘ‘зҙ„ж–№ејҸгҒ§гӮӮгҖҒж•·йҮ‘гғ»дҝқиЁјйҮ‘гҒҜгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲж•·йҮ‘гҒҜйҖҖеҺ»жҷӮгҒ«еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰиҝ”йҮ‘гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷпјүгҖӮеҗҢиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒе…Ҙеұ…жҷӮгҒ«ж”Ҝжү•гҒҶж•·йҮ‘гғ»дҝқиЁјйҮ‘гҒ®е№іеқҮпјҲйқһзү№е®ҡж–ҪиЁӯпјүгҒҜ96,756еҶҶгҒ§гҒҷгҖӮ[5]
жңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷ
жңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰж¬ЎгҒ®гӮӮгҒ®гҒӘгҒ©гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҶ…иЁігҖ‘
- еұ…дҪҸиІ»з”Ё
- з®ЎзҗҶиІ»з”Ё
- йЈҹиІ»
- е…үзҶұж°ҙиІ»
е…¬зӣҠзӨҫеӣЈжі•дәәе…ЁеӣҪжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ еҚ”дјҡгҒҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒжңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷгҒ®з·ҸйЎҚгҒҜ142,215еҶҶгҒ§гҒҷгҖӮеҶ…иЁігҒҜгҖҒеұ…дҪҸиІ»з”Ё61,344еҶҶгҖҒз®ЎзҗҶиІ»з”Ё38,747еҶҶгҖҒйЈҹиІ»45,877еҶҶгҖҒе…үзҶұж°ҙиІ»1,566еҶҶгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲиЁҲз®—ж–№ејҸгҒ®еҪұйҹҝгҒ§е°ҸиЁҲгҒЁеҗҲиЁҲйҮ‘йЎҚгҒҜдёҖиҮҙгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮз®ЎзҗҶиІ»з”ЁгҒ«гҒҜгҖҒе…ұзӣҠиІ»гғ»з®ЎзҗҶиІ»гҒ«еҠ гҒҲгҖҒз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгғ»д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҖҒеҹәжң¬гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ[6]гҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘжңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҒҜгҖҒж–ҪиЁӯгҒ®гӮ°гғ¬гғјгғүгӮ„з«Ӣең°гҒӘгҒ©гҒ®жқЎд»¶гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйғҪеёӮйғЁгҒ®дҪҸе®…гҒҜгҖҒжңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«гҒҜиүҜгҒ„зӮ№гҒЁжӮӘгҒ„зӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдё»гҒӘиүҜгҒ„зӮ№гҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲв‘ ж–ҪиЁӯж•°гҒҢеӨҡгҒҸе…Ҙеұ…гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®иүҜгҒ„зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж–ҪиЁӯж•°гҒҢеӨҡгҒ„гҒҹгӮҒе…Ҙеұ…еҫ…гҒЎгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮиҮӘе®…гҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гҒ«дёҚе®үгӮ’иҰҡгҒҲгҒҹгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒӘгҒ©гҒ§гҖҒгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«е…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәй«ҳйҪўиҖ…дҪҸе®…еҚ”дјҡгҒҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒ2023е№ҙ11жңҲжҷӮзӮ№гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®жҲёж•°гҒҜ284,993жҲёгҒ§гҒҷгҖӮ2019е№ҙ12жңҲжҷӮзӮ№гҒ®жҲёж•°гҒҢ250,352жҲёгҖҒ2017е№ҙ12жңҲжҷӮзӮ№гҒ®жҲёж•°гҒҢ225,374жҲёгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеў—еҠ гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ[7]д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰе…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҢз·©гӮ„гҒӢгҒӘзӮ№гӮӮйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰ60жӯід»ҘдёҠгҒ®ж–№гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·гӮ’е•ҸгӮҸгҒҡе…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеҲ©з”ЁгҒ—гӮ„гҒҷгҒ•гҒҜгҖҒгғЎгғӘгғғгғҲгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲв‘ЎиҮӘз”ұгҒӘз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢ
еҗҚз§°гҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢйҖҡгӮҠгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜй«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢдҪҸе®…гҒ®дёҖеҪўж…ӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒе…Ҙеұ…еүҚгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘз”ҹжҙ»гӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеҘҪгҒҚгҒӘгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§е…ҘжөҙгҒ—гҒҹгӮҠиҮӘз”ұгҒ«еӨ–еҮәгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮиҮӘеҲҶгӮүгҒ—гҒ„жҡ®гӮүгҒ—гӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„ж–№гҒ§гӮӮжәҖи¶ігҒ§гҒҚгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„йЈҹдәӢжҸҗдҫӣгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢзӮ№гӮӮиҰӢйҖғгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзҸҫеңЁгҒ®з”ҹжҙ»гӮҲгӮҠгӮӮеҝ«йҒ©гҒ«жҡ®гӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе°Ӯй–Җ家гҒӢгӮүгӮөгғқгғјгғҲгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒиҮӘз”ұеәҰгҒ®й«ҳгҒ„з”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢзӮ№гҒҜйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«гҒҜж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҒ„зӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…еүҚгҒ«жҠјгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲв‘ еҢ»её«гӮ„зңӢиӯ·её«гҒҢеёёй§җгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮӢ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒҜгҖҒгӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гғ»з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ®дҫӢгҒЁгҒ—гҒҰеҢ»её«гӮ„зңӢиӯ·её«гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…ЁгҒҰгҒ®дҪҸе®…гҒ§еҢ»её«гӮ„зңӢиӯ·её«гҒҢеёёй§җгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҢ»её«гӮ„зңӢиӯ·её«гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгӮұгӮўгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒҢеёёй§җгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжүӢеҺҡгҒ„гӮөгғқгғјгғҲгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮж—ҘдёӯгҒ®дәәе“Ўй…ҚзҪ®гӮ„еӨңй–“гҒ®дәәе“Ўй…ҚзҪ®гҖҒзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮ„з”ҹжҙ»зӣёи«ҮгҒ®ж–№жі•гҒӘгҒ©гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒӢгӮүе…Ҙеұ…гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲв‘ЎиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁе…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢ
иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁе…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дҪҸе®…гҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гӮӮжҠјгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢж–№гҒҜгҖҒйҒёжҠһгҒ§гҒҚгӮӢдҪҸе®…гҒ®е№…гҒҢзӢӯгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҜҫеҝңзҠ¶жіҒгҒҜдҪҸе®…гҒ§з•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒеҖӢеҲҘгҒ®зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒӘгҒ©гҒ®й«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дҪҸе®…гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҜз·©гӮ„гҒӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиӘ°гҒ§гӮӮе…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе…Ҙеұ…еҫҢгҒ«иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁйҖҖеҺ»гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҙеұ…еүҚгҒ«йҖҖеҺ»жқЎд»¶гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰеӮҷгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒи©ІеҪ“гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«еҜҫеҮҰгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·еһӢгҒҜиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„ж–№гҒ§гӮӮе…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҪҸе®…ж•°гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒе…Ҙеұ…гҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҜй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гӮӮдәҲгӮҒжҠјгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гӮ’йҒёгҒ¶йҡӣгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«гҒҜгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘйҒёжҠһиӮўгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…е…ҲгӮ’йҒёгҒ¶йҡӣгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғқгӮӨгғігғҲв‘ з«Ӣең°гғ»гӮўгӮҜгӮ»гӮ№
з«Ӣең°жқЎд»¶гӮ„гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒе…Ҙеұ…еҫҢгӮӮеҝ«йҒ©гҒӘз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз«Ӣең°жқЎд»¶гҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ§еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–ҪиЁӯгҒЁгҒ®и·қйӣўгӮ’зўәгҒӢгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮж–ҪиЁӯгҒ®дҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғјгғ‘гғјгғ»йҮ‘иһҚж©ҹй–ўгғ»еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж–ҪиЁӯгҒҢдҪҸе®…гҒ®иҝ‘гҒҸгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁдҫҝеҲ©гҒӘз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒдҪҸе®…гӮ’й »з№ҒгҒ«иЁӘгӮҢгӮӢ家ж—ҸгҒӘгҒ©гҒ®зӣ®з·ҡгҒ§иҖғгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮйҖҡгҒ„гҒ«гҒҸгҒ„гҒЁгҖҒиЁӘе•Ҹеӣһж•°гҒҢжёӣгҒЈгҒҹгӮҠдҪҷиЁҲгҒӘиІ жӢ…гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…гҒҷгӮӢдҪҸе®…гӮ’жұәе®ҡгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒй–ўдҝӮгҒҷгӮӢж–№гҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гғқгӮӨгғігғҲв‘ЎжҸҗдҫӣгӮөгғјгғ“гӮ№
е…Ҙеұ…еҫҢгҒ«еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮӮзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дҪҸе®…гҒҢжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҠ¶жіҒжҠҠжҸЎгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүд»ҘеӨ–гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢдҪҸе®…гӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҝ…иҰҒд»ҘдёҠгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒиІ»з”ЁгӮ’無駄гҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒжң¬еҪ“гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’иҰӢжҘөгӮҒгӮӢеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®е“ҒиіӘгӮӮзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеёҢжңӣгҒ—гҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒе“ҒиіӘгҒҢи‘—гҒ—гҒҸжӮӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒҜгҖҒж–ҪиЁӯиҰӢеӯҰгӮ„дҪ“йЁ“е…Ҙеұ…гҒӘгҒ©гҒ§зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғқгӮӨгғігғҲв‘ўиІ»з”Ё
е…Ҙеұ…гҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгӮӮзўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮзўәиӘҚгӮ’жҖ гӮӢгҒЁгҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒ«еҺігҒ—гҒҸгҒӘгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®ж”Ҝжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…жҷӮгҒ«е®¶иіғгҒӘгҒ©гӮ’еүҚжү•гҒ„гҒҷгӮӢеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒЁе®¶иіғгҒӘгҒ©гӮ’жҜҺжңҲж”Ҝжү•гҒҶжңҲжү•гҒ„ж–№ејҸгҒ«гӮҸгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒ«гҒҜжңҲйЎҚеҲ©з”Ёж–ҷгӮ’жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…Ҙеұ…жҷӮгҒ«гҒҫгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹйҮ‘йЎҚгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮи©ізҙ°гҒ®зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…Ҙеұ…еҫҢгҒ«д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҝҪеҠ гҒ§гҒӢгҒӢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢиІ»з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒҜпјҹзӣёе ҙгҒЁе®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢгғқгӮӨгғігғҲ
гғқгӮӨгғігғҲв‘ЈйЈҹдәӢгҒ®еҶ…е®№
е…Ҙеұ…еҫҢгҒ®жәҖи¶іеәҰгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢйЈҹдәӢгҒ§гҒҷгҖӮйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣж–№жі•гӮ„йЈҹдәӢгҒ®еҶ…е®№гӮӮгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮжҸҗдҫӣж–№жі•гҒҜгҖҒдҪҸе®…еҶ…гҒ§иӘҝзҗҶгҖҒејҒеҪ“гӮ’жүӢй…ҚгҒӘгҒ©гҒ«гӮҸгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫЎеҖӨиҰігҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжҸҗдҫӣж–№жі•гӮ’йҒёгҒ¶гҒЁжәҖи¶ігҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҲ»гҒҝйЈҹгӮ„гғҹгӮӯгӮөгғјйЈҹгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҜҫеҝңзҠ¶жіҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮзўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮдәҲгӮҒгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒй•·гҒҸдҪҸгҒҝз¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢдҪҸе®…гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйЈҹдәӢгҒ®еҶ…е®№гҒӘгҒ©гӮӮгҖҒж–ҪиЁӯиҰӢеӯҰгӮ„дҪ“йЁ“е…Ҙеұ…гҒ§зўәгҒӢгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢжөҒгӮҢ
гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒёе…Ҙеұ…гҒҷгӮӢжөҒгӮҢгҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗе…Ҙеұ…гҒ®жөҒгӮҢгҖ‘
- жғ…е ұеҸҺйӣҶ
- иіҮж–ҷи«ӢжұӮ
- иҰӢеӯҰгҒҫгҒҹгҒҜдҪ“йЁ“е…Ҙеұ…
- д»®з”ігҒ—иҫјгҒҝгҒЁйқўи«Ү
- еҘ‘зҙ„з· зөҗ
- е…Ҙеұ…
жғ…е ұеҸҺйӣҶгҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ жӨңзҙўгӮөгӮӨгғҲгҒӘгҒ©гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁеҠ№зҺҮгӮҲгҒҸиЎҢгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮиіҮж–ҷи«ӢжұӮгӮ„иҰӢеӯҰгҒ®з”ігҒ—иҫјгҒҝгӮӮеҗҢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§иЎҢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮиҰӢеӯҰгҒҫгҒҹгҒҜдҪ“йЁ“е…Ҙеұ…гҒ§гҒҜгҖҒиіҮж–ҷгҒ§гӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеұ…е®Өгғ»иЁӯеӮҷгҒ®дҪҝгҒ„еӢқжүӢгҖҒгӮ№гӮҝгғғгғ•гғ»е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®йӣ°еӣІж°—гҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе•ҸйЎҢгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°д»®з”ігҒ—иҫјгҒҝгҒЁйқўи«ҮгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮйқўи«ҮгҒ§гҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ„е…Ҙеұ…еҫҢгҒ®еёҢжңӣгҒӘгҒ©гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҘ‘зҙ„гҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…жңҹй–“гҒҢй•·гҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰгҖҒзҙ°йғЁгҒҫгҒ§зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҙеұ…жҷӮгҒҜз”ҹжҙ»з”Ёе“ҒгӮ’иҮӘеҲҶгҒ§з”Ёж„ҸгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеӨ§еһӢ家具гӮ„еӨ§еһӢ家йӣ»гҒҜгҖҒеӮҷгҒҲд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иҮӘеҲҶгҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гӮ’йҒёгҒігҒҫгҒ—гӮҮгҒҶ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒҢж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ§еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјж§ӢйҖ гҒ®гҖҢдҪҸе®…гҖҚгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮдё»гҒӘеј·гҒҝгҒҜз”ҹжҙ»гҒ®иҮӘз”ұеәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒдё»гҒӘејұгҒҝгҒҜиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгӮ„еҒҘеә·зҠ¶ж…ӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜе…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„ж”Ҝжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҢдәӢжҘӯиҖ…гҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮӢзӮ№гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮдҪҸе®…гҒ”гҒЁгҒ®зү№еҫҙгҒЁиҮӘиә«гҒ®гғӢгғјгӮәгӮ’з…§гӮүгҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҖҒжҡ®гӮүгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„дҪҸе®…гӮ’йҒёгҒігӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®йҒёжҠһиӮўгӮ’зҹҘгӮҠгҒҹгҒ„ж–№гҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ жӨңзҙўгӮөгӮӨгғҲгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҒ§гҒҜгҖҒгӮЁгғӘгӮўгӮ„дәҲз®—гҖҒеҢ»зҷӮгҒЁзңӢиӯ·гҒ®дҪ“еҲ¶гҒӘгҒ©гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжқЎд»¶гҒ§зөһгӮҠиҫјгӮ“гҒ§ж–ҪиЁӯгӮ’гҒҠжҺўгҒ—гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгҒқгҒҶгҒҜиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзөҗеұҖгҒ©гӮҢгҒ«зөһгӮҠиҫјгӮҒгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚ
гҖҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“ж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹвҖҰвҖҰгҖҚ
гҒқгӮ“гҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒзӣёи«Үе“ЎгҒёгҒ®з„Ўж–ҷзӣёи«ҮгӮӮгҒ”жҙ»з”ЁгҒҸгҒ гҒ•гҒ„пјҒ
е№ҙй–“зҙ„6,120件гҒ®зҙ№д»Ӣе®ҹзёҫгҒ®гҒӮгӮӢгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢгҖҒгҒ”еёҢжңӣгҒ«гғ”гғғгӮҝгғӘгҒ®ж–ҪиЁӯгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰз„Ўж–ҷгҒ§гҒ”зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯйҒёгҒігҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒңгҒІгҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
В
[1]еҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҚВ
[3]еҮәе…ёпјҡдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәй«ҳйҪўиҖ…дҪҸе®…еҚ”дјҡгҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒ®зҸҫзҠ¶гҒЁеҲҶжһҗгҖҚВ
[4][5][6]еҮәе…ёпјҡе…¬зӣҠзӨҫеӣЈжі•дәәе…ЁеӣҪжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ еҚ”дјҡгҖҢй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸгҒҫгҒ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒӢе–¶еҪўж…ӢгҒ®еӨҡж§ҳеҢ–гҒ«й–ўгҒҷгӮӢе®ҹж…ӢиӘҝжҹ»з ”究е ұе‘ҠжӣёгҖҚВ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№



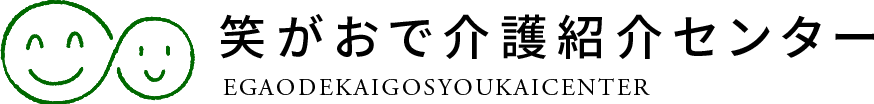




 0120-177-250
0120-177-250