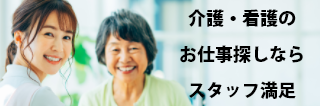гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгғ»гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒҠгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„е…Ҙеұ…гҒ®жөҒгӮҢ

гҖҢгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒ‘гҒ©гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®пјҹгҖҚгҖҢзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮүж•ҷгҒҲгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгҖӮ
е…Ҙеұ…еҫҢгҒ®еҝғй…ҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜеӨҡгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒҜгҖҒжүҖеҫ—гҒҢдҪҺгҒ„ж–№гҒ§гӮӮеҲ©з”ЁгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„дҪҸгҒҫгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒж–ҪиЁӯгҒ®зү№еҫҙгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒжҖқгӮҸгҒ¬гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§йҖҖеҺ»гӮ’иҝ«гӮүгӮҢгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®жҰӮиҰҒгӮ’и§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғЎгғӘгғғгғҲгғ»гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҖҒе…Ҙеұ…гҒ®жөҒгӮҢгҒӘгҒ©гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ®жғ…е ұгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒзӣ®зҡ„гҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮеҲ©з”ЁгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒЁгҒҜ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒҜгҖҒиҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒз„Ўж–ҷеҸҲгҒҜдҪҺйЎҚгҒӘж–ҷйҮ‘гҒ§гҖҒиә«дҪ“ж©ҹиғҪгҒ®дҪҺдёӢзӯүгҒ«гӮҲгӮҠиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’е–¶гӮҖгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдёҚе®үгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢиҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒ家ж—ҸгҒ«гӮҲгӮӢжҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӣ°йӣЈгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’е…ҘжүҖгҒ•гҒӣгҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҖҒе…ҘжөҙзӯүгҒ®жә–еӮҷгҖҒзӣёи«ҮеҸҠгҒіжҸҙеҠ©гҖҒзӨҫдјҡз”ҹжҙ»дёҠгҒ®дҫҝе®ңгҒ®дҫӣдёҺгҒқгҒ®д»–гҒ®ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёҠеҝ…иҰҒгҒӘдҫҝе®ңгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе…ҘжүҖиҖ…гҒҢе®үеҝғгҒ—гҒҰз”ҹгҒҚз”ҹгҒҚгҒЁжҳҺгӮӢгҒҸз”ҹжҙ»гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
еј•з”Ёе…ғпјҡe-GOVжі•д»ӨжӨңзҙўгҖҢе№іжҲҗдәҢеҚҒе№ҙеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒд»Ө第зҷҫдёғеҸ· и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®иЁӯеӮҷеҸҠгҒійҒӢе–¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжә–гҖҚВ
еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ60жӯід»ҘдёҠпјҲ60жӯід»ҘдёҠгҒ®й…ҚеҒ¶иҖ…гҒЁдёҖз·’гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜ60жӯіжңӘжәҖгҒ§гӮӮеҸҜпјүгҒ§иҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгҒҢгҒӮгӮӢж–№гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜд»ҘдёӢгҒ®зЁ®йЎһгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
| йЎһеһӢ | жҰӮиҰҒ |
| AеһӢ | й«ҳйҪўгҒӘгҒ©гҒ®гҒҹгӮҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гҒ«дёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒ§гҖҒ家ж—ҸгҒӢгӮүжҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж–№гӮ’е…ҘжүҖгҒ•гҒӣгҒҰгҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгғ»е…ҘжөҙгҒ®жә–еӮҷгғ»зӣёи«ҮжҸҙеҠ©гҒӘгҒ©гӮ’жҸҗдҫӣ |
| BеһӢ | иҰҒ件гҒҜAеһӢгҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҖҒиҮӘзӮҠгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢж–№гӮ’е…ҘжүҖгҒ•гҒӣгҒҰгҖҒе…ҘжөҙгҒ®жә–еӮҷгғ»зӣёи«ҮжҸҙеҠ©гҒӘгҒ©гӮ’жҸҗдҫӣ |
| гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲCеһӢпјү | иә«дҪ“ж©ҹиғҪгҒ®дҪҺдёӢгҒӘгҒ©гҒ§иҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢж–№гҒ§гҖҒ家ж—ҸгҒӢгӮүжҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж–№гӮ’е…ҘжүҖгҒ•гҒӣгҒҰгҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгғ»е…ҘжөҙгҒ®жә–еӮҷгғ»зӣёи«ҮжҸҙеҠ©гҒӘгҒ©гӮ’жҸҗдҫӣ |
| йғҪеёӮеһӢ | ж—ўжҲҗеёӮиЎ—ең°гҒӘгҒ©гҒ«иЁӯзҪ®пјҲеҺҹеүҮпјүгҒ•гӮҢгҖҒе…ҘжүҖе®ҡе“Ў20дәәд»ҘдёӢгҒ§гҖҒйғҪйҒ“еәңзңҢзҹҘдәӢгҒҢжҢҮе®ҡгҒ—гҒҹж–ҪиЁӯ |
BеһӢгҒ®гҒҝиҮӘзӮҠгҒҢеҺҹеүҮгҒ§гҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜдёҖйғЁгҒ®гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®гҒҝгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲгҒқгҒ®д»–гҒ®ж–ҪиЁӯгӮӮеӨ–йғЁгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜеҲ©з”ЁеҸҜпјүгҖӮAеһӢгҒЁBеһӢгҒҜж–°иЁӯгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҢгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲCеһӢпјүгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒҜгҖҒзү№еҫҙгҒ«гӮҲгӮҠдёҖиҲ¬еһӢпјҲиҮӘз«ӢеһӢпјүгҒЁд»Ӣиӯ·еһӢгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖиҲ¬еһӢпјҲиҮӘз«ӢеһӢпјү
иә«дҪ“ж©ҹиғҪгҒ®дҪҺдёӢгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢ60жӯід»ҘдёҠпјҲй…ҚеҒ¶иҖ…гҒҢ60жӯід»ҘдёҠгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ60жӯіжңӘжәҖгҒ§гӮӮеҸҜпјүж–№гҒ§гҖҒ家ж—ҸгҒӢгӮүжҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж–№гҒҢеҜҫиұЎгҒ§гҒҷпјҲиҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹй«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҗ«гӮҖпјүгҖӮ
з„Ўж–ҷгҒҫгҒҹгҒҜдҪҺйЎҚгҒӘж–ҷйҮ‘гҒ§гҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгғ»е…ҘжөҙгҒӘгҒ©гҒ®жә–еӮҷгғ»зӣёи«ҮжҸҙеҠ©гҒӘгҒ©гҖҒзӨҫдјҡз”ҹжҙ»дёҠгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёҠгҒ®дҫҝе®ңгӮ’дҫӣдёҺгғ»жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷпјҲе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒҜж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜжҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәжі•дёҠгҖҒеұ…е®…гҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӨ–йғЁгҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒЁеҖӢеҲҘгҒ«еҘ‘зҙ„гҒ—гҒҰиЁӘе•Ҹд»Ӣиӯ·гҖҒгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·еһӢ
еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ65жӯід»ҘдёҠгҒ§иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰ1д»ҘдёҠгҒ®ж–№гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢж–№гҒҢеҜҫиұЎгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеұ…е®…гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒзү№е®ҡж–ҪиЁӯпјҲгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјүгҒ«е…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гӮ’еҜҫиұЎгҒ«жҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгӮӢйЈҹдәӢгғ»е…Ҙжөҙгғ»жҺ’жі„гҒӘгҒ©гҒ®д»Ӣиӯ·гҖҒзҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұгҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҒӘгҒ©гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒд»Ӣиӯ·еһӢгҒ§гҒҜж–ҪиЁӯгҒҢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷпјҲж–ҪиЁӯгҒ®иҒ·е“ЎгҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹиЁҲз”»гҒ«еҹәгҒҘгҒҚеӨ–йғЁгҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒе…Ҙеұ…жҷӮгӮҲгӮҠгӮӮд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢеәҰеҗҲгҒ„гҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдҪҸгҒҝж…ЈгӮҢгҒҹз’°еўғгҒ§з”ҹжҙ»гӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒЁд»–гҒ®иҖҒдәәеҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒЁжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҒгӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ гҒ®йҒ•гҒ„гӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ’е…Ҙеұ…гҒ•гҒӣгҒҰж¬ЎгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢиҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯгҒӘгҒ©д»ҘеӨ–гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҷгҖӮ гҖҗгӮөгғјгғ“гӮ№гҖ‘
- йЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣ
- д»Ӣиӯ·гҒ®жҸҗдҫӣ
- жҙ—жҝҜгғ»жҺғйҷӨгҒӘгҒ©гҒ®е®¶дәӢгҒ®жҸҗдҫӣ
- еҒҘеә·з®ЎзҗҶ
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®йЎһеһӢгҒЁе…Ҙеұ…иҰҒ件гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
| йЎһеһӢ | е…Ҙеұ…иҰҒ件 | дё»гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№ |
| д»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | 65жӯід»ҘдёҠгғ»иҮӘз«ӢпҪһиҰҒд»Ӣиӯ·5 | д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№ |
| дҪҸе®…еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | 60жӯід»ҘдёҠгғ»иҮӘз«ӢпҪһиҰҒд»Ӣиӯ·5 | з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№ |
| еҒҘеә·еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | 60жӯід»ҘдёҠгғ»иҮӘз«ӢпҪһиҰҒж”ҜжҸҙзЁӢеәҰгҒҫгҒ§ | йЈҹдәӢгҒӘгҒ©гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№ |
еҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеңЁе®…гҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гҒ«дҪ•гҒӢгҒ—гӮүгҒ®дёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢй«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒҜйЎһеһӢгӮ„ж–ҪиЁӯгҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ«жҜ”гҒ№гғ¬гӮҜгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮ„гӮӨгғҷгғігғҲгҒҜе……е®ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиІ»з”ЁйқўгҒ«гӮӮеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒЁжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®зӣ®е®үгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
| ж–ҪиЁӯгҒ®зЁ®еҲҘ | гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№ | жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ |
| еҲқжңҹиІ»з”Ё | 0пҪһ30дёҮеҶҶ | 0пҪһж•°е„„еҶҶ |
| жңҲйЎҚиІ»з”Ё | 6пҪһ20дёҮеҶҶзЁӢеәҰ | 10пҪһ30дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |
гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜе……е®ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гӮҲгӮҠгӮӮиІ»з”ЁгҒҜй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ 10зЁ®йЎһгҒ®зү№еҫҙгӮ„иІ»з”ЁгӮ’дёҖиҰ§и§ЈиӘ¬пјҒйҒ•гҒ„гӮ„йҒёгҒіж–№гҒЁгҒҜ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡд»Ӣиӯ·д»ҳжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®зү№еҫҙгғ»е…Ҙеұ…гҒ®жқЎд»¶гҒЁиІ»з”Ёзӣёе ҙ
гӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒҢ家еәӯзҡ„гҒӘз’°еўғгҒ®гӮӮгҒЁе…Ҙжөҙгғ»жҺ’жі„гғ»йЈҹдәӢгҒӘгҒ©гҒ®д»Ӣиӯ·гҒЁж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒиғҪеҠӣгҒ«еҝңгҒҳгҒҹиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢе…ұеҗҢз”ҹжҙ»дҪҸеұ…гҒ§гҒҷпјҲиӘҚзҹҘз—ҮеҜҫеҝңеһӢе…ұеҗҢз”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·пјүгҖӮиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®иЁәж–ӯгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹиҰҒж”ҜжҸҙ2гғ»иҰҒд»Ӣиӯ·1д»ҘдёҠгҒ®ж–№гҒҢеҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮҠй–ўйҖЈж”ҜжҸҙ2гҒ®ж–№гҒҜд»Ӣиӯ·дәҲйҳІиӘҚзҹҘз—ҮеҜҫеҝңеһӢе…ұеҗҢз”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒ®еҜҫиұЎпјүгҖӮ
зү№еҫҙгҒҜ5пҪһ9дәәгҒ®е…Ҙеұ…иҖ…гҒЁгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ§гҒӘгҒҳгҒҝгҒ®й–ўдҝӮгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠз©ҸгӮ„гҒӢгҒ«йҒҺгҒ”гҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ®гӮөгғқгғјгғҲгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүе…Ҙеұ…иҖ…гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰжҢҒгҒҰгӮӢиғҪеҠӣгӮ’з¶ӯжҢҒгғ»еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҠӘгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒЁгҒҜгҖҒзӣ®зҡ„гӮ„еҪ№еүІгҒҢз•°гҒӘгӮӢж–ҪиЁӯгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮиІ»з”ЁйқўгҒ«гӮӮеӨҡе°‘гҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒЁжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®зӣ®е®үгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
| ж–ҪиЁӯгҒ®зЁ®еҲҘ | гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№ | гӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ |
| еҲқжңҹиІ»з”Ё | 0пҪһ30дёҮеҶҶ | 0пҪһж•°зҷҫдёҮеҶҶ |
| жңҲйЎҚиІ»з”Ё | 6пҪһ20дёҮеҶҶзЁӢеәҰ | 12пҪһ18дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |
еҜҫиұЎиҖ…гҒ®йҒ•гҒ„гӮ’гҒҠгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡйҡңе®іиҖ…гӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ гҒЁгҒҜпјҹзЁ®йЎһгӮ„иІ»з”Ёзӣёе ҙгғ»е…Ҙеұ…гҒ®жөҒгӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲ
дё»гҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰд»ҘдёӢгҒ®зӮ№гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲв‘ жҜ”ијғзҡ„иІ»з”ЁгӮ’е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒҜиҖҒдәәзҰҸзҘү法第20жқЎгҒ®6гҒ§д»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҖҒз„Ўж–ҷеҸҲгҒҜдҪҺйЎҚгҒӘж–ҷйҮ‘гҒ§гҖҒиҖҒдәәгӮ’е…ҘжүҖгҒ•гҒӣгҖҒйЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгҒқгҒ®д»–ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёҠеҝ…иҰҒгҒӘдҫҝе®ңгӮ’дҫӣдёҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢж–ҪиЁӯпјҲ第дәҢеҚҒжқЎгҒ®дәҢгҒ®дәҢгҒӢгӮүеүҚжқЎгҒҫгҒ§гҒ«е®ҡгӮҒгӮӢж–ҪиЁӯгӮ’йҷӨгҒҸгҖӮпјүгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
еј•з”Ёпјҡe-GOVжі•д»ӨжӨңзҙўгҖҢжҳӯе’ҢдёүеҚҒе…«е№ҙжі•еҫӢ第зҷҫдёүеҚҒдёүеҸ· иҖҒдәәзҰҸзҘүжі•гҖҚВ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒиІ»з”ЁгҒҜе®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘиІ»з”ЁгҒҜгӮұгғјгӮ№гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҠгҒҠгӮҲгҒқгҒ®зӣ®е®үгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
| йЎһеһӢ | еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…йЎҚ |
| гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲдёҖиҲ¬еһӢпјү | 6дёҮеҶҶпҪһ12дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |
| гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲд»Ӣиӯ·еһӢпјү | 6дёҮеҶҶпҪһ20дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |
д»Ӣиӯ·еһӢгҒҜиІ»з”ЁгҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гӮ’еҗ«гӮҖгҒҹгӮҒгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…йЎҚгҒҜж–ҪиЁӯгӮ„иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңҲгҖ…гҒ®иІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҹгҒ„ж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгғЎгғӘгғғгғҲгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘж–ҪиЁӯгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲв‘Ўд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгӮӮе…Ҙеұ…гҒ—з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢ
д»Ӣиӯ·еһӢгҒҜгҖҒеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢдҪҺжүҖеҫ—й«ҳйҪўиҖ…гҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹдҪҸгҒҫгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮи©ІеҪ“гҒҷгӮӢж–ҪиЁӯгҒҜзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гҒ®жҢҮе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®иӘІйЎҢгӮ„е•ҸйЎҢзӮ№гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹиЁҲз”»гӮ’з«ӢжЎҲгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҹәгҒҘгҒҸе…Ҙжөҙгғ»жҺ’жі„гғ»йЈҹдәӢгҒӘгҒ©гҒ®д»Ӣиӯ·гҖҒзҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұгҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгҒӘгҒ©гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгӮӮе…Ҙеұ…гӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
зңӢеҸ–гӮҠгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гӮӮиҰӢйҖғгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз”ҹжҙ»з’°еўғгӮ’еӨүгҒҲгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„ж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгғЎгғӘгғғгғҲгҒ®гҒӮгӮӢйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲв‘ўгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјгҒҢзўәдҝқгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ
и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®иЁӯеӮҷеҸҠгҒійҒӢе–¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжә–гҒ§гҖҒеұ…е®ӨгҒ®е®ҡе“ЎгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еұ…е®ӨгҒ®е®ҡе“ЎгҒҜгҖҒдёҖдәәгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…ҘжүҖиҖ…гҒёгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣдёҠеҝ…иҰҒгҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒдәҢдәәгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
еј•з”Ёпјҡe-GOVжі•д»ӨжӨңзҙўгҖҢе№іжҲҗдәҢеҚҒе№ҙеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒд»Ө第зҷҫдёғеҸ· и»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®иЁӯеӮҷеҸҠгҒійҒӢе–¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжә–гҖҚВ
еұ…е®ӨгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҖӢе®ӨгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјгӮ’зўәдҝқгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеӨ«е©ҰгҒ§е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«2дәәйғЁеұӢгҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒеұ…е®ӨгҒ®еәҠйқўз©ҚгҒҜ21.6гҺЎд»ҘдёҠпјҲ2дәәгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ31.9гҺЎд»ҘдёҠпјүгҒ§гҒҷгҖӮз•іж•°гҒ«жҸӣз®—гҒҷгӮӢгҒЁ13.33з•ід»ҘдёҠ(2дәәгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ19.69з•ід»ҘдёҠ)гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҚҒеҲҶгҒӘеәғгҒ•гӮ’зўәдҝқгҒ§гҒҚгӮӢзӮ№гӮӮйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮ
гғЎгғӘгғғгғҲв‘Јгғ¬гӮҜгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігҒҢиұҠеҜҢгҒ«з”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ
гӮҜгғ©гғ–гғ»гӮөгғјгӮҜгғ«жҙ»еӢ•гӮ„гғ¬гӮҜгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҖҒгӮӨгғҷгғігғҲгҒӘгҒ©гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢзӮ№гӮӮгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®зү№еҫҙгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮеҸӮеҠ гҒҷгӮҢгҒ°д»–гҒ®е…Ҙеұ…иҖ…гҒЁдәӨжөҒгӮ’еӣігӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ1дәәгҒ§жҡ®гӮүгҒ—гҒ„гҒҰгӮӮеҜӮгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгҒ«гҒҸгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиә«дҪ“гӮ’еӢ•гҒӢгҒ—гҒҹгӮҠй ӯгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиә«дҪ“ж©ҹиғҪгӮ„иӘҚзҹҘж©ҹиғҪгҒ®з¶ӯжҢҒгғ»еҗ‘дёҠгҒ«еҪ№з«ӢгҒӨеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҶ…е®№гҒҜгӮұгғјгӮ№гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҪ“ж“ҚгҖҒе°ҶжЈӢгҖҒгӮІгғјгғ гҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҸӮеҠ гӮ’еј·еҲ¶гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲ
е…Ҙеұ…еүҚгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲв‘ е…ұеҗҢз”ҹжҙ»гҒ«йҰҙжҹ“гӮҒгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢ
еҖӢе®ӨгҒ§з”ҹжҙ»гҒ§гҒҚгӮӢгҒҶгҒҲгҖҒз”ҹжҙ»гҒ®иҮӘз”ұеәҰгӮӮй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–№гҒ®дҫЎеҖӨиҰігӮ„жҖ§ж јгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜе…ұеҗҢз”ҹжҙ»гҒ«йҰҙжҹ“гӮҒгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҢдјҡи©ұгҒҢеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒд»–гҒ®е…Ҙеұ…иҖ…гҒЁйЎ”гӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖҚгҖҒгҖҢж°—гҒҫгҒҫгҒ«з”ҹжҙ»гҒ—гҒҹгҒ„гҒҹгӮҒгғ¬гӮҜгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйқўеҖ’гҖҚгҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йҒҺеҺ»гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹиӘҝжҹ»гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®е№іеқҮе№ҙйҪўгҒҜ84.0жӯіпјҲз”·жҖ§81.6жӯігғ»еҘіжҖ§85.0жӯіпјүгҒ§гҒҷгҖӮ[2]иӘҝжҹ»гҒ«гӮҲгӮҠиӢҘе№ІгҒ®е·®гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе№іеқҮе№ҙйҪўгҒҜ80жӯіеүҚеҫҢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮе…Ҙеұ…гҒҷгӮӢж–№гҒ®е№ҙйҪўгҒҢиӢҘгҒ„гҒЁгҖҒжҲёжғ‘гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲв‘ЎйҖҖеҺ»гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢ
еҗҢгҒҳгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдёҖиҲ¬еһӢгҒЁд»Ӣиӯ·еһӢгҒ§гҒҜзү№еҫҙгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬еһӢгҒҜдҪҺжүҖеҫ—й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҸгҒҫгҒ„гҖҒд»Ӣиӯ·еһӢгҒҜиҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹдҪҺжүҖеҫ—й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҸгҒҫгҒ„гҒЁдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дёҖиҲ¬еһӢпјҲеӨ–йғЁгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгҒҜеҸҜиғҪпјүгҒҜгҖҒе…Ҙеұ…гҒ—гҒҰгҒӢгӮүиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁйҖҖеҺ»гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒж–°гҒҹгҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢж–ҪиЁӯгӮ’жҺўгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе…Ҙеұ…гҒ®зӣ®зҡ„гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢйЎһеһӢгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…Ҙеұ…еүҚгҒ«йҖҖеҺ»иҰҒ件гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гғҮгғЎгғӘгғғгғҲв‘ўе…Ҙеұ…гҒҫгҒ§гҒ«жҷӮй–“гӮ’иҰҒгҒҷгӮӢ
з”ігҒ—иҫјгҒҝеҫҢгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«е…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„зӮ№гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҫ…ж©ҹжңҹй–“гҒҜгӮұгғјгӮ№гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒз”ігҒ—иҫјгҒҝгҒӢгӮүе…Ҙеұ…гҒҫгҒ§1е№ҙд»ҘдёҠгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘ж—©гҒҸе…Ҙеұ…гҒ—гҒҹгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®еёҢжңӣгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ§зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҜ”ијғзҡ„е®үдҫЎгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…гҒӘгҒ©гӮ’еҖҷиЈңгҒ«еҠ гҒҲгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№и©ізҙ°
дёҖиҲ¬еһӢгҒЁд»Ӣиӯ·еһӢгҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬еһӢгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗгӮөгғјгғ“гӮ№гҖ‘
- йЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣ
- е…ҘжөҙгҒ®жә–еӮҷ
- жҺғйҷӨгғ»жҙ—жҝҜгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙ
- зӣёи«ҮгҒҠгӮҲгҒіжҸҙеҠ©
- з·ҠжҖҘеҜҫеҝң
ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢе№…еәғгҒ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз”ҹжҙ»дёҠгҒ®еӣ°гӮҠгҒ”гҒЁгӮ’зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮиҒ·е“ЎгҒ«гӮҲгӮӢиҰӢе®ҲгӮҠгӮ„з·ҠжҖҘжҷӮгҒ®еҜҫеҝңгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢзӮ№гӮӮгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гҒ«дёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҹй«ҳйҪўиҖ…гҒҢе®үеҝғгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«й…Қж…®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӨ–йғЁгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·еһӢгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬еһӢгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«еҠ гҒҲзү№е®ҡж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…иҖ…з”ҹжҙ»д»Ӣиӯ·гӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдё»гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗгӮөгғјгғ“гӮ№гҖ‘
- йЈҹдәӢгғ»жҺ’жі„гғ»е…ҘжөҙгҒӘгҒ©ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢд»Ӣиӯ·
- зҷӮйӨҠдёҠгҒ®дё–и©ұ
- гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢж©ҹиғҪиЁ“з·ҙ
д»ҘдёҠгҒ«еҠ гҒҲгҖҒеҢ»зҷӮзҡ„гӮұгӮўгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгӮӮз”ҹжҙ»гӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ§гҒҚгӮӢзӮ№гҒҢйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҜҫеҝңзҠ¶жіҒгҒҜж–ҪиЁӯгҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮи©ізҙ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜе…Ҙеұ…еүҚгҒ«зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒёгҒ®е…Ҙеұ…жқЎд»¶
е…Ҙеұ…жқЎд»¶гӮӮдёҖиҲ¬еһӢгҒЁд»Ӣиӯ·еһӢгҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®е…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖиҲ¬еһӢгҒ®е ҙеҗҲ
д»ҘдёӢгҒ®жқЎд»¶гҒӘгҒ©гӮ’жәҖгҒҹгҒҷж–№гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗжқЎд»¶гҖ‘
- иә«дҪ“ж©ҹиғҪгҒ®дҪҺдёӢгҒӘгҒ©гҒ§иҮӘз«ӢгҒ—гҒҹж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгҒҢгҒӮгӮӢ
- 家ж—ҸгҒ«гӮҲгӮӢжҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„
- 60жӯід»ҘдёҠпјҲеӨ«е©ҰгҒ§е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒҢ60жӯід»ҘдёҠпјү
иҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–№гҒ§гӮӮдёҠиЁҳгҒ®жқЎд»¶гҒ«еҪ“гҒҰгҒҜгҒҫгӮҢгҒ°е…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷпјҲиҰҒж”ҜжҸҙгғ»иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢж–№гӮӮе…Ҙеұ…еҸҜпјүгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжүҖеҫ—еҲ¶йҷҗгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»Ӣиӯ·еһӢгҒ®е ҙеҗҲ
д»Ӣиӯ·еһӢгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘе…Ҙеұ…жқЎд»¶гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗжқЎд»¶гҖ‘
- иә«дҪ“ж©ҹиғҪгҒ®дҪҺдёӢгҒӘгҒ©гҒ§иҮӘз«ӢгҒ—гҒҹж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгҒҢгҒӮгӮӢ
- 家ж—ҸгҒ«гӮҲгӮӢжҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„
- 65жӯід»ҘдёҠ
- иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰ1д»ҘдёҠ
дёҖиҲ¬еһӢгӮҲгӮҠгӮӮжқЎд»¶гҒҜеҺігҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе…Ҙеұ…еҫҢгҒ«иҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгӮӮж–ҪиЁӯгҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·еһӢгӮӮжүҖеҫ—еҲ¶йҷҗгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒёгҒ®е…Ҙеұ…иІ»з”Ё
е…Ҙеұ…гҒ§гҒӢгҒӢгӮӢдё»гҒӘиІ»з”ЁгҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…жҷӮиІ»з”Ё
ж”Ҝжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜгҖҒдҪҸеұ…иІ»гҒ®е…ЁйғЁгҒҫгҒҹгҒҜдёҖйғЁгӮ’еүҚжү•гҒ„гҒҷгӮӢгҖҢеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҖҚгҒЁеұ…дҪҸиІ»гӮ’жҜҺжңҲж”Ҝжү•гҒҶгҖҢжңҲжү•гҒ„ж–№ејҸгҖҚгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜе…Ҙеұ…йҮ‘гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҠгҒҠгӮҲгҒқгҒ®зӣ®е®үгҒҜж•°еҚҒдёҮеҶҶпјҲж•°зҷҫдёҮеҶҶгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҒ§гҒҷгҖӮжңҲжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜе…Ҙеұ…йҮ‘гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒж•·йҮ‘пјҲгҒҫгҒҹгҒҜдҝқиЁјйҮ‘пјүгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж•·йҮ‘гҒҜгҖҒдҪҸеұ…иІ»гӮ’ж”Ҝжү•гҒҲгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгӮ„йҖҖеҺ»жҷӮгҒ®еҺҹзҠ¶еӣһеҫ©гҒ«еӮҷгҒҲгҒҰж–ҪиЁӯгҒ«й җгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҒҠйҮ‘гҒ§гҒҷгҖӮгҒҠгҒҠгӮҲгҒқгҒ®зӣ®е®үгҒҜ0пҪһ30дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҺҹзҠ¶еӣһеҫ©гҒӘгҒ©гҒҢдёҚиҰҒгҒ®е ҙеҗҲгҒҜйҖҖеҺ»жҷӮгҒ«иҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒҜпјҹзӣёе ҙгҒЁе®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢгғқгӮӨгғігғҲ
жңҲйЎҚиІ»з”Ё
еұ…дҪҸиІ»гғ»з”ҹжҙ»иІ»гғ»гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ»гғ»д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ»гҒӘгҒ©гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢжңҲйЎҚиІ»з”ЁгӮӮгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬еһӢгҒ®зӣ®е®үгҒҜ6пҪһ12дёҮеҶҶгҒ§гҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·еһӢгҒҜгӮұгғјгӮ№гҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еұ…дҪҸиІ»
еұ…дҪҸиІ»пјҲеұ…дҪҸгҒ«иҰҒгҒҷгӮӢиІ»з”ЁпјүгҒҜ家иіғгҒЁз®ЎзҗҶиІ»гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…йҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒеұ…дҪҸиІ»гҒҜгҒ“гҒ“гҒӢгӮүж”Ҝжү•гӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж—©жңҹгҒ«йҖҖеҺ»гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒе…Ҙеұ…йҮ‘гҒ®иҝ”еҚҙгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®йҮ‘йЎҚгҒҜе„ҹеҚҙзҺҮгҖҒе„ҹеҚҙжңҹй–“гҒ§еӨүеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
з”ҹжҙ»иІ»
з”ҹжҙ»иІ»гҒҜйЈҹжқҗж–ҷиІ»гҒЁе…ұз”ЁйғЁгҒ®е…үзҶұж°ҙиІ»гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒҢгғЎгӮӨгғігҒ«гҒӘгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮи©ізҙ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜж–ҪиЁӯгҒ§зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ»
е…Ҙеұ…иҖ…гҒ®жүҖеҫ—гҒ®зҠ¶жіҒгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®дәӢжғ…гӮ’еӢҳжЎҲгҒ—гҒҰгҖҒеҫҙеҸҺгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚиІ»з”ЁгҒЁгҒ—гҒҰйғҪйҒ“еәңзңҢзҹҘдәӢгҒҢе®ҡгӮҒгҒҹйЎҚгӮ’гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ»пјҲгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣгҒ«иҰҒгҒҷгӮӢиІ»з”ЁпјүгҒЁгҒ—гҒҰеҫҙеҸҺгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®жүҖеҫ—гҒ®зҠ¶жіҒгӮ’еӢҳжЎҲгҖҚгҒЁиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢйҖҡгӮҠгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®еүҚе№ҙгҒ®жүҖеҫ—гҒ«гӮҲгӮҠеҫҙеҸҺйЎҚгҒҢеӨүеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжүҖеҫ—гҒ«еҝңгҒҳгҒҰеҫҙеҸҺйЎҚгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢзӮ№гҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮеҫҙеҸҺйЎҚгҒ®дҫӢгӮ’жҠңзІӢгҒ—гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ[2]
гҖҗеҫҙеҸҺйЎҚгҖ‘
- еҜҫиұЎеҸҺе…Ҙ150дёҮеҶҶд»ҘдёӢпјҡ1дёҮеҶҶпјҲжңҲйЎҚпјү
- еҜҫиұЎеҸҺе…Ҙ200дёҮ1еҶҶд»ҘдёҠ210дёҮеҶҶд»ҘдёӢпјҡ3дёҮеҶҶпјҲжңҲйЎҚпјү
- еҜҫиұЎеҸҺе…Ҙ250дёҮ1еҶҶд»ҘдёҠ260дёҮеҶҶд»ҘдёӢпјҡ5дёҮ7,000еҶҶ
- еҜҫиұЎеҸҺе…Ҙ300дёҮеҶҶ1еҶҶд»ҘдёҠ310дёҮеҶҶд»ҘдёӢпјҡ9дёҮ3,000еҶҶ
- еҜҫиұЎеҸҺе…Ҙ330дёҮ1еҶҶд»ҘдёҠ340дёҮеҶҶд»ҘдёӢпјҡ11дёҮ7,000еҶҶ
- еҜҫиұЎеҸҺе…Ҙ340дёҮ1еҶҶд»ҘдёҠпјҡе…ЁйЎҚ
иҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҜ’еҶ·ең°еҠ з®—гҒӘгҒ©гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢзӮ№гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ»
д»Ӣиӯ·еһӢгҒҜд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣиІ»гӮӮгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иІ»з”ЁгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жң¬дәәиІ жӢ…еҲҶгҒ§гҒҷгҖӮиІ жӢ…йЎҚгҒҜеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁиҮӘе·ұиІ жӢ…еүІеҗҲгҒ§з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҮӘе·ұиІ жӢ…еүІеҗҲгҒҜгҖҒжүҖеҫ—гҒ«еҝңгҒҳгҒҰпј‘пҪһ3еүІгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲеҺҹеүҮ1еүІпјүгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҖиҲ¬еһӢгӮӮеӨ–йғЁдәӢжҘӯиҖ…гҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢе ҙеҗҲгҒҜеҲҘйҖ”гҒ“гҒ®иІ»з”ЁгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…жүӢз¶ҡгҒҚгҒ®жөҒгӮҢ
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜе…Ҙеұ…гҒ®жөҒгӮҢгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
в‘ иіҮж–ҷи«ӢжұӮ
е…Ҙеұ…жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’йҖІгӮҒгҒҹгҒ„ж–ҪиЁӯгӮ’жҺўгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲжӨңзҙўгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гӮ„ең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®зӘ“еҸЈгҒ§жғ…е ұгӮ’йӣҶгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҹгҒ„ж–ҪиЁӯгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹгӮүгҖҒе…¬ејҸгӮөгӮӨгғҲгӮ„йӣ»и©ұгҒ§иіҮж–ҷгӮ’и«ӢжұӮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
в‘Ўе…Ҙеұ…з”ігҒ—иҫјгҒҝ
е…Ҙеұ…гҒ—гҒҹгҒ„ж–ҪиЁӯгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҹгӮүгҖҒеҲ©з”Ёз”іиҫјжӣёгҒ«еҝ…иҰҒдәӢй …гӮ’иЁҳе…ҘгҒ—гҒҰжҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж–ҪиЁӯйҒёгҒігҒ§жӮ©гӮҖгҒЁгҒҚгҒҜиҰӢеӯҰгӮ„дҪ“йЁ“е…Ҙеұ…гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе®ҹйҡӣгҒ®йӣ°еӣІж°—гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒЁеҖҷиЈңгӮ’зөһгӮҠиҫјгҒҝгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
в‘ўиЁӘе•Ҹгғ»йқўи«Ү
з”ігҒ—иҫјгҒҝжүӢз¶ҡгҒҚеҫҢгҒ«гҖҒж–ҪиЁӯгҒ®иҒ·е“ЎгҒЁйқўи«ҮгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮйқўи«Үе ҙжүҖгҒҜгҖҒж–ҪиЁӯгҒҫгҒҹгҒҜз”іиҫјдәәе®…гҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒҷгҖӮжқҘиЁӘгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҢгҒ°иЁӘе•ҸгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйқўи«ҮгҒ§гҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®еҝғиә«гҒ®зҠ¶жіҒгӮ„е…Ҙеұ…гҒ®ж„ҸжҖқгҒӘгҒ©гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮйӣЈгҒ—гҒ„еҶ…е®№гҒҜиҒһгҒӢгӮҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒж§ӢгҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
в‘Јеҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒ®жҸҗеҮә
еҝ…иҰҒжӣёйЎһгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҰе…Ҙеұ…гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжҸҗеҮәгӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢдё»гҒӘжӣёйЎһгҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗжӣёйЎһгҖ‘
- жүҖеҫ—иЁјжҳҺжӣё
- еҒҘеә·иЁәж–ӯжӣё
- дҪҸж°‘зҘЁ
гҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒ®жғ…е ұгҒЁеҝ…иҰҒжӣёйЎһгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«е…Ҙеұ…еҜ©жҹ»гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷпјҲйқўи«Үгғ»еҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒ®жҸҗеҮәгғ»еҜ©жҹ»гҒ®й Ҷз•ӘгҒҜеүҚеҫҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
в‘Өе…Ҙеұ…
еҜ©жҹ»гҒ«йҖҡгӮҢгҒ°е…Ҙеұ…гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮз©әгҒҚе®ӨгҒҢгҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз©әгҒҚе®ӨгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜеҫ…ж©ҹжңҹй–“гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮй•·жңҹгҒ«еҸҠгҒ¶гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгғ»гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒӢгӮүйҒёжҠһ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгӮ„гҒҷгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒе…Ҙеұ…гҒҫгҒ§жҷӮй–“гӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁйҖҖеҺ»гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·еһӢгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·еәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгӮӮе…Ҙеұ…гӮ’з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№еҫҙгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҖҒе…Ҙеұ…гҒ®зӣ®зҡ„гҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҙеұ…гҒ®жӨңиЁҺгӮ’йҖІгӮҒгҒҹгҒ„ж–№гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҜгҒ„гҒӢгҒҢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҒ§гҒҜгҖҒгӮЁгғӘгӮўгӮ„дәҲз®—гҖҒеҢ»зҷӮгҒЁзңӢиӯ·гҒ®дҪ“еҲ¶гҒӘгҒ©гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжқЎд»¶гҒ§зөһгӮҠиҫјгӮ“гҒ§ж–ҪиЁӯгӮ’гҒҠжҺўгҒ—гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгҒқгҒҶгҒҜиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзөҗеұҖгҒ©гӮҢгҒ«зөһгӮҠиҫјгӮҒгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚ
гҖҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“ж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹвҖҰвҖҰгҖҚ
гҒқгӮ“гҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒзӣёи«Үе“ЎгҒёгҒ®з„Ўж–ҷзӣёи«ҮгӮӮгҒ”жҙ»з”ЁгҒҸгҒ гҒ•гҒ„пјҒ
е№ҙй–“зҙ„6,120件гҒ®зҙ№д»Ӣе®ҹзёҫгҒ®гҒӮгӮӢгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢгҖҒгҒ”еёҢжңӣгҒ«гғ”гғғгӮҝгғӘгҒ®ж–ҪиЁӯгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰз„Ўж–ҷгҒ§гҒ”зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯйҒёгҒігҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒңгҒІгҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬
-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№



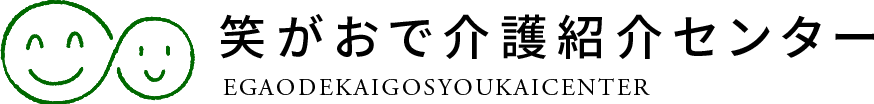




 0120-177-250
0120-177-250