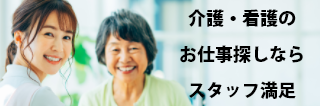介護付有料老人ホームの特徴・入居の条件と費用相場

高齢者施設の多くは、身体への介助や介護といったサービスが付属しており、料金を支払うことで利用できます。介護付有料老人ホームもそのような施設として利用されています。
特別養護老人ホームやサービス付き高齢者住宅のように、高齢者専用の施設はいくつかの種類に分かれており、どの施設を選ぶべきか迷ってしまいますね。
この記事では、介護付有料老人ホームについて、入居条件・費用の内訳・初期償却と返還金・クーリングオフ・支払い方法といった費用にまつわるポイントを紹介します。老人ホームに関して詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護付有料老人ホームとは何か
介護付有料老人ホームは、主に民間企業によって運営される高齢者専用の介護施設です。
24時間介護スタッフが施設内に常勤しており、身体介助・食事・洗濯・入浴・排泄・着替えといったサービスが受けられます。主に民間企業が運営しており、一定の設備、人員、運営基準のもと都道府県の指定(認可)を受けている施設を指します。
高級な施設もあれば低価格が特徴の施設もあり、入居費用の設定はさまざまです。入居要件も施設により異なり、介護度が軽い方から重い方、寝たきりの方、認知症の症状がある方など幅広く受け入れています。
関連記事:老人ホームとは?介護施設との違いや種類・費用などを一覧表で解説
介護付有料老人ホームの入居条件
介護付有料老人ホームは、「介護付き型(介護専用型/介護型)」「住宅型(混合型)」「健康型(自立型)」に分けられます。
健康型(自立型)は、介護が必要ない方のための老人ホームです。施設内で介護サービスが提供されないため、要介護となった場合は介護付き型(介護専用型/介護型)か住宅型(混合型)へ転居しなければなりません。
どの有料老人ホームも原則として65歳以上の高齢者が対象となっており、さらに介護付き型に入居できるのは、以下の条件を満たしている場合に限られます。
【介護付有料老人ホームの入居条件】
- 原則65歳以上の高齢者
- 要介護状態にある方
介護付き有料老人ホームは、65歳以上であり要介護1以上の方が対象となります。要支援では介護サービスの必要がなく条件に該当しないため、住宅型、健康型を検討することになります。
混合型の有料老人ホームでは、自立・要支援の方でも入居できます。住宅型の有料老人ホームは常勤するスタッフが介護を提供せず、清掃や食事といった生活サービスが提供されます。介護が必要な方は、訪問介護を行っている外部のサービスを契約する必要があります。
有料老人ホームの種類と入居条件は以下のとおりです。
| 種類 | 介護付き型 | 住宅型 | 健康型 |
| 年齢 | 65歳以上の高齢者 | 65歳以上の高齢者 | 65歳以上の高齢者 |
| 段階 | 要介護1〜要介護5 | 自立〜要介護5まで(ただし施設によって基準が異なる) | 自立 |
| 認知症の方の入居 | 可 | 可(要問い合わせ) | 不可 |
| 看取り | あり | あり(訪問看護など) | なし |
| 施設の特長 | 介護に特化している | 入居者ごとにサービスが選べる |
余生を楽しめるサービスが充実 |
介護付き型の有料老人ホームは要介護1以上、軽度ではなく中等度以上の方が対象となります。
住宅型は入居者ごとに介護サービスが付帯できるため、自立から要介護5までが対象ですが、施設によって受け入れの基準となる段階に違いがあるため、事前に確認をしておきましょう。
看取りについては、介護付き型や住宅型で対応が可能です。住宅型は外部の介護サービスや医療機関による訪問看護サービスを申し込まなければならないため、事前に確認をとってください。
介護付有料老人ホームの費用
介護付有料老人ホームは、賃貸住宅のように一時金や月額料金が発生します。1回のみ支払うものと、月々支払うもの、必要に応じて支払うものに分かれていますので、それぞれの費用の内容や目安をみていきましょう。
関連記事:有料老人ホーム10種類の特徴や費用を一覧解説!違いや選び方とは
入居一時金
入居一時金とは、施設に支払う初期費用であり賃貸住宅でいう敷金にあたるお金です。前払い金・保証金・入居金などいくつかの名称で呼ばれていますが、内容は敷金と同じです。
入居一時金は0円〜数千万円以上まで幅がありますが、月額利用料と違って返還される可能性もあります。まず施設側が受け取り、入居期間に応じて償却しながら、入居者が退去する際に未償却残高を返還します。
入居一時金の支払い方には、いくつかの種類があります。一括払いにして月額費用を少額に抑えられる方法のほか、入居一時金を少額にして月額費用が増える方法、入居一時金が無料になる代わりに月額費用が高くなる方法があります。
月額利用料
月額利用料は、介護付有料老人ホームを利用するための料金です。
施設の設備・規模・サービス・立地条件といった点で相場が異なり、基本的に新築で設備やサービスが充実し、看護師が常駐しているなどの行き届いた老人ホームほど月額利用料も割高になっていきます。10万円台から利用できる施設もあれば、30万円を超える高額な施設もあります。
料金プランは入居一時金とのバランスによって複数のパターンがあり、入居一時金を支払うと月額利用料は安くなる傾向にあります。生活保護を受給していても入居できる介護付有料老人ホームもあります。
居住費
居住費は家賃に当たる費用で、月額利用料の中に含まれる項目です。後から紹介する「全額前払い型」「一部前払い型」「月払い型」の支払い方法が存在します。純粋に家賃のみの費用で、食費や介護サービス費などは含まれません。
介護付有料老人ホームの場合、運営者が民間企業になりやすいという特性上、老人ホームの居住費は施設の立地・アクセス性・設備・居室のタイプ(グレード)といった点で違いがあります。
公的施設では居住費が大きく差別化される心配はありませんが、民間で運営されている施設では、グレードの高い施設ほど費用が高くなります。
家賃など、必要な費用が支払えないと別の施設への転居が必要になります。賃貸物件と同じく猶予期間の後に退去となるほか、身元保証人にも連絡されるため、早めに施設スタッフや責任者への相談が必要です。
管理費
管理費(管理費用)は、共用部の維持管理や設備費、メンテナンス料金、事務費用、人件費といった項目が含まれています。
介護付有料老人ホームでは生活支援サービスを利用者に提供していますが、それらにかかる諸経費を管理費として徴収するものです。施設で提供しているサービス、スタッフの数などによって管理費が異なるため、事前に内容と費用を確認し、料金の内容を比較してください。
食費
食費は、介護付有料老人ホームで食事のサービスを利用するために支払う費用です。食材の調達にかかる費用のほかにも、厨房での人件費や維持費が含まれています。
施設ではすべての利用者が必ず3食を食べるわけではないため、それぞれの利用者ごとに食事の回数に応じて費用がかかります。月額利用料となるケースが多い一方、すべての利用者が毎月一定額を支払うタイプの施設もあります。
また、食事以外におやつ(軽食)が含まれる場合もあり、予約制で食事を用意する施設もみられます。おやつや間食など食費の項目に含まれる内容を確認し、メニューが選択できるか・療養食などに対応しているかといった点も確認しましょう。
水道光熱費
水道光熱費は賃貸住宅と同じく、水道・光熱にかかる費用です。トイレや浴室の利用、部屋の照明や家電製品を利用する場合、この項目が必ず加算されます。
施設によっては水道光熱費として分けられず、管理費に組み込まれているケースもあります。また、介護付有料老人ホームでは賃貸住宅のように一人ひとりの使用量に応じた請求ではなく、固定費のように一定額を請求するシステムが多くみられます。
居室にメーターが設置されているケースでは使用量に応じた請求となりますが、想定される使用量を決めるケースでは一定額の請求となります。
医療費
医療費は、有料老人ホームに入居する方が病院や医学的ケアにかかった際に、医療保険を使って自己負担で支払う料金です。
有料老人ホームの多くは地域の医療機関と連携しており、医師と看護師による往診・訪問歯科・健康チェック・診断・アドバイスなどを実施しています。
既往症をお持ちの方は、病院介護とは別に医薬品にかかる費用も支払う必要があります。また、ケガ・病気で新たに病院を受診したときにも医療費がかかります。
医療費の詳細については、申し込みを行う介護付有料老人ホームの規定やサービスの一覧表に記載されていますので、入居前に必ず確認をしてください。
介護サービス費
介護サービス費(介護費)は、食事・入浴・排泄・生活相談といった介助・介護を受けるための費用です。介護サービスを受ける方には介護保険が適用され、サービス費の全額の1〜3割(所得によって変わる)を負担します。
有料老人ホームではそれぞれの利用者ごとに設定したケアプランに基づいて、居宅サービスをスタッフが提供しています。介護サービス費はそのサービスに対しての代金という位置づけです。
介護の中には療養上のケア、機能訓練(リハビリテーション)といった項目も含まれます。サービスにかかる消耗品(おむつ・トイレットペーパーなど)や日用品(タオル・歯ブラシ・ティッシュペーパーなど)については含まれず、日用品費(生活費)などとして別途請求されます。
介護付有料老人ホームでは看取りが行われますが、施設によっては提供していない場合があるため、確認のうえ入居を検討してください。
「サービス加算」という名目で、介護サービス費に加えて発生する費用にも注意が必要です。介護保険の中から施設側に支払われる費用です。サービス内容や事業体制によって加算割合が異なります。
施設によっては介護保険の対象外である、目的地までの送迎や外出時の付き添い、理美容師の施術といった自費で利用できるサービスも用意されています。具体的には以下の通りです。
【介護保険の対象外となるサービス費用】
- 外出時の付き添い(介助)
- 書類の記入・整理の手伝い
- 理美容師によるサービス
- 目的地への移送や送迎
- 宅食など
これらのサービスは必須ではありませんが、生活において必要となる場合があります。どの項目にいくらかかるのかを試算しておくと安心です。
関連記事:老人ホームの入居にかかる費用は?相場と安く抑えるポイント
初期償却と返還金
入居一時金は賃貸住宅でいう敷金の意味があり、有料老人ホームでは入居してから一定の割合で償却されていきます。この仕組みを「初期償却」と呼び、割合はホームごとに異なります。割合が高いほど手元に帰ってくるお金が少なくなるため、入居前に確認してください。
入居一時金が500万、初期償却の割合が20%、償却期間が5年の有料老人ホームなら、100万円は初期償却で手元には残らないことになります。500万から100万を引いた400万が5年で毎月償却されていきます。
上記の例では、償却期間である5年のうちに退去した場合、未償却の分が返還金として戻ります。しかし5年を過ぎてしまうと償却済みとなるため、返還金は0円になります。
入居一時金が500万、初期償却がなく「均等償却」が毎月発生する、償却期間が5年の有料老人ホームでは、500万を5年(60ヶ月)で割り、1ヶ月あたり5万円が償却される計算になります。
有料老人ホームに入居する期間が短い場合は、償却期間や初期償却の割合を必ず確認しましょう。
クーリングオフとは
入居にかかる費用を支払ったにも関わらず、入院やその他の理由で入居後すぐに退去した場合は、「クーリングオフ(短期解約特例制度)」が利用できます。
クーリングオフ制度は、訪問販売や通信販売で購入した商品をキャンセルするための制度として広く知られていますが、かつて老人ホームへの短期入居で支払ったお金が戻ってこないといった問題が相次いだため、改正老人福祉法によって新たにクーリングオフの対象となりました。
クーリングオフ制度は、契約を締結してから所定の期間内であれば、無条件に契約を解除できるというものです。連鎖販売取引は20日以内、訪問販売は8日以内と解除可能な期間は限られていますが、消費者の正しい購買活動を保護するための制度であり、老人ホームへの入居についても同様です。
老人ホームの契約では、契約した日から90日以内に退去した際に、前払いをしたお金を全額返金してもらえます。ただしクーリングオフを申請しなければ前払い金は戻らないため、忘れずに申請するようにしましょう。
介護付有料老人ホームの支払い方法
介護付有料老人ホームでは、敷金に当たる入居一時金について、3種類の支払い方法があります。入居一時金の支払い方によって、月々にかかる費用が変わる点に注意しましょう。
全額前払い型(一時金型)
全額前払い型とは、入居時に家賃の全額を支払う方式です。入居の際に家賃をすべて支払ってしまうので、固定費の一つである家賃の支払いが不要になり、月々の食費や管理費の支払いのみとなります。
ただし、入居する方の多くはどの程度老人ホームに入居しているのか予想できないため、入居期間をあらかじめ想定し、その期間の家賃を支払うことになります。基本的に終身での入居を想定するため、数ヶ月や2,3年程度といった細かい期間ではなく、まとめての期間を指定します。
全額前払いの中に含まれていない費用については月額料金として支払っていきます。あくまでも全額前払いに含まれるものは終身で入居する分の家賃になります。
一部前払い型(一部月払い型)
一部前払い型は、入居にかかる費用の一部を前払いにして、残りは一括または月々に分割して支払っていく方式です。
一部前払い型は、「全額前払い型では持ち出しが多くなり手持ちが少なくなってしまう、一方で月払い型も月々の負担が大きくなってしまい負担がかかる」といった場合に、両者の間をとって負担を軽減できる方法です。
あらかじめ入居期間を想定して、その期間に応じた金額を支払います。一部を入居のときに前払いし、残った分は毎月支払い続けます。このとき前払いする金額は、ご本人が支払える金額で設定されるため、無理のない前払いが可能です。
月払い型
月払い型は、入居一時金を最初に支払わず毎月家賃が徴収される方式です。入居一時金を事前に支払わないぶん、月々の家賃が全額前払い型や一部前払い型よりも高くなります。
費用を抑えるために利用できる制度
有料老人ホームは入居一時金・月額利用料を含めて高額になりやすく、費用を少しでも抑えるためにいくつかの制度が利用できます。「高額介護サービス費制度」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」について、それぞれの内容を確認しましょう。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、介護保険の自己負担額が上限を超えたとき、超過分を国や市町村が負担する制度です。
所得に応じて1〜3割の自己負担割合が決められており、その割合を超えて負担が発生し限度額の上限を超えた場合は、居住している市区町村に申請することで「高額介護サービス費」という名目で還付が受けられます。
令和3年(2021年)8月からは新たに高所得者に対して負担限度額の見直しが行われ、課税所得380万円〜690万円と690万円以上の2枠が新設されました。
厚生労働省によると一般的な所得者の負担限度額は月額44,000円ですが、この枠組みに当てはまる方については、負担の上限額が月額(世帯)93,000円以上になります。
| 年収 | 負担上限月額 |
| 約1,160万円~ | 140,100円(世帯) |
| 約770万~約1,160万円 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税~約770万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護サービス費をどちらも支払っている方が、1年間(毎年8月1日〜翌年の7月31日まで)に限度額の上限を著しく超えたときに、負担した金額の一部が払い戻される制度です(ショートステイを含む施設への入所中の食費・居住費・生活費などの利用料は含まれません)。
具体的には、医療機関や介護サービス事業者に自己負担限度額を超えて支払ったとき、差額分を2種類の方法で支給される制度です。介護保険の分は「高額医療合算介護サービス費」として支給され、医療保険の分は「高額介護合算療養費」として支給されます。
一例として、医療保険を1割負担する70歳の方(自己負担限度額は57,600円)が100万円の医療費がかかる治療を受けたとき、窓口では10万円の負担になります。しかし自己負担限度額が57,600円のため、窓口で負担した10万円のうち限度額を差し引いた42,200円は高額介護合算療養費となって手元に戻ります。
世代間での公平性、負担能力に応じた負担といった観点から、本制度の限度額は所得や年齢に鑑みて設定されています。2018年8月には、新たに70歳以上の方の高額療養費制度の見直しが行われ、以下のような自己負担限度額が設定されました。
| 年収 | 70歳以上 | 70歳未満 |
| 約1,160万円~ | 212万円 | 212万円 |
| 約770万~約1,160万円 | 141万円 | 141万円 |
| 約370万~約770万円 | 67万円 | 67万円 |
| 約156万~約370万円 | 56万円 | 60万円 |
| 市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 34万円 |
| 市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下の方) |
19万円 | 34万円 |
上記の表では、現役並みの所得を得ている方は年収に応じて細分化し、限度額を引き上げています。代わりに一般区分や非課税世帯の方の限度額は据え置きとなっています。
また、療養のために病院などに入院したときは、食費やベッド代などを自己負担しなければなりません。そこで、月額に換算した場合は以下のようになります。
| 世帯の年収 | 外来(個人ごと) | 1か月の上限額(世帯ごと) | |
| 現役並みの所得者 | 約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1%<多数回140,100円※>(1か月の上限額(世帯ごと)を含む) | |
| 現役並みの所得者 | 約770万~約1,160万円 | 167,400+(医療費-558,000)×1%<多数回93,000円※>(1か月の上限額(世帯ごと)を含む) | |
| 現役並みの所得者 | 約370万~約770万円 | 80,100+(医療費-267,000)×1%<多数回44,400円※>(1か月の上限額(世帯ごと)を含む) | |
| 一般の方 |
約156万~約370万円・標報26万円以下 課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 <多数回44,400円※> |
| 低所得者 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者 |
住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下などを含む) |
8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上上限額に達すると、4回目からは「多数回」の該当となり上限額が下がる
本制度を利用するためには、費用の支給対象となるかを確認しなければなりません。介護保険者である、お住まいの地域の市区町村へ申請を行い、受理されると介護自己負担額証明書が送付されます。この証明書を添付し、申請書とともに医療保険者に申請します。
費用を抑えるために利用できる所得控除
介護付有料老人ホームの費用を抑える際に利用できる所得控除には「扶養控除」と「障害者控除」が挙げられます。それぞれの控除の特長について確認していきましょう。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に所得税の控除対象となる扶養親族がいる場合に、一定金額の所得控除が受けられるという制度です。納税者と生計を同じにする配偶者以外の親族で、その方が年収103万円以下の場合に該当します。
介護付有料老人ホームの利用者に仕送りをしながら遠距離介護を行うなど、扶養控除の対象者に該当しており、その方が70歳以上の場合は「老人扶養親族」として控除が受けられます。
控除額は、対象となる方が配偶者なのか、扶養親族なのかによって分けられます。さらに配偶者では一般(70歳以下)または老人(70歳以上)かで分けられ、親族については一般・特定・老人の3区分が設けられています。
| 区分 | 控除額 |
| 一般の扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 63万円 |
|
老人扶養親族 (同居老親等以外の者) |
48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
※特定扶養親族は19〜23歳の方を指すため、有料老人ホームを利用する方は対象外となります。
障害者控除
障害者控除は、納税者と生計を同じにする配偶者または親族が、所属税法上の障害者に該当する場合は一定金額の所得控除が受けられる制度です。 障害者・特別障害者・同居特別障害者の3区分に分けられ、控除金額は以下の通りです。
| 区分 | 控除額 |
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
介護付有料老人ホーム以外の施設
介護付有料老人ホーム以外にも、高齢者を受け入れている施設があります。ここでは「特別養護老人ホーム」「ケアハウス」「介護医療院」「介護老人保健施設」「グループホーム」の特徴と費用についてみていきましょう。
施設①特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な高齢者に対して介護を提供する施設です。
終身での入居が可能であり、食事・歩行・起き上がり・入浴・排泄・健康管理といったさまざまなケアを介護というかたちで提供します。費用については入居一時金が不要で、要介護度によって月額料金が異なりますが、月々の支払いを続けていれば終身での入居が可能です。
要介護3以上という条件があるため、要介護2以下では入居ができません。一方で民間企業の運営ではないため、倒産や退去のリスクが少ない点がメリットです。
関連記事:特別養護老人ホームの費用相場は?入居できない場合の3つの対処法
施設②ケアハウス
ケアハウスは、自宅での自立した生活が困難な60歳以上の方に提供される介護サービス付きの施設です。「軽費老人ホームC型」と呼ばれる安価型老人ホームの一種で、都市型・軽費老人ホームA・B型を含めて4種類に分かれています。
家族からの援助が受けられず金銭的に困窮する方の場合、一般(自立)型と呼ばれるケアハウスに60歳から入所が認められます。要介護度1以上となり、65歳以上で家庭での生活が困難な場合は、介護型と呼ばれるケアハウスが用意されています。
いわゆる高級老人ホームとは異なり、生活支援を安価に受けられるという特長があります。時間的な制約は少なく、外出も基本的には可能で自由に過ごせます。介護付有料老人ホームとは、入居一時金がない・家賃や管理費が安いという点で違いがあります。
施設③介護医療院
介護医療院は、医師の配置が義務付けられており要介護状態にある高齢者が長期的に療養を行います。介護サービスが必要でありながら、医学的管理・看護やターミナルケア、看取りが必要な方が入所する施設です。
一般的な介護施設では医療従事者が常駐しているわけではないため、慢性期の医療ニーズを抱える方のために設置されています。
介護医療院は2018年に法定化された施設のため、まだ数が多いとはいえない状況です。しかし今後、高齢化社会が進むにつれて介護を受ける人や高齢者の医療ニーズも高まっていくと考えられ、数が増えていくと予想されています。
要介護1〜5で、医学的管理や長期療養が必要とされた方が入所します。公的施設のため入居一時金は発生しません。利用者の要介護度、自己負担額などに応じて月額料金が10万円以下から20万円以上まで異なります。
施設④介護老人保健施設
介護老人保健施設は「老健」「老健施設」とも呼ばれ、要介護の方が自宅に復帰できるようにサービスを提供する施設です。
介護医療院と同じく、介護保険が適用される公的施設であり、リハビリテーションや医学的ケアを行います。終身の入居ではなく、原則的に3ヶ月の入居を終えた後は在宅での介護に切り替わります。
特別養護老人ホームが終身であるのに対して、介護老人保健施設は数ヶ月のみの滞在期間となり、施設への入所(またはショートステイ)以外では自宅から通う形式の通所、施設のスタッフが自宅へやってくる訪問形式もとられています。
公的施設のため入居一時金が発生せず、月額利用料も10万円以下からと比較的利用しやすい価格帯です。
施設⑤グループホーム
グループホームは、認知症の認定を受けている65歳以上で要支援2以上の方を対象とした共同住宅です。
ユニット型と呼ばれる、5〜9名程度の利用者を1ユニットとした施設が多く、施設全体では最大でも2ユニットまでの入居と決められているため、小規模でアットホームな雰囲気が特徴的です。
近年では一人暮らしが可能なサテライト型も登場していますが、基本的には支援員と呼ばれるスタッフのサポートを受けながら、認知症の方同士で理解を深めながら自立した生活を送ることが目的です。
民間企業の運営が多く、入居一時金(ない場合もあります)と月額利用料がそれぞれかかるほか、介護サービスを受ける際にはその費用も加算されます。
ただし家賃(居住費・賃料)が5万円程度と比較的安く、入居一時金がかからない施設も多いため、比較的利用しやすい施設といえるでしょう。
関連記事:認知症向けの老人ホームは?施設に入れるタイミングや選び方を解説
介護付有料老人ホームに関するQ&A
次に、介護付有料老人ホームに関するQ&Aをみていきましょう。医療費控除の対象となるのか、入居一時金は必要なのかといった疑問をまとめました。
医療費控除の対象?
現役世代でも適用可能な医療費控除は、1年間のうちに基準額以上の医療費を超えて支払ったとき、確定申告を行うと超過分が控除対象となる制度です。
医療費控除の対象には、病院での診察・治療費のほかに通院にかかった交通費や入院中の食事代も含まれます。サプリメントや漢方薬、予防注射といった対象外になる項目も多いため、間違えて申告しないように注意が必要です。
介護付有料老人ホームでは、医療機関を受診した際にかかった交通費、介護サービス費の一部などが特定の条件を満たした際に対象となります。居住費や管理費、水道光熱費などは対象外となります。
前年度の所得額が80万円以下の場合、月額の医療費の上限が15,000円までとなり、それ以上かかっても費用を負担する必要がありません。
入居一時金は絶対に必要?
入居一時金は数百万円以上にのぼる場合もあり、高額になると支払いが難しく入居を諦めざるを得ないケースも発生します。
入居にかかるお金を少しでも減らしたい場合は、各種控除制度や高額介護サービス費制度などを利用するか、入居一時金が不要な施設を検討しましょう。
「軽費老人ホーム」と呼ばれる種類の老人ホームは、一般的な介護付有料老人ホームよりも費用を安く抑えられます。
生活保護を受けていても入居できる?
生活保護を受給している方でも、予算に合う施設であれば入居することが可能です。
ただし施設によって設備、居室の状況、受け入れ体制などが異なるため、施設を探したうえで入居の相談を行ってみてください。
生活保護を受けている方は、お金の使い方で特に注意が必要です。介護サービス費は高額にならなくても、生活費や食費といった面では支給された金額の中からまかなう必要が出てくるため、予算に見合わなければ支払いが不可能となり、退去になってしまうおそれがあります。
まずは施設を探して問い合わせを行うか、生活保護受給者を担当しているケースワーカーへ相談するなどして、予算に見合う施設の確認や相談を行いましょう。
年金のみで費用をまかなえる?
有料老人ホームは民間企業が運営しているものも多く、年金のみでは費用がまかなえるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
軽費老人ホームのように他の施設よりも費用がかからない老人ホームであれば入居が検討できますが、それでも不安な場合は給付される年金額を確認し、安い施設を取り上げて複数箇所を比較してください。
年金だけではまかなえず、貯蓄の持ち出しになってしまう場合でも、入居期間に応じてしっかりと収支のバランスをとっていく必要があります。不明点や疑問点はお近くのケースワーカーへご相談ください。
関連記事:働きながら入れる老人ホームはある?施設探しの注意点を徹底解説
地域の施設と料金体系を比較する
今回は、介護付有料老人ホームの入居条件や費用の内訳、他の施設との違いや支払い費用を抑えるために活用できる制度について紹介しました。
高齢者施設にはさまざまな種類があり、年齢や認知症の有無によって入居できる環境が異なります。費用に余裕はないが、入居を検討したいという方はケースワーカーへ直接ご相談ください。
ご自身で調べられる場合も、まずは身近な場所にどのような施設があるか確認のうえ、1ヶ月にかかる月額利用料と入居一時金、さらに施設ごとのサービスや受け入れている入居者の詳細をチェックし、比較することをおすすめします。
笑がおで介護紹介センターでは、エリアや予算、医療と看護の体制などさまざまな条件で絞り込んで施設をお探しいただけます。
「そうは言っても、結局どれに絞り込めばいいのかわからない」
「たくさん施設があって、わからなくなってきた……」
そんな場合は、相談員への無料相談もご活用ください!
年間約6,120件の紹介実績のあるスタッフが、ご希望にピッタリの施設をすべて無料でご紹介いたします。
介護施設選びのパートナーとして、私たちにぜひご相談ください。

監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
この記事の関連記事



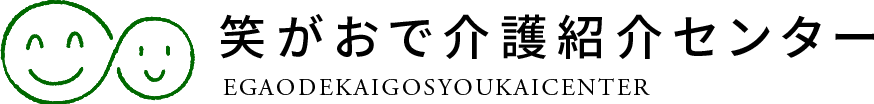




 0120-177-250
0120-177-250



とシニア向け分譲マンションの違い.webp)