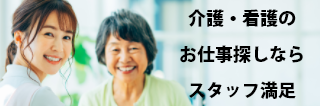иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгҖҢе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҖҚгҒ®жҰӮиҰҒгҒЁиІ»з”ЁгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„ж–№жі•

иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁгҒҜгҖҒй«ҳйҪўиҖ…пјҲиҖҒдәәпјүгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹдҪҸе®…гӮ„ж–ҪиЁӯгҒ®з·Ҹз§°гҒ§гҒҷгҖӮ
60гҖң65жӯігӮ’иҝҺгҒҲгҒҹж–№гҒҢдё»гҒӘеҜҫиұЎиҖ…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж–ҪиЁӯгҒ”гҒЁгҒ«и©ізҙ°гҒӘжқЎд»¶гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиҮӘиә«гҒ«еҗҲгҒЈгҒҹж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒ¶еҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҗҢгҒҳиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§гӮӮжҖ§ж јгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ»гҒӢгҖҒгҖҢе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҖҚгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гҒ«е·®гҒҢеҮәгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®жҰӮиҰҒгҒЁдё»гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒе…Ҙеұ…гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгӮ„иІ»з”ЁгҒ®еҶ…иЁігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒЁгҒҚгҒ®иІ жӢ…гӮ„гҖҒе…Ҙеұ…иІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢж–№жі•гӮӮзҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒңгҒІеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®жҰӮиҰҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәжі•гҒ«гӮӮгҒЁгҒҘгҒ„гҒҰйҒӢе–¶гҒ•гӮҢгӮӢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒЁгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ®й«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјүгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜгҖҢзү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҒҢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«и©ІеҪ“гҒ—гҖҒй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјүгҒ§гҒҜгҖҢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҖҢйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҖҢгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјүгҖҚгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗй«ҳйҪўиҖ…ж–ҪиЁӯгҒ®еҲҶйЎһгҖ‘
| еҲҶйЎһ | д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯ | й«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјү |
| еҗҚз§° |
|
|
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәжі•гҒ«гӮӮгҒЁгҒҘгҒ„гҒҰйҒӢе–¶гҒ•гӮҢгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҷгҖӮй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒӘгҒ©гҒҢйҒӢе–¶гҒҷгӮӢе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒЁгҖҒж°‘й–“гҒ®жі•дәәгӮ„еӣЈдҪ“гҒҢйҒӢе–¶гҒҷгӮӢж°‘й–“ж–ҪиЁӯгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®дёӯгҒ§гҖҢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜгҖҢзү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҒҢи©ІеҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒҜгҖҢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҖҢйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҖҚгҖҢгӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјүгҖҚгҒ®3ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҷгҖӮ
вҖ»д»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўгҒҜ2024е№ҙ3жңҲгҒҫгҒ§гҖҢд»Ӣиӯ·зҷӮйӨҠеһӢеҢ»зҷӮж–ҪиЁӯгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚз§°гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ2024е№ҙ3жңҲжң«гҒ§гҒ®е®Ңе…Ёе»ғжӯўгҒ«дјҙгҒ„гҖҒй•·жңҹгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰзҷӮйӨҠгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гҖҢд»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўгҖҚгҒҢйҒӢе–¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®зү№еҫҙгҖ‘
| ж–ҪиЁӯ | зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ | гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№ |
| еҹәжң¬зҡ„жҖ§ж ј | иҰҒд»Ӣиӯ·й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®з”ҹжҙ»ж–ҪиЁӯ | й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҸеұ… | з’°еўғзҡ„гғ»зөҢжёҲзҡ„гҒ«еӣ°зӘ®гҒ—гҒҹй«ҳйҪўиҖ…гҒ®е…Ҙеұ…ж–ҪиЁӯ | дҪҺжүҖеҫ—й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҸеұ… |
| ж–ҪиЁӯгҒ®е®ҡзҫ© | еёёжҷӮгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гӮ’йӨҠиӯ·гҒҷгӮӢ | й«ҳйҪўиҖ…гҒ«д»Ӣиӯ·гғ»йЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгғ»е®¶дәӢгғ»еҒҘеә·з®ЎзҗҶгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢ | й«ҳйҪўиҖ…гӮ’йӨҠиӯ·гҒ—гҖҒиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гӮ„зӨҫдјҡзҡ„жҙ»еӢ•гҒёгҒ®еҸӮеҠ гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжҢҮе°Һгғ»иЁ“з·ҙгғ»жҸҙеҠ©гӮ’иЎҢгҒҶ | з„Ўж–ҷгҒҫгҒҹгҒҜдҪҺйЎҚж–ҷйҮ‘гҒ§й«ҳйҪўиҖ…гҒ«йЈҹдәӢгҒ®жҸҗдҫӣгғ»гҒқгҒ®д»–гҒ®дҫҝе®ңгӮ’дҫӣдёҺгҒҷгӮӢ |
| ж–ҪиЁӯгҒ®иЁӯзҪ®дё»дҪ“ |
ең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“ зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәә |
йҷҗе®ҡгҒӘгҒ— |
ең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“ зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәә |
ең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“ зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәә зҹҘдәӢиӘҚеҸҜгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжі•дәә |
| еҜҫиұЎиҖ… | 65жӯід»ҘдёҠгҒ§иҰҒд»Ӣиӯ·3д»ҘдёҠгҒ®ж–№ | й«ҳйҪўиҖ…вҖ» | 65жӯід»ҘдёҠгҒ§з’°еўғгҒҠгӮҲгҒізөҢжёҲзҡ„зҗҶз”ұгҒ«гӮҲгӮҠиҮӘе®…гҒ§йӨҠиӯ·гҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„дәә | 60жӯід»ҘдёҠгҒ§е®¶ж—ҸгҒӢгӮүгҒ®жҸҙеҠ©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҡиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»гҒ«дёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгӮӢдәә |
вҖ»гҖҢй«ҳйҪўиҖ…гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®ж №жӢ жі•гғ»иҖҒдәәзҰҸзҘүжі•гҒ§гҒҜй«ҳйҪўиҖ…гҒ®е®ҡзҫ©гҒҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒзӨҫдјҡйҖҡеҝөдёҠгҒ®гҖҢиҖҒдәәгҖҚгҒ®ж–№гҒҢеҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢдё»гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢдё»гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒиЎЈйЈҹдҪҸгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮӢгӮөгғқгғјгғҲгӮ„гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҖҒеҫҖиЁәгғ»еҒҘеә·зӣёи«Үгғ»гҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§гҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҖ‘
| ж–ҪиЁӯ | д»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | дҪҸе®…еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ | еҒҘеә·еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ |
| гӮөгғјгғ“гӮ№ |
|
|
|
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгҒЁгҒҜгҖҒжҙ—жҝҜгғ»жҺғйҷӨгғ»иҰӢе®ҲгӮҠгғ»зӣёи«Үгғ»иІ·гҒ„зү©д»ЈиЎҢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз”ҹжҙ»гӮөгғјгғ“гӮ№е…ЁиҲ¬гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒиІ·гҒ„зү©гҒ®д»ЈиЎҢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢд»ҳеёҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж–ҪиЁӯгҒ”гҒЁгҒ«зўәиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
дёҠиЁҳгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜдёҖдҫӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢд»ҳеёҜгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҪҸе®…еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·иҖ…гҒҢе…Ҙеұ…еҸҜиғҪгҒӘж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜеӨ–йғЁгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸҚеҜҫгҒ«гҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·иҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҒҘеә·еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйҖҖеұ…гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«е…Ҙеұ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§гҒҜгҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№гҒ«гҒҜд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢгҖҒиҮӘз«ӢиҖ…гӮ„иҮӘз«ӢгҒ«иҝ‘гҒ„ж–№гҒҜгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ„гғ¬гӮҜгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©гҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гӮ’гҒ“гҒӘгҒ—гҒҰгҖҒеҒҘеә·зҡ„гҒӘз”ҹжҙ»гҒҢз¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒҜж°‘й–“ж–ҪиЁӯгӮҲгӮҠгӮӮиІ»з”ЁгҒҢе®үгҒҸгҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒ«дёҚе®үгҒҢгҒӮгӮӢж–№гҒ«гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮж°‘й–“ж–ҪиЁӯгҒҜиЎҢгҒҚеұҠгҒ„гҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒ«еҠ гҒҲгҖҒиЁӯеӮҷгӮ„еҚҒеҲҶгҒӘз”ҹжҙ»з’°еўғгҒҢж•ҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒжәҖи¶іеәҰгҒ®й«ҳгҒ•гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜ24жҷӮй–“дҪ“еҲ¶гҒ§гҒ®иҰӢе®ҲгӮҠгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ§гӮӮз”ҹжҙ»зӣёи«ҮгӮ„ж—ҘдёӯгҒ®иҰӢе®ҲгӮҠгҒҢд»ҳеёҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҒҘеә·дёҠгҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°йҡҸжҷӮзӣёи«ҮгҒ®гҒҶгҒҲгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®зҙ№д»ӢгӮ„йҖҒиҝҺгҖҒеҫҖиЁәпјҲиЁӘе•ҸзңӢиӯ·пјүгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҖдәәгҒ§з”ҹжҙ»гҒҷгӮӢд»ҘдёҠгҒ®е®үеҝғж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гҒҜгҒ©гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ«гӮӮе…ұйҖҡгҒҷгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒёгҒ®е…Ҙеұ…иІ»з”ЁгҒ®зӣ®е®үгҒЁеҶ…иЁі
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒҜгҖҒжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гғ»ж•·йҮ‘гғ»дҝқиЁјйҮ‘гҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҖҒе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒЁдҝқиЁјйҮ‘гӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…¬е…ұж–ҪиЁӯгҒҜең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒӘгҒ©гҒҢйҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ 4ж–ҪиЁӯгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиІ»з”ЁгҒ®зӣ®е®үгҒЁеҶ…иЁігӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҲқжңҹиІ»з”Ё
еҲқжңҹиІ»з”ЁгҒҜгҖҒжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®дёҖйғЁгӮ’еүҚгӮӮгҒЈгҒҰж”Ҝжү•гҒҶгҖҢе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҖҚгҒЁгҖҒйғЁеұӢгӮ„е…ұжңүйғЁгӮ’иіғиІёгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«ж”Ҝжү•гҒҶж•·йҮ‘гӮ„дҝқиЁјйҮ‘гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜзөӮиә«гҒ§е…Ҙеұ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҲҶиӯІгғһгғігӮ·гғ§гғігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иіје…ҘгҒҷгӮӢеҪўејҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиіғиІёзү©д»¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж•·йҮ‘гӮ„дҝқиЁјйҮ‘гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҖ‘
- зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡгҒӘгҒ—
- д»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯпјҡгҒӘгҒ—
- д»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўпјҡгҒӘгҒ—
зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜе…¬е…ұж–ҪиЁӯгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁеҗҢгҒҳе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒ§гҒӮгӮӢд»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯгӮ„д»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўгҒ«гӮӮеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒҜзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҗй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјүгҖ‘
- еҒҘеә·еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ0пҪһж•°е„„еҶҶ
- д»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ0пҪһж•°еҚғдёҮеҶҶ
- дҪҸе®…еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ0пҪһж•°еҚғдёҮеҶҶ
- йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ0еҶҶ
- гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҡ0гҖң30дёҮеҶҶ
- гӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ пјҡ0гҖңж•°зҷҫдёҮеҶҶ
й«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒҜгҖҒе…¬е…ұж–ҪиЁӯгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢиІ»з”ЁгҒҜгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҸҚеҜҫгҒ«гҖҒж°‘й–“ж–ҪиЁӯгҒҜеҒҘеә·еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒҢж•°е„„еҶҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒҡжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж–ҪиЁӯгҒ”гҒЁгҒ®ж–ҷйҮ‘дҪ“зі»гҒЁж”Ҝжү•гҒ„ж–№жі•гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
жңҲйЎҚиІ»з”Ё
жңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гӮ’иіғиІёдҪҸе®…гҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«еҖҹгӮҠгҒҰдҪҸгӮҖгҒҹгӮҒгҒ®иІ»з”ЁгҒ§гҒҷгҖӮжҜҺжңҲгҒ®ж–ҷйҮ‘гҒ«гҒҜж¬ЎгҒ®ж–ҷйҮ‘гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®еҶ…иЁігҖ‘
- иіғж–ҷ
- з®ЎзҗҶиІ»
- ж°ҙйҒ“е…үзҶұиІ»
- йЈҹиІ»
- еҢ»зҷӮиІ»
- дёҠд№—гҒӣд»Ӣиӯ·иІ»
- д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…еҲҶ
- гҒқгҒ®д»–пјҲзҗҶзҫҺе®№иІ»гғ»гҒҠгӮҖгҒӨд»ЈгҒӘгҒ©пјү
дёҠиЁҳгҒҜдёҖдҫӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиіғж–ҷгғ»з®ЎзҗҶиІ»гғ»йЈҹиІ»гғ»ж°ҙйҒ“е…үзҶұиІ»гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®е…Ҙеұ…иҖ…гҒҢж”Ҝжү•гҒҶй …зӣ®гҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒӘгҒ„ж–№гҒҜд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…еҲҶгӮ„дёҠд№—гҒӣд»Ӣиӯ·иІ»гҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮзҗҶзҫҺе®№гӮ’ж–ҪиЁӯеӨ–гҒ§еҸ—гҒ‘гӮӢж–№гӮӮеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®и«ӢжұӮгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҗд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯгҖ‘
- зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ5пҪһ15дёҮеҶҶ
- д»Ӣиӯ·иҖҒдәәдҝқеҒҘж–ҪиЁӯпјҡ8пҪһ20дёҮеҶҶ
- д»Ӣиӯ·еҢ»зҷӮйҷўпјҡ9пҪһ15дёҮеҶҶ
зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§гҒҜгҖҒиӨҮж•°еҗҚгҒҢдёҖгҒӨгҒ®йғЁеұӢгҒ§е°ұеҜқгҒҷгӮӢеӨҡеәҠе®ӨгӮҝгӮӨгғ—гҒ§4.4дёҮгҖңзҙ„12дёҮеҶҶгҒЁгҖҒзӣёе ҙгӮҲгӮҠгӮӮжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒҢе®үгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғҰгғӢгғғгғҲеһӢпјҲгғҰгғӢгғғгғҲеһӢеҖӢе®ӨпјүгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе»ҠдёӢгӮ„гғӣгғјгғ«гӮ’еӣІгӮ“гҒ§еҖӢе®ӨгҒҢеҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜгҖҒ6.8дёҮгҖңзҙ„15дёҮеҶҶгҒҢзӣёе ҙгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯпјҲдҪҸгҒҫгҒ„пјүгҖ‘
- еҒҘеә·еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ10пҪһ40дёҮеҶҶ
- д»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ15пҪһ30дёҮеҶҶ
- дҪҸе®…еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ12пҪһ30дёҮеҶҶ
- йӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјҡ0пҪһ14дёҮеҶҶ
- гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҡ6гҖң20дёҮеҶҶ
- гӮ°гғ«гғјгғ—гғӣгғјгғ пјҡ12пҪһ18дёҮеҶҶ
й«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒ„гӮҝгӮӨгғ—гҒҜжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮұгӮўгғҸгӮҰгӮ№пјҲи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ пјүгҒҜгҖҒдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®ж–ҪиЁӯгҒҜиІ»з”ЁгҒҢе®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»Ӣиӯ·еһӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’д»ҳеёҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜиІ»з”ЁиІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒЁгҒҜ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®еұ…дҪҸгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒ®дёҖйғЁгҒҢгҖҢеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҖҚгҒ§еҫҙеҸҺгҒ•гӮҢгӮӢиІ»з”ЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еүҚгӮӮгҒЈгҒҰе…Ҙеұ…иҖ…гҒҢж–ҪиЁӯеҒҙгҒ«й җгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҒҠйҮ‘гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…Ҙеұ…еҫҢгҒҜеүҚжү•гҒ„еҲҶгҒӢгӮү家иіғгҒҢе„ҹеҚҙгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮжҜҺж—ҘгҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ§гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҒҠйҮ‘гҒҜжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒЁгҒ—гҒҰеҲҘйҖ”и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиіғж–ҷгҒ гҒ‘гҒҜеүҚжү•гҒ„гҒӢгӮүе„ҹеҚҙгҒҷгӮӢгҒ¶гӮ“гҖҒжңҲгҖ…гҒ®иІ жӢ…гҒҢи»ҪгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е„ҹеҚҙгҒҜдәӢеүҚгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹжңҹй–“гҒ®дёӯгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжңҹй–“гҒ®зӣ®е®үгӮ„еҲқжңҹе„ҹеҚҙзҺҮгҒҜж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ е…Ҙеұ…жҷӮгҒ®иІ»з”ЁгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„ж–№жі•
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒ®гӮҝгӮӨгғ—гҒҜгҖҒе…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„гғ»дёҖйғЁеүҚжү•гҒ„гғ»жңҲжү•гҒ„гҒ®3зЁ®йЎһгҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖиҲ¬гҒ®иіғиІёзү©д»¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжңҲгҖ…гҒ®иІ»з”ЁгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶж–№ејҸгҒҜгҖҢжңҲжү•гҒ„ж–№ејҸгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜдёҖжӢ¬гҒ—гҒҰж”Ҝжү•гҒҶгҖҢе…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„гҖҚгҒЁе…ЁдҪ“гҒ®дёҖйғЁгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҖҢдёҖйғЁеүҚжү•гҒ„гҖҚгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
ж”Ҝжү•гҒҶиІ»з”ЁгҒ®з·ҸйЎҚгҒ«йҒ•гҒ„гҒҢеҮәгҒҹгӮҠгҖҒйҖҖеҺ»гҒ®гҒЁгҒҚгҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢйҮ‘йЎҚгҒ«йҒ•гҒ„гҒҢгҒҝгӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж”Ҝжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®иҰӢеӯҰжҷӮгҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж”Ҝжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„
е…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜгҖҒеҝ…иҰҒгҒӘеҲқжңҹиІ»з”ЁгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰж”Ҝжү•гҒҶж–№ејҸгҒ§гҒҷгҖӮ
еүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜе…Ҙеұ…еҫҢгҒ«дҪ•е№ҙгӮӮдҪҸгҒҝз¶ҡгҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҖҒе°ҶжқҘгҒ®е®¶иіғгӮ’е…Ҳжү•гҒ„гҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮжғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹй–“гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжңҹй–“гҒ®е®¶иіғгӮ’е…Ҳжү•гҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖйғЁеүҚжү•гҒ„гӮ„жңҲжү•гҒ„гҒҜгҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгӮ’еҲҶеүІгҒ—гҒҰжңҲйЎҚж–ҷйҮ‘гҒЁеҗҲз®—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒжҜҺжңҲгҒ®иІ»з”ЁиІ жӢ…гҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…ЁйЎҚгӮ’еүҚжү•гҒ„гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жңҲйЎҚж–ҷйҮ‘гӮ’жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«ж”Ҝжү•гҒ„гӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒе…Ҙеұ…еҫҢгҒҜжңҖдҪҺйҷҗгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒ§жёҲгӮҖзӮ№гҒҢгғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®еҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҒҢдёӢгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹеҲҶгҒ®иҝ”йҮ‘гҒҜгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дёҖйғЁеүҚжү•гҒ„
дёҖйғЁеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜгҖҒе…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒ®дёҖйғЁгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮ
е…ЁдҪ“гҒ®дёҖйғЁгӮ’еүҚжү•гҒ„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„ж–№ејҸгӮҲгӮҠгӮӮиІ жӢ…гҒҜи»ҪгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒжңҲгҖ…гҒ®жңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ«ж®ӢгӮҠгҒҢдёҠд№—гҒӣгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиІ жӢ…гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒжғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹй–“еҲҶгҒ®гҒҫгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹиІ»з”ЁгӮ’еүҚгӮӮгҒЈгҒҰж”Ҝжү•гҒ„зөӮгҒҲгҒҹгҒ„ж–№гҒ«гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„ж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҲжү•гҒ„
жңҲжү•гҒ„ж–№ејҸгҒҜгҖҒеүҚжү•гҒ„гӮ’гҒӣгҒҡгҒ«жұәгҒҫгҒЈгҒҹжңҲйЎҚиІ»з”ЁгӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҸж–№ејҸгҒ§гҒҷгҖӮ
иіғиІёдҪҸе®…гҒЁеҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒЁеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ«гҒҜ家иіғгӮ„гҒқгҒ®д»–гҒ®иІ»з”ЁгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜзҗҶзҫҺе®№гӮ„йҖҒиҝҺгҖҒиІ·гҒ„зү©д»ЈиЎҢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢй »еәҰгҒҢеӨҡгҒ„гҒ»гҒ©жңҲйЎҚиІ»з”ЁгӮӮй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еүҚжү•гҒ„гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе°ҶжқҘгҒ®е®¶иіғгӮ’е…Ҳжү•гҒ„гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒҜгҒқгҒ®гҒҫгҒҫи«ӢжұӮгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒеүҚжү•гҒ„гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иІҜи“„гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸеҸ–гӮҠеҙ©гҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒҢиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒҜ家иіғгҒҢжү•гҒҲгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«иЈңгҒҰгӮ“гҒ•гӮҢгӮӢгҒҠйҮ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҜиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒҢиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҖ‘
- жғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹй–“гӮҲгӮҠгӮӮж—©гҒҸгҒ«йҖҖеҺ»гҒ—гҒҹе ҙеҗҲ
- гӮҜгғјгғӘгғігӮ°гӮӘгғ•гҒ«гӮҲгӮӢиҝ”йӮ„
- жғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹй–“гҒ®еүҚгҒ«жӯ»дәЎгҒ—гҒҹе ҙеҗҲ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒҜгҖҒжғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹй–“гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжңҹй–“гӮ’еҹәжә–гҒ«иЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҖҒе…ЁйЎҚгҒҫгҒҹгҒҜдёҖйғЁгҒ®гҒҝеүҚжү•гҒ„гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе…Ҙеұ…иҖ…гҒҢеүҚжү•гҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒжғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹгӮҲгӮҠж—©гҒҸгҒ«жӯ»дәЎгҒҫгҒҹгҒҜйҖҖеҺ»гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒе„ҹеҚҙжңҹй–“гҒҢйҒҺгҒҺгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒжңӘе„ҹеҚҙеҲҶгҒҢиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…гҒӢгӮү90ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°зҹӯжңҹи§Јзҙ„гҒЁгҒ—гҒҰгӮҜгғјгғӘгғігӮ°гӮӘгғ•гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮеҝ…иҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжңҹй–“еҶ…гҒ«гӮҜгғјгғӘгғігӮ°гӮӘгғ•гӮ’з”ігҒ—еҮәгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жңӘе„ҹеҚҙеҲҶгҒ®иҝ”йӮ„гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ®еҲ©зӮ№
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гҒҜгҖҒ家иіғгҒ®е…Ҳжү•гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰж”Ҝжү•гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮе®ҹиіӘзҡ„гҒӘ家иіғгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеүҚжү•гҒ„гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҜжҜҺжңҲе°‘гҒ—гҒҡгҒӨе„ҹеҚҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҲгҖ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁиІ жӢ…гҒҢи»ҪгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒе„ҹеҚҙжңҹй–“гӮ’йҒҺгҒҺгҒҰгҒӢгӮүгӮӮе…Ҙеұ…гҒҢз¶ҷз¶ҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮжғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹй–“гҒҢжәҖдәҶгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«йҖҖеҺ»гӮ„жӯ»дәЎгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒжғіе®ҡеұ…дҪҸжңҹй–“гҒ®ж®ӢгӮҠгҒ«еүІгӮҠеҪ“гҒҰгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж®ӢйҮ‘гҒҢиҝ”еҚҙгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж”Ҝжү•гҒ„жҗҚгҒ«гҒӘгӮӢеҝғй…ҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜж•°еҚғдёҮгҖңж•°е„„еҶҶгҒ«гҒ®гҒјгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜз„ЎзҗҶгҒ®гҒӘгҒ„зҜ„еӣІгҒ§ж–ҷйҮ‘гғ—гғ©гғігҒҢзө„гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖжҷӮйҮ‘гҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„ж–ҪиЁӯгӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғ—гғ©гғігӮ’гӮҲгҒҸзўәиӘҚгҒ—гҒҰжӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒжңҲжү•гҒ„гҒ§5е№ҙй–“гҒ®еҗҲиЁҲйЎҚгҒҢ1,800дёҮеҶҶгҒ«гҒӘгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒёгҒ®е…Ҙеұ…гӮ’иҖғгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮе…ЁйЎҚеүҚжү•гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰе…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘600дёҮеҶҶгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгғ‘гӮҝгғјгғігҒЁгҖҒ0еҶҶгҒ®гғ‘гӮҝгғјгғігҒ®гӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶе ҙеҗҲ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘600дёҮеҶҶгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгғ‘гӮҝгғјгғігҒ§гҒҜгҖҒ1,800дёҮеҶҶгҒӢгӮүгҒҷгҒ§гҒ«600дёҮеҶҶгӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжңҲгҖ…гҒ®иІ»з”ЁгҒҜ20дёҮеҶҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®и©Ұз®—гҒҜгӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжңҲйЎҚ20дёҮеҶҶгӮ’дёӢеӣһгӮӢж–ҪиЁӯгӮӮеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ©гҒ®ж–ҪиЁӯгӮӮеүҚжү•гҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒҢдҪҺгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж–ҷйҮ‘дҪ“зі»гӮ’зўәиӘҚгҒ®гҒҶгҒҲгҖҒз„ЎзҗҶгҒ®гҒӘгҒ„ж”Ҝжү•гҒ„гҒҢеҸҜиғҪгҒӘгғ—гғ©гғігғ»ж–ҪиЁӯгӮ’йҒёгҒігҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒ„е ҙеҗҲ
е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒ„гғ‘гӮҝгғјгғігҒҜгҖҒ1,800дёҮеҶҶгӮ’5е№ҙпјҲ60гғ¶жңҲпјүгҒ§еүІгҒЈгҒҹ30дёҮеҶҶгҒҢжңҲгҖ…гҒ®иІ»з”ЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгғ‘гӮҝгғјгғігӮҲгӮҠгӮӮй«ҳйЎҚгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеүҚжү•гҒ„гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒж”Ҝжү•гҒ„гҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ®дҝқиЁјгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ж”Ҝжү•гҒ„гҒҢеӣ°йӣЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгӮҲгӮҠе®үгҒ„ж–ҪиЁӯгҒёи»ўеұ…гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеј•гҒЈи¶ҠгҒ—гӮ„гҒқгҒ®д»–гҒ®иІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢзӮ№гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒёгҒ®е…Ҙеұ…иІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢж–№жі•
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜиЁӯеӮҷгҒҢж•ҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒ»гҒ©й«ҳйЎҚгҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®ж–ҪиЁӯгҒҢй«ҳзҙҡгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢе ҙеҗҲгҒ«гӮӮгҖҒиІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҲ¶еәҰгҒҢеҲ©з”ЁеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
иІ»з”ЁгҒ®е®үгҒ„ж–ҪиЁӯгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢ
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгӮ„жңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒҢе®үгҒ„ж–ҪиЁӯгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеүҚжү•гҒ„гҒҢжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гӮ’и»ҪгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁгҒҜгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеүҚжү•гҒ„гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиІҜи“„гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸжёӣгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®з”ҹжҙ»гҒ«иІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иІ»з”ЁгҒ®е®үгҒ„ж–ҪиЁӯгҒЁгҒҜгҖҒең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“гӮ„зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәгҒҢйҒӢе–¶гҒҷгӮӢе…¬зҡ„ж–ҪиЁӯгҒҢд»ЈиЎЁзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮж–ҪиЁӯгҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҖҒеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҜ”ијғгҒ—гҒҰжұәгӮҒгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢ
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒҜгҖҒ1гғ¶жңҲгҒ«ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹиІ жӢ…йЎҚгҒ®еҗҲиЁҲгҒҢйҷҗеәҰйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒи¶…йҒҺеҲҶгӮ’жү•гҒ„жҲ»гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®еҲ©з”ЁгҒ§гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…йЎҚгҒҢдёҠйҷҗгӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒж”Ҝжү•гҒЈгҒҹеҲҶгҒЁдёҠйҷҗйЎҚгҒ®е·®йЎҚгҒҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒӢгӮүж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғе…ғпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®иІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҒҢиҰӢзӣҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖҚ
й«ҳйЎҚеҢ»зҷӮгғ»й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·еҗҲз®—зҷӮйӨҠиІ»еҲ¶еәҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢ
й«ҳйЎҚеҢ»зҷӮгғ»й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·еҗҲз®—зҷӮйӨҠиІ»еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮдҝқйҷәгҒЁд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…йЎҚгҒҢи‘—гҒ—гҒҸй«ҳйЎҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒиІ жӢ…гӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
з”іи«ӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰи¶…йҒҺеҲҶгҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжүҖеҫ—еҢәеҲҶгҒ«еҝңгҒҳгҒҹиҮӘе·ұиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ70гҖң75жӯігҒ§дҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜпјҲжүҖеҫ—гҒҢ145дёҮеҶҶжңӘжәҖпјүгҒ®ж–№гҒҜгҖҒиҮӘе·ұиІ жӢ…йҷҗеәҰйЎҚгҒҢ56дёҮеҶҶгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғе…ғпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢй«ҳйЎҚеҢ»зҷӮгғ»й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·еҗҲз®—зҷӮйӨҠиІ»еҲ¶еәҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҚ
зҰҸзҘүз”Ёе…·гӮ„家具гӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮҖ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ§гҒҜгҖҒз”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж—Ҙз”Ёе“ҒгӮ„家具гғ»е®¶йӣ»пјҲзҷәзҒ«гҒӘгҒ©гҒ®еҚұйҷәгҒҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®пјүгҒ®жҢҒгҒЎиҫјгҒҝгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҷгҒ§гҒ«иҮӘе®…гӮ„гҒқгҒ®д»–гҒ®е ҙжүҖгҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢи»ҠжӨ…еӯҗгӮ„гҒӨгҒӢгҒҫгӮҠз«ӢгҒЎз”ЁгҒ®гӮ№гӮҝгғігғүгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®ж–ҪиЁӯгҒ§гҒҜгҒқгҒ®гҒҫгҒҫжҢҒгҒЎиҫјгҒҝгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
ж–ҪиЁӯгҒ§ж–°гҒҹгҒ«жҸғгҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгғ¬гғігӮҝгғ«гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгғ¬гғігӮҝгғ«д»ЈгҒҢеҠ з®—гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ§жҸғгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁе®үеҝғгҒ§гҒҷгҖӮ
иҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®е…Ҙеұ…дёҖжҷӮйҮ‘гӮ„еҲқжңҹиІ»з”ЁгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢ
д»ҠеӣһгҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ®жҰӮиҰҒгӮ„дё»гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒе…Ҙеұ…гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒЁиІ»з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ©гҒ®ж–ҪиЁӯгҒ§гӮӮжңҲйЎҚж–ҷйҮ‘гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгҒ®еҶ…е®№гӮ„йҮ‘йЎҚгҒҜдёҖеҫӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒдәӢеүҚгҒ«гӮҲгҒҸзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еүҚжү•гҒ„гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ©гҒ®зЁӢеәҰжңҲйЎҚиІ»з”ЁгҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒҫгҒҹжҜҺжңҲгҒ®з”ҹжҙ»гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гӮ’иҖғгҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ家ж—ҸгӮ„еҪ№жүҖгғ»еҪ№е ҙгҒ®зҰҸзҘүиӘІгҖҒең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҒ§гӮҲгҒҸи©ұгҒ—еҗҲгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
иІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҲ¶еәҰгӮӮгҒҶгҒҫгҒҸжҙ»з”ЁгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒзҙҚеҫ—гҒ®гҒ§гҒҚгӮӢз’°еўғгӮ’йҒёгҒігҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢ笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ жҺўгҒ—гҒӢгӮүгҖҒе…Ҙеұ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҒҫгҒ§е№…еәғгҒҸеҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮй–ўиҘҝгҒ§е…Ҙеұ…гӮ’жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгӮүгҖҒгҒңгҒІз§ҒгҒ©гӮӮгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮдәҲз®—гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ”зҙ№д»ӢгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

зӣЈдҝ®иҖ…
иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү
дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«
жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ
гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ
д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«
зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
-

гҖҗзӣёи«ҮдәӢдҫӢгҖ‘еҢ»зҷӮгӮұгӮўгҒЁQOLгӮ’дёЎз«ӢгҖӮеҢ»зҷӮгӮұгӮўгҒҢеҝ…иҰҒгҖҒгҒ§гӮӮгғ¬гӮҜгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғіиұҠеҜҢгҒӘж–ҪиЁӯе…Ҙеұ…гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹдәӢдҫӢпјҡе әгӮЁгғӘгӮў еҘҘз”°зӣёи«Үе“Ў vol.2
-

гӮөгғјгғ“гӮ№д»ҳгҒҚй«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘дҪҸе®…пјҲгӮөй«ҳдҪҸпјүгҒЁгӮ·гғӢгӮўеҗ‘гҒ‘еҲҶиӯІгғһгғігӮ·гғ§гғігҒ®йҒ•гҒ„гӮ’еҫ№еә•жҜ”ијғпјҒиІ»з”ЁгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒеҘ‘зҙ„еҪўж…ӢгҒҫгҒ§
-

й«ҳйҪўиҖ…еҗ‘гҒ‘е„ӘиүҜиіғиІёдҪҸе®…гҒЁгҒҜпјҹе…Ҙеұ…еҹәжә–гҒӢгӮүиІ»з”ЁгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒҫгҒ§еҫ№еә•и§ЈиӘ¬
-

зү№е®ҡж–ҪиЁӯгҒЁгҒҜпјҹд»Ӣиӯ·д»ҳгҒҚгғ»дҪҸе®…еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒӢгӮүе…Ҙеұ…гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҫгҒ§еҫ№еә•и§ЈиӘ¬
-

гғӣгӮ№гғ”гӮ№гҒЁгҒҜпјҹзөӮжң«жңҹгӮ’з©ҸгӮ„гҒӢгҒ«йҒҺгҒ”гҒҷгҒҹгӮҒгҒ®ж–ҪиЁӯйҒёгҒігҒЁз·©е’ҢгӮұгӮўгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰ
-

дҪҸе®…еһӢжңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒЁгӮөй«ҳдҪҸгҒ®йҒ•гҒ„гҒЁгҒҜпјҹе…Ҙеұ…жқЎд»¶гғ»иІ»з”Ёгғ»гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҫ№еә•жҜ”ијғ



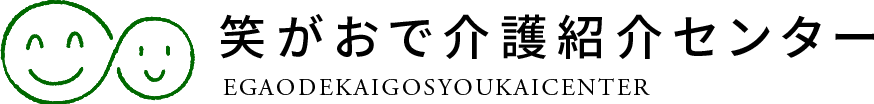




 0120-177-250
0120-177-250