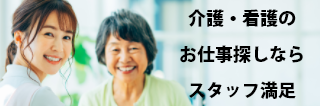成年後見制度とその落とし穴【カイゴのゴカイ 27】

認知症と成年後見制度
さて、前回認知症の予防の話を書いたが、認知症の予防は無理だが、頭を使うことでなるのを遅らせることや進行を遅らせることは可能というのが趣旨だった。
ただ、レーガン大統領やサッチャー首相のように頭を使っている人でも、結局は認知症になっている。(私はレーガン大統領やサッチャー首相が大統領や首相になっていなければもっと早く認知症を発症していたはずだと考えている)
今回、認知症になってしまってからの対応の中で、その財産を守るための制度、成年後見制度についてお話ししたい。
軽度認知症の判断力
前にも書いたが認知症というのは、軽いうちなら大統領でも務まる病気で、記憶障害が目立っても人の話は、かなり重くなるまで理解できるし、判断力だって、軽いうちなら、そんなに普通の高齢者と変わらない。
たった数人の高齢者が死亡事故を起こせば、高齢者全体から免許を取りあげろというような乱暴で短絡的な判断力と比べたら、数学のできる軽度認知症の高齢者のほうが、はるかに判断力は高いだろう。
認知機能テストである一定より低い点を取った場合、認知症の診断を受けたら、免許が失効するが、これにしても認知症の程度を問わずに、認知症の診断を受けたらというのは明らかに誤解に基づく法律としか言いようがない。(実際は認知機能テストはかなり易しいものだから、これに落ちたら自動的に中等度以上の認知症とは言えるが)
中等度以上の認知症
実際は、中等度以上の認知症でもできることはいくらでもある。
料理にしても、農業にしても、子守のようなことでも、それどころか子どもに字や簡単な算数を教えることもできることが多い。
認知症の人の運転にしても、道に迷いやすいということはあっても、わざと人をはねるようなことはほぼ考えられない。(幻覚が出ていたら別だが、これは認知症より薬の副作用のことが多い)その上、運転をやめると認知症の程度は進んでしまう。だから認知症という診断で免許を取り上げることは納得できない。
ちゃんと認知症の高齢者を診ている人が声を上げないと、こんな法律もこんな週間も絵にかいたモチにしかならないだろう。
認知症の判断力とトラブル
いっぽうで中途半端に判断力が落ちるためのトラブルは確かにある。
前に買ったことを忘れて、同じものをいくつも買うとか、不安をあおるようなセールスマンの言葉を素直に信じて、高額のリフォーム工事の契約を結ぶなどだ。
この場合、事前の対策で、それ以降の不本意や商行為を無効にすることができる。
法定後見制度
成年後見制度というもののなかで、法定後見制度という法的な拘束力があるものがある。
これは、家庭裁判所に申し入れをすると、どの程度のものに相当するのかとか、誰を成年後見人にするのかを選任するのかなどを裁判所が決めてくれる。
補助、補佐、後見の三段階があり、補助と補佐というのは、一人で手続きや契約を結ぶのが困難な人に成年後見人(補助人、補佐人)をつけて、本人とこの後見人の両方の署名捺印がなければ商行為や契約が成立しないというものだ。
本物の詐欺の場合は、この制度でも救われないが、同じものをいくつも買うとか、いかがわしい高額契約などの場合、この認定を受けていると、後見人の同意がないのなら商行為や契約そのものが成立していないので、取り消しが原則無料で可能になる。
そういう意味で、認知症を患う人の財産などを守るために有効な制度と言える。
法定後見制度の「後見」とは?
問題は「後見」である。
これに相当すると判断されると、本人には契約を行う能力や判断力は、実質的にないとみなされ、後見人が、その契約や判断を代行する。
要するに判断力がなくなった場合、たとえば老人ホームに入るために家を売るというような判断力が必要な行為について、後見人がすべて代行してくれるというものだ。
また後見人が預金をおろすなどのことも可能になる。
ある程度以上財産がある場合、認知症が重くなっても、その財産の管理や運用は任せる人がいるので、認知症になった人の生活は守られるというわけだ。
通常は、子どもや配偶者が後見人になるのだが、子どもが兄弟間で意見が一致していないために、財産の使い道に対してもめごとが起きそうな時や、配偶者が後妻などで子どもが財産管理を許せないなどという場合は、弁護士などが後見人になることもある。
本人の意思が無視される「後見」
誰を後見人にするのかも家庭裁判所が決めてくれる。
ただ、これを悪用されると怖い制度であるのも確かだ。
どんなに財産があっても、後見レベルの高度の認知症と家庭裁判所が判断すると、契約を行える判断力がないとみなされてしまう。
認知症になる前に見学に行って気に入った有料老人ホームがあって、そこに入れるだけの十分なお金と希望があっても、後見人が許してくれなければ、そこには入れない。
老人ホームの場合、10年くらいで入居金が償却される(10年経つと払った入居金が1円も返ってこなくなる)ことが多いので、財産をあてにしている子供などが、親の認知機能がしっかりしている場合でも、入居に反対することが珍しくないが、この後見になると、実質的に親の意志は完全に無視されてしまう。
法定後見制度の判定基準
私は、今の制度で完全に判断力がなくなるとみなされる基準が緩すぎると考えている。
改訂長谷川式簡易知能スケールで11点以下だと高度認知症と見なされ、後見レベルとされてしまうのだ。
この知能スケールを検索してもらえればわかると思うが、仮に10点しか取れていなくても、正答があるということはその問題の意味は理解しているし、10点取れていれば、それなりの意志も認知能力もある。
人の助けがあれば判断できると考えられるから、補佐で十分だと思うのだが、判断力ゼロの扱いを受けるのだ。
成年後見制度と意思能力
この成年後見制度は、本来は、認知症になった人の財産などを守るために作られた制度であるし、商行為や契約などでの判断力がどのくらいあるかを見るものなのに、つまり判断力があるかどうかの判定であるのに(だから、11点以下ということなのだろう)、意志能力の有無まで援用されることは珍しくない。
たとえば、自分に親切にしてくれる親族にいくばくかの財産を与えたいとか、場合によっては養子にしてあげたいと思ったとしても、その意志は重度の認知症だからといって認めてもらえない。
認知症に対する裁判所の実態
実は、私もある裁判で、判断力は重度認知症レベルでも(このときの長谷川式は4点だった)、テストで1点でも取れているということは問題の意味も理解しているし、人物も誤認しているのだから、養子にしたいという意志は認められるべきだという意見書を出したことがある。ところが裁判官の側から、この裁判で意思能力を認めるわけにいかないという話を事前にしてきて、結局、私に意見書を依頼した人が和解にしてしまった。
今の裁判所というのは、こんなに認知症の実態を知らないのかと暗澹たる気分になった。
認知症の感情と制度の差
認知症の人は理解できないことがあっても、自分の意志と反対のことを言ったり、思ってもいないことを言うようなことは、幻覚や妄想でもない限り、まずない。
普通名詞がでてこなくて、カレーが食べたいのに餃子が食べたいというようなことはあり得なくないが、これは本当に重症例で、テストでは1点も取れないレベルでの話だ。
養子にしたいというのは、気に入ったという感情をもったからで、認知症の人も、もちろんそういう感情をもつ。嫌な人を養子にしたいなどとは決して言わないのだ。
裁判所がきちんと認知症を理解しない限り、親族に勝手に成年後見の訴えを裁判所に出され、後見レベルの認知症と判定されれば、まったくお金も使えなくなる。
ラーメンが食べたいと言っても、そんな意志はないと適当なおかずを出されても文句は言えない。
任意後見
ただ、任意後見という制度を使って、自分が認知症になる前に、信用できると思って選んだ人に財産管理や意志の代行をしてもらうことはできる。
この人なら、自分が養子を選んだ時もその意志を尊重してくれるとか、自分の行きたい老人ホームを伝えておいて、それをきちんとやってくれるとか、カツカレーが食べたいと言えば、認知症になっても意志を尊重してくれるとか思える人に任意後見人になってもらえばいいのだ。
この契約がある限り、勝手に別の親族が後見人になることはできない。逆にこの契約がないと、勝手に後見制度を申請されると拒否できない。
超高齢社会の原則
自分は認知症になるはずがないと思うかもしれないが、85歳以上になるとテスト上認知症と判断される人は4割もいる。そして、後見の判断はテストで決められるのだ。
自分の子どもが絶対に信用できるという人はいいが、私の長年の高齢者をみてきた経験では、お金のために考えが変わる人はそんなに珍しくない。
自分の身は自分で守るというのが超高齢社会での原則だと私には思えてならない。
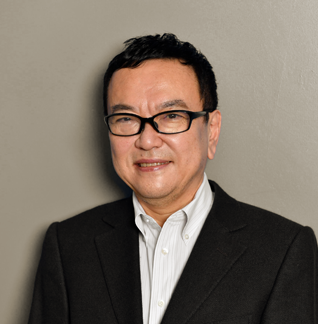
著者
和田 秀樹(わだ ひでき)
国際医療福祉大学特任教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科医師を歴任。
著書に「80歳の壁(幻冬舎新書)」、「70歳が老化の分かれ道(詩想社新書)」、「うまく老いる 楽しげに90歳の壁を乗り越えるコツ(講談社+α新書)(樋口恵子共著)」、「65歳からおとずれる 老人性うつの壁(毎日が発見)」など多数。
この記事の関連記事



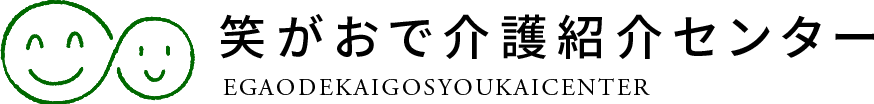




 0120-177-250
0120-177-250



とシニア向け分譲マンションの違い.webp)