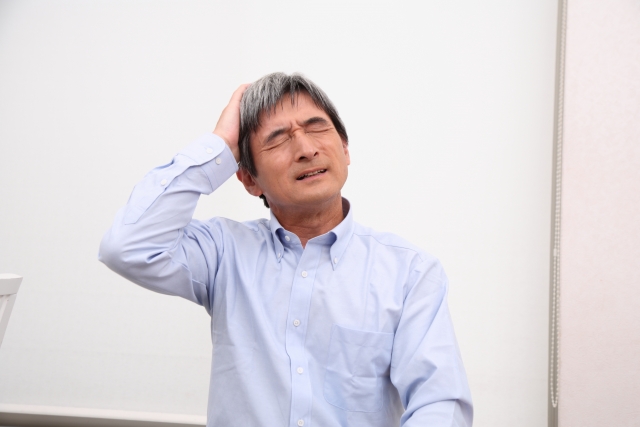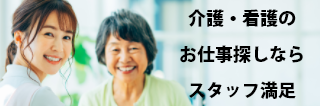定年後うつを避ける【カイゴのゴカイ 21】
介護のゴカイ

定年後うつと五月病の違い
五月病と適応障害とは
3月に、『老人性うつの壁』(KADOKAWA)という本を出したら、モーニングショーで定年後うつ(テレビ上のタイトルは定年後五月病)の話をすることになった。
五月病というのは、たとえば受験生が大学に入った後とか、新入社員が会社に入った後、1か月くらいで、意欲や気力が急におちて昼行燈みたいな状態になることを一般に指す。
この場合、その後、何かやりたいことや打ち込めることが見つかると、そういう虚脱状態からよくなることが多く、一か月くらいで元に戻るから五月病と呼ばれていたわけだ。
ただ、最近は、学校や職場に合わない状態がずっと続く人も珍しくなくなり、そういう人は、適応障害という診断を受ける。
自分が適応していない場(学校や職場)では、調子が悪いのだが、そうでない場(家に戻った後など)では、元気がいいので仮病みたいに思われがちだが、学校や職場に適応しようと焦るほど具合が悪くなるし、最悪、自殺することもあるのであなどれない病気と言える。
一般的には、その適応できない場を変える(転校とか、大学の受け直しとか、転職で)か、ものの見方を変える(一般的には心療内科か、カウンセリング治療で認知療法というものを受ける)ことで回復するし、進行性で悪くなることは少ない。それでも、本人にとってはつらい時期が続くので、治療を受けるに越したことはない。
定年後うつとは
それと比べて、定年後五月病というのは、私が実は定年後うつと呼んだように、定年後の一か月目くらいに症状が目立つのだが、すぐによくなることはまずないものだ。
会社に行かなくてよくなって、家でのんびりすると思っていたら、1週間たっても、二週間たっても、ほとんど外出しようとしない。
外出に誘っても気乗りがしないと断るパターンが多く、そういう無気力状態が1か月くらい続いて、医療機関を受診したりすることが多いので、五月病と呼ばれるようだ。
一日中、ボンヤリとテレビを見たりしているのだが、徐々に眠りが浅くなり、なんども目が覚めたり、食欲が少しずつ落ちてきたりする。
こうなってくるとうつ病と我々精神科医は診断することになる。
実は、60代というと40代くらいの人と比べて、生物学的にもうつ病になりやすい年代である。
定年後うつになりやすい理由
定年後うつにかかわるセロトニン
前にも説明したが、セロトニンという神経伝達物質が加齢に伴って減ってくる。
セロトニンが減ってくると、不安感が高まったり、イライラしやすくなり、最終的にはうつ病になってしまう。
加齢でそうでなくてもセロトニンが減っているところに、ショックなこと、嫌なことがあるとドンとセロトニンが減ってしまう。
失業というのは、若い人でもうつになることがあるくらいのショックなイベントなので、60歳や65歳の人にはそれだけ堪えるのだ。
そのためにそうでなくても脳内で減っているセロトニンが減ると、簡単にうつ状態に陥ってしまう。
その上に、このような引きこもり生活を続けているとセロトニンがどんどん減っていってしまう。
定年後うつとセロトニンが減少する理由①
一つは、セロトニンは光が目に入ると脳内で分泌されるのだが、家に閉じこもって、日光を浴びていないとその分泌が減ってしまう。とくに一日テレビをぼんやり見ているようなときは、部屋のほうは薄暗くしていることが多いからセロトニンが十分分泌されないということになりがちだ。
また、そうでなくても動かないのでお腹が空かないのに、セロトニンがだんだん減ってくると余計に食欲が落ちる。ついついあっさりしたものばかり食べるというようなことになってしまう。
セロトニンの材料はたんぱく質に含まれるトリプトファンというアミノ酸だし、それを脳に運ぶのはコレステロールなので、肉類が脳内でセロトニンを増やすのに最適な食べ物だ。すき焼きや焼き肉を食べると気分が上がるのもそのためとされている。ところが、こういう引きこもり生活を送っていると、肉類は避けられがちだ。
さらにセロトニンを増やすのは、軽い運動ということになっているのだが、これも家にこもった生活を送っていると、ろくに運動しないことになりがちだ。
ということで歳のせいで減っていたセロトニンが、失業でさらに減り、その後のひきこもり生活でよけいに減って、うつ病やうつ状態に陥ってしまう。
実は、50代後半や60代前半の人で、うつ病スレスレくらいセロトニンが減っている人は珍しくない(個人差はあるが)。
定年後うつとセロトニンの減少する理由②
そういう人でも職場に通っているうちは、否が応でも通勤で外出し、日にも当たるのでセロトニンが分泌される。昼ご飯などは人によるだろうが、週に何回かは肉類も摂るだろう。そして通勤は歩行というセロトニン分泌によい運動になる。
そういうわけでうつ状態にならないで済んでいた人が、仕事に通わなくなるとうつ状態のレベルまでセロトニンが下がってしまうということもあるのだ。
さて、こういう状態に陥ってしまったとき、若い頃の五月病なら、前述のように1か月くらいで治まることが多いのだが、この年代の五月病は放っておくと前述の理由でどんどん悪くなることが珍しくない。
もちろん、運よく、再就職が決まったり、ボランティアであれ、趣味であれ何かやりたいことが見つかって、そのまま回復する人もいるのだが、そうならないことのほうが多いだろう。
定年後うつを防ぐ方法
定年後うつは予防が重要
実は、脳内のセロトニンというのは薬で足せるようになっているし、それで食欲や睡眠が回復することが多い。やはり、食欲も落ちていて、夜中に何度も目が覚めるレベルになっているのなら、精神科や心療内科に行くのが賢明だ。
定年後五月病だから無職の状態に慣れればよくなるだろうという考えは甘いことはお伝えしておきたい。
さて、五月病であれうつ病であれ、本人にしてみたらつらい状態なのは確かだから、予防をするに越したことはない。
定年後うつの予防方法
最大の予防は、通勤という運動と外出の状態を確保するために、早めに再就職先や定年延長の機会を確保することだろう。
ただ、残念ながら、次の就職先でも年齢のために引退しなくてはいけなくなるのは確かだし、定年延長もどんなに長くても70歳くらいだろう。
要するに五月病やうつ病の先送りになってしまう。
可能なら、その後続けられる、外出を伴う趣味を見つけておく方がいいだろう。
あとは、人間関係だ。
日本の場合、定年した後、一緒に愚痴をこぼせる相手も、ゴルフ仲間もマージャンの相手もいなくなるというパターンが多い。定年で親しくできる人間関係を失うのだ。
定年した後もつきあえる相手を一人でも探しておくと、その人がいろいろと誘ってくれる可能性もあるし、会話によってうつをかなり予防できる。
日常生活も大切だ。
前述のように定年でセロトニンが減る生活に陥らないように、定年後も朝の散歩を日課にしたり、たんぱく質や肉類を摂る生活を続けることだ。これは意外にバカにならないことだ。
それ以上に大切なのは、ものの見方、考え方を変えることだ。
「働かざる者、食うべからず」というようなかくあるべし思考を捨て、定年で労働から解放されたのだ(ヨーロッパではこんな風に考えられている)と思うというような意識改革をする。
要するに、会社に勤めていない、働いていない、役職や肩書のない自分を受け入れることだ。
これができないと自分はダメになってしまった、役立たずだ、価値がないなどという考えに囚われてすぐに抑うつ的になってしまう。
専業主婦にとっての定年後うつ
実は、専業主婦であっても似たようなことが起こる。
子どもを育て、子どもの世話をしていた頃は、母親アイデンティティのようなものが心の支えになるが、子どもが離れてしまうと、自分が役立っているように思えなくなる。すると、定年後の夫を過度に面倒をみたり、親の介護に打ち込んでしまって、自分の人生もなくなってしまうし、燃え尽きてしまうようなこともある。
やっと子育てから解放されたのだから自由に生きようくらいに思ってちょうどいいのだ。
定年後うつのまとめ
さて、定年後五月病では、無気力、意欲低下のようなことが主症状になるのだが、意外にうつ病の薬では、睡眠や食欲、不安感などは改善しても、意欲が出ないことが多い。
実は、この年代のもう一つの問題として前にも説明した男性ホルモンの低下がある。そしてうつ状態、うつ病になると余計に男性ホルモンが減ることも知られている。
意欲が出ない状態が長く続いた場合は、一度、男性ホルモンの検査を受けてほしい。
一定より値が低い場合は、保険で男性ホルモン補充治療が受けられるので経済的負担も少ない。
とりあえず、定年後五月病を甘く見ないということをお伝えしたい。
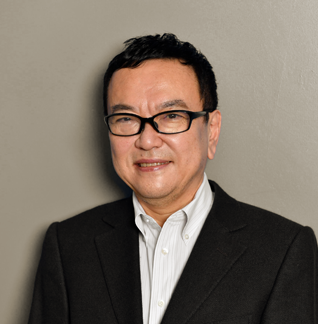
著者
和田 秀樹(わだ ひでき)
国際医療福祉大学特任教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科医師を歴任。
著書に「80歳の壁(幻冬舎新書)」、「70歳が老化の分かれ道(詩想社新書)」、「うまく老いる 楽しげに90歳の壁を乗り越えるコツ(講談社+α新書)(樋口恵子共著)」、「65歳からおとずれる 老人性うつの壁(毎日が発見)」など多数。
この記事の関連記事

定年後うつを避ける【カイゴのゴカイ 21】
定年後うつと五月病の違い 五月病と適応障害とは …
定年後うつと五月病の違い 五月病と適応障害とは …

高齢者の運転と薬の危険性【カイゴのゴカイ 20】
高齢者の交通事故と意識障害 高齢者の目立つ事故の不…
高齢者の交通事故と意識障害 高齢者の目立つ事故の不…
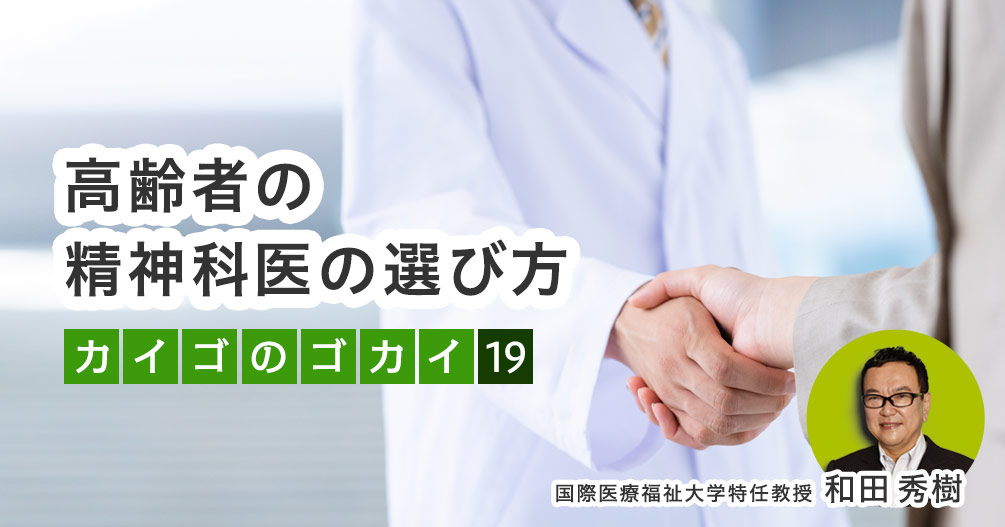
高齢者の精神科医の選び方【カイゴのゴカイ 19】
高齢者のうつ病や介護うつと精神科医の選び方とは 高…
高齢者のうつ病や介護うつと精神科医の選び方とは 高…

老人介護は日本の美風か【カイゴのゴカイ 18】
古い価値観や義務感が看護の負担に この介護の誤解につい…
古い価値観や義務感が看護の負担に この介護の誤解につい…

せん妄を知る【カイゴのゴカイ 17】
せん妄とは意識の混乱のこと 超高齢社会になり、人口の3…
せん妄とは意識の混乱のこと 超高齢社会になり、人口の3…

栄養学の大切さ【カイゴのゴカイ 16】
超高齢社会における高齢者の栄養状態と長生き 日本の医学…
超高齢社会における高齢者の栄養状態と長生き 日本の医学…

介護保険を受けよう【カイゴのゴカイ 15】
多くの人が要介護状態への備えをしていない これまで、い…
多くの人が要介護状態への備えをしていない これまで、い…

外見を若く保つという老化予防術【カイゴのゴカイ 14】
男性ホルモンと意欲の関係 前回、今の時代は80歳までは…
男性ホルモンと意欲の関係 前回、今の時代は80歳までは…
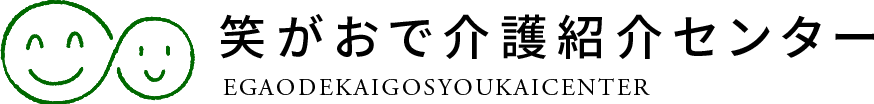




 0120-177-250
0120-177-250